Category Archives: カテゴリーなし
エグゼクティブ・サマリー
AI(人工知能)を巡る規制は、もはや技術部門や法務部門だけの問題ではなく、企業の事業戦略そのものを左右する重要な要素となっています。特に、EUと日本の両市場でAIを開発・提供・利用する企業にとっては、両者の規制アプローチの違いを正確に理解することが不可欠です。本稿は、EUと日本におけるAI規制の考え方の違いを整理し、それが企業実務にどのような影響を与えるのかを、実務の視点から解説するものです。
EUは、EU AI法(EU Artificial Intelligence Act)により、AIをリスクに応じて分類し、高リスクと位置付けられるAIについては、市場投入前から詳細なガバナンス体制、技術文書の整備、適合性評価等を求める包括的かつ拘束力のある制度を採用しました。EU市場への進出やサービス提供を行う企業にとって、AI規制対応は付随的なコンプライアンス事項ではなく、プロダクト設計や市場参入戦略の中核的な検討事項となりつつあります。
これに対し、日本は、AIに特化した包括的なハードローを導入するのではなく、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(いわゆるAI推進法)を中心に、研究開発・社会実装を促進しつつ、個人情報保護法や労働法、消費者保護法等の既存法制によって具体的なリスクに対応するという政策を採っています。このイノベーション重視・事後的責任追及型のモデルは、初期段階での規制負担を抑える一方、企業には内部ガバナンスや説明可能性の確保が強く求められます。
クロスボーダーでAIビジネスを展開する企業にとって、こうした違いは、コンプライアンスコスト、開発スケジュール、組織体制の設計に直接的な影響を及ぼします。EU基準に合わせた対応が一つのベースラインとなる場合もありますが、それだけで日本法上の論点が解消されるわけではありません。逆に、日本市場を前提に設計されたAIシステムは、EU市場に展開する際に大幅な見直しを迫られることもあります。本稿が、こうした判断を行う際の実務的な指針となることを意図しています。
1. はじめに:AI規制はなぜ事業戦略の問題なのか
なぜ各国のAI規制はこれほど異なる方向に進んでいるのか、そしてその違いは企業実務にどのような影響を与えるのか。
AI規制を巡る議論は、「EUは厳しい」「日本は緩やか」といった単純な対比で語られがちです。しかし、この捉え方だけでは、企業実務にとって本質的な問題を見誤るおそれがあります。重要なのは、規制の厳しさそのものではなく、各国がどのような制度設計によってAIリスクに向き合い、その結果として企業の意思決定や事業運営にどのような影響が生じるのかという点です。
EUと日本の対比が特に示唆的なのは、両者が「信頼できるAIの実現」や「社会的リスクの抑制」といった政策目的を共有しながらも、まったく異なる法的枠組みを選択している点にあります。EUは、AI専用の包括的な法制度を通じて、事前のリスク管理と市場投入前の統制を重視するアプローチを採用しました。一方、日本は、既存の法制度と行政実務の中にAIガバナンスを位置付け、問題が顕在化した段階で対応するという枠組みを基本としています。
こうした制度設計の違いは、企業にとって抽象的な法政策論にとどまりません。それは以下のような日常的な実務判断に直結します。
- どの段階で法務レビューが必要になるのか
- どの程度の文書化が市場投入前に求められるのか
- 規制当局の執行リスクをどのように評価すべきか
- 製品開発のタイムラインにどの程度の余裕を見込むべきか
- 組織内のどの部署が主導的に対応すべきか
本稿では、いずれの制度が規範的に望ましいかを論じることを目的とはせず、EUと日本のAI規制が実務上どのように機能しているのか、そして両市場でAIを活用する企業が何を理解しておくべきかを明らかにします。まず両者の規制思想を整理し、次に各制度の具体的内容を確認した上で、実務的な比較とケーススタディを通じて企業への影響を検討し、最後に企業が取るべき対応のポイントを提示します。
2. EUと日本の規制思想: ハードローとソフトロー
EUと日本のAI規制を比較する際の出発点は、「新しい技術をどのような法形式で規律するか」という根本的な問いにあります。すなわち、法的拘束力を伴う明確な義務を事前に課すべきか、それとも柔軟性を重視したガイドラインや既存法制による事後的な対応を中心とすべきか、という問題です。
ハードローとは、一般に、法的拘束力を有し、違反した場合に裁判所や行政機関による制裁が科され得る規範を指します。法律、政令、省令といった形式で明文化され、執行機関による強制が可能です。ハードローの利点は、法的確実性が高く、権利義務関係が明確になる点にあります。企業にとっては、何が許され何が禁じられているかが事前に分かるため、長期的な投資判断やコンプライアンス体制の構築がしやすくなります。
ソフトローとは、法的拘束力自体は有しないものの、行政指導や業界慣行、レピュテーション(評判)、市場の期待を通じて行動を方向付ける規範を意味します。ガイドライン、ベストプラクティス、原則声明などがこれに該当します。ソフトローの利点は、技術進展や社会状況の変化に応じて柔軟に更新できる点、そして事業者の創意工夫の余地を残せる点にあります。
2.2. AIにおけるハードローとソフトローのトレードオフ
AIのように技術進展が速く、社会的影響の射程が不確定な分野においては、この選択は特に重要な意味を持ちます。
(1) ハードローの利点と課題
利点として、ハードローは責任の所在を明確にし、基本的権利を強く保護できます。特に、AIが雇用、信用評価、社会的サービスへのアクセスといった重要な場面で用いられる場合、明確な法的保護があることで、個人の権利が侵害されるリスクを低減できます。また、域内での統一的な基準を設けることで、企業にとっても複数国での展開が容易になり得ます。
他方で課題もあります。技術の進展速度が速い分野では、法制度が実態に追いつかず、時代遅れになるリスクがあります。また、詳細な規制は、特に資金や人材に限りのあるスタートアップや中小企業にとって過度な負担となり、イノベーションを阻害する可能性があります。
(2) ソフトローの利点と課題
ソフトローは、変化への適応力に優れています。ガイドラインであれば、新たなリスクが判明した際に速やかに更新することができます。また、事業者に自主的な工夫の余地を残すことで、多様なアプローチが試され、社会全体として最適な解決策が見つかりやすくなる可能性があります。
しかし、ソフトローには予見可能性の低さという課題があります。何が法的に許容されるのかが明確でないため、企業は慎重にならざるを得ず、かえって萎縮効果が生じることもあります。また、実効性や説明責任のメカニズムが弱く、実際に問題が生じた際の対応が後手に回るリスクもあります。
2.3. EUと日本の選択
EUと日本は、このトレードオフに対して明確に異なる解を示しました。
EUの選択は、域内での統一的なルールと高い法的確実性を優先するものです。単一市場を形成するEUにとって、加盟国間での規制の断片化を防ぎ、企業が複数国で一貫した対応をとれるようにすることは重要な政策目標です。また、基本的人権の保護を重視するEU法の伝統からも、AIによる権利侵害リスクに対して明確な法的保護を設けることは自然な選択でした。
日本の選択は、国際競争力の維持や実証実験の促進を重視するものです。日本政府は、AI分野において諸外国に遅れをとっているという認識を持っており、規制による過度な制約を避けることで、企業による積極的な研究開発と社会実装を後押しすることを選びました。既存の法制度が一定の安全網として機能するという前提のもと、AI特有のハードローは最小限にとどめる判断をしています。
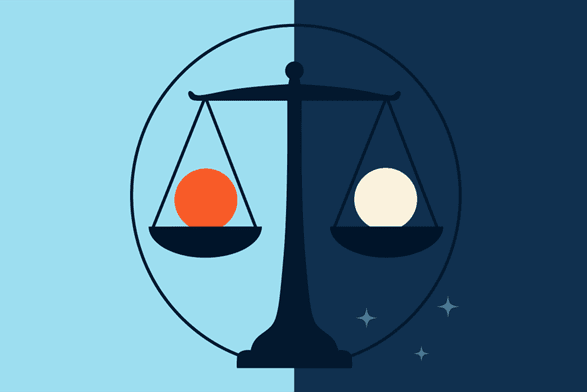
3. EU AI法: リスク分類に基づく事前規制モデル
前章で示した概念的枠組みを踏まえ、本章ではEU AI法の具体的内容を検討します。
3.1. EU AI法の成立経緯と基本構造
EU AI法は、2021年に欧州委員会から提案され、欧州議会と理事会での立法交渉を経て2024年に正式に成立しました。2025年から段階的に適用が開始されており、条項によって施行時期が異なります。
本法の中心的な組織原理は、リスクベース・アプローチです。AIシステムをその利用態様や社会的影響に応じて分類し、リスクが高いと評価されるAIほど厳格な義務を課すという構造を採っています。この枠組みは、すべてのAIに一律の規制を課すのではなく、真にリスクの高い領域に規制資源を集中させるという考え方に基づいています。
3.2. 適用範囲と域外適用
(1)地理的適用範囲
EU AI法は、EU域内に設立された事業者に限らず、以下の場合にも適用されます。
- AIシステムをEU市場に投入する場合
- AIシステムの出力がEU域内で利用される場合
この広範な域外適用により、日本企業や他の第三国企業であっても、EU市場を対象とする場合には規制対象となる可能性があります。これは、EU一般データ保護規則(GDPR)が採用したアプローチと類似しており、EUの規制が実質的にグローバルスタンダードとして機能する可能性を示唆しています。
(2) 適用除外
一方で、以下のような活動は適用除外とされています。
- 軍事、防衛、国家安全保障目的での利用
- 外国の公的機関や国際機関による法執行目的での利用(個人の権利保護の保障措置を条件とする)
- 個人的・非業務的な利用
- 研究開発段階にある場合(特定の条件下)
また、自由でオープンソースのライセンスの下で開発・公開されるAIについては、高リスクに該当しない限り、一定の配慮がなされています。
3.3. 執行体制
EU AI法の執行は、複層的な体制を採用しています。 EU レベルでは、欧州委員会内に新設されたAI Officeが中核的な調整・監督機能を担います。特に、汎用AIモデル(General-Purpose AI Models)については、AI Officeが直接的な監督権限を持ちます。
加盟国レベルでは、各国が指定する所管当局および市場監視当局が、日常的な執行を担当します。これは、製品安全規制やデジタル規制における他のEU法制と同様の枠組みであり、中央での政策調整と現場での執行能力を組み合わせる意図があります。
3.4. リスク分類の詳細
EU AI法は、AIシステムを以下の4つのカテゴリーに分類しています。
3.4.1. 禁止されるAI(許容できないリスク)
EU AI法第5条は、基本的人権に対するリスクが許容できないと判断されるAI手法について、全面的に禁止しています。これには以下が含まれます。
- 潜在意識への働きかけや脆弱性の悪用: 個人の行動を実質的に歪める形で、潜在意識に働きかける技術や、年齢・障害等による脆弱性を悪用する技術
- ソーシャルスコアリング: 社会的行動や個人的特性に基づいて個人を評価・分類し、その結果として不利益な取扱いを受けるシステム(一定の公的機関による利用)
- 予測的警察活動: プロファイリングに基づいて、誰が犯罪を犯しやすそうかを予測するシステム
- 顔画像の大規模スクレイピング: インターネット上や監視カメラ映像から顔画像を無差別に収集してデータベースを構築する行為
- 感情認識AI: 職場や教育機関における感情認識技術の利用(例外的に医療目的や安全目的で正当化される場合を除く)
これらの禁止は、違反した場合に最も重い制裁の対象となります。
3.4.2. 高リスクAI
AIシステムが以下のいずれかに該当する場合、高リスクAIとして分類されます。
(1)類型1: 製品の安全コンポーネント
既存のEU製品安全法制(Annex Iに列挙)の対象となる製品の安全コンポーネントまたは当該製品自体としてのAI。例えば、医療機器、自動車、航空機などに組み込まれたAIが該当し得ます。
(2)類型2: 特定の高影響領域での利用
Annex IIIに列挙される用途でのAI。主なものとして以下があります。
- 生体認証および分類
- 重要インフラの管理・運営
- 教育および職業訓練(入学・評価等)
- 雇用、労働者管理、自営業へのアクセス
- 必須の民間サービスおよび公的給付へのアクセス
- 法執行
- 移民・亡命・国境管理
- 司法・民主的プロセスの運営
ただし、Annex IIIに列挙されていても、個別の事案において重大なリスクを生じさせないことについて、堅固な文書化と正当化理由を提示できる場合には、例外的に高リスク分類から除外され得ます。
3.5. 高リスクAIに対する義務
高リスクAIのプロバイダー(提供者)およびデプロイヤー(利用者・導入者)には、詳細な義務が課されます。
(1)用語の定義
プロバイダー: AIシステムを開発し市場に提供する者
デプロイヤー: AIシステムを自らの権限・管理下で使用する者(導入企業等)
(2)プロバイダー(提供者)の主な義務
- リスク管理システム: AIシステムのライフサイクル全体を通じた継続的なリスク管理体制の構築・維持
- データガバナンス: 訓練・検証・テストに用いるデータセットが、関連性を有し、十分に代表性があり、バイアスの可能性について検証されていることの確保
- 技術文書の作成: 規制当局がコンプライアンスを評価できる詳細な文書の準備
- 記録保持(ロギング): 適切な場合にはログの自動記録
- 透明性と利用説明書: デプロイヤーに対し、意図された目的、限界、適切な運用方法を明示
- 人間による監視(Human Oversight): 適切に訓練された人間がAIの出力を監督し、必要に応じて介入できる設計
- 正確性、堅牢性、サイバーセキュリティ: 利用文脈に照らして適切な性能基準の達成
- 適合性評価と登録: 市場投入または運用開始前に、関連する適合性評価手続を完了し、必要に応じてシステムを登録
(3)デプロイヤーの主な義務
デプロイヤー(AIシステムを自らの権限・管理下で使用する者、すなわち導入企業等)にも以下のような義務が課されます。
- プロバイダーの利用説明書に従った使用
- 人間による監視措置の実施
- 重大なインシデントが発生した場合の報告
- 入力データの関連性確保
3.6. 制裁
EU AI法違反に対しては、以下のような行政制裁金が科され得ます。
- 禁止行為違反: 最大3,500万ユーロまたは全世界年間売上高の7%のいずれか高い方
- その他の義務違反: 最大1,500万ユーロまたは全世界年間売上高の3%のいずれか高い方
- 不正確な情報提供: 最大750万ユーロまたは全世界年間売上高の1%のいずれか高い方
これに加え、是正措置、市場からの撤回、リコールといった行政措置も可能です。

4. 日本のAIガバナンス: イノベーション重視・事後的責任モデル
本章では、日本のAI規制アプローチを詳しく検討します。
4.1. 立法意図と基本的枠組み
日本の「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(AI推進法)は、2024年に成立し、同年中に全面施行されています。この法律は、EUのような包括的な規制法ではなく、政策推進法としての性格を持っています。
法律の目的は、第1条で「人工知能関連技術の研究開発及び活用を推進し、もって経済社会の発展及び国民生活の向上に寄与すること」と明記されており、「規制」よりも「推進」に重心が置かれています。
(1)立法者の問題意識
立法過程の資料によれば、日本政府は、AI技術の開発・実装において主要国に遅れをとっているという認識を持っています。同時に、AIの社会的影響に対する国民の関心も高まっています。このような状況下で、新たな包括的規制を導入するのではなく、イノベーションを促進しつつリスクは既存法制で対応するというバランスを選択しました。
この考え方は、日本の行政法の伝統とも整合的です。日本では、規制目的を達成する手段として、法的拘束力のあるハードローだけでなく、行政指導、ガイドライン、業界団体との協議といった柔軟な手法が広く用いられてきました。レピュテーション(評判)や「お上」との関係性が重視される日本の企業文化においては、こうしたソフトな手法も一定の実効性を持ち得ます。
(2)基本理念(第3条)
AI推進法は、以下のような基本理念を掲げています。
- 人間の尊厳を重視し、人間の能力を補完・拡張するものであること
- 多様性を尊重し、公平性・透明性を確保すること
- 安全性・信頼性を確保すること
- プライバシーを保護すること
- 公正な競争を促進すること
これらは、ソフトローとしての指針であり、直接的に私人間の権利義務を創設するものではありませんが、後述する「合理的な措置」の内容を解釈する際の基準となります。
(3)事業者の責務(第7条)
AI関連事業者(活用事業者)には、第7条により以下の2つの責務が課されています。
①AI活用の努力義務: 自ら積極的なAI関連技術の活用により事業活動の効率化および高度化ならびに新産業の創出に「努める」こと
②施策への協力義務: 国・地方公共団体が実施する施策に「協力しなければならない」こと
①は努力義務にとどまりますが、②は「協力しなければならない」という義務であり、協力しない場合は後述する第16条に基づく指導・助言その他の必要な措置の対象となり得ます。ただし、EUのような明確な罰則規定や詳細な義務内容が定められているわけではありません。
4.2. 適用範囲
AI推進法にはEU AI法のような明示的な域外適用条項は設けられていません。しかし、政府の政策文書および大臣答弁により、日本市場で事業活動を行う国外企業(日本語でのサービス提供や日本のユーザーを対象とする場合等)は、適用対象から一律に除外されるものではないことが明らかにされています。
同法の規定は努力義務として定められていますが、日本国内で活動する企業(国内・国外を問わず)は、個人情報保護法、労働法、消費者保護法、業法等の既存法制の全面的な適用を受けます。
4.3. 調査研究等と指導・助言の権限
AI推進法第16条は、国に対して以下の権限を付与しています。
- 国内外のAI関連技術の研究開発・活用動向に関する情報収集
- 不正な目的・不適切な方法による権利侵害事案の分析・対策の検討
- その他のAI関連技術の研究開発・活用の推進に資する調査研究
- これらの結果に基づく、活用事業者等に対する指導、助言、情報提供その他の必要な措置
第16条後段(上記4)は、「講ずることができる」ではなく「講ずるものとする」という規定となっており、国による指導・助言が積極的に実施される可能性を示唆しています。ただし、具体的な措置の内容や判断基準については、今後の運用において明らかになると考えられます。
4.4. 既存法制との関係: 実質的なリスク管理の場
日本のAIガバナンスにおいて最も重要なのは、既存法制がAIに関する実質的な法的リスクの源泉となるという点です。AI推進法は理念と方向性を示すにとどまり、具体的な法的責任は、以下のような既存法によって判断されます。
4.4.1. 個人情報保護法(APPI)
AIシステムの開発・運用において個人情報を取り扱う場合、個人情報保護法の全面的な適用を受けます。
(1)訓練データの収集
機械学習モデルの訓練に個人情報を用いる場合、以下が問題となります。
- 取得時の利用目的の特定・通知(第21条)
- 本人同意の要否(第18条、第27条)
- 要配慮個人情報(人種、病歴等)の取得制限(第20条)
- 安全管理措置(第23条)
判例・実務上、AI訓練目的が「当初の取得目的」に含まれていない場合、新たな目的での利用として本人同意が必要となる場合があります。
(2)プロファイリングと本人関与
AIによるプロファイリング(個人の行動・関心等を分析・予測すること)は、個人情報保護法上、「保有個人データ」の利用として位置付けられます。本人は、開示請求権(第33条)や利用停止請求権(第35条)を有するため、AIによる判断のロジックや根拠についての説明が求められる場合があります。
(3)海外事業者への委託・移転
AIモデルの訓練や推論を海外のクラウドサービスで行う場合、外国にある第三者への提供(第28条)の問題が生じます。本人同意または適切な体制整備が求められます。
4.4.2. 労働法制
AI採用ツールや人事評価AIは、以下の法的リスクを伴います。
- 募集・採用段階での情報収集制限: 職業安定法により、業務遂行に必要な範囲を超えた個人情報の収集は制限されます
- 差別的取扱いの禁止: 労働基準法第3条(国籍・信条・社会的身分による差別禁止)、男女雇用機会均等法による性別差別禁止などが適用されます。AIの判断結果が間接的に差別的効果を持つ場合も問題となり得ます
- 解雇・配置転換における合理性: AIが示唆する判断を機械的に適用して解雇や配置転換を行う場合、裁判所は「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」(労働契約法第16条)の有無を厳格に審査します
4.4.3. 消費者保護法制
消費者向けにAIサービスを提供する場合、以下が適用され得ます。
- 不当表示規制(景品表示法): AIの性能や精度について、実際よりも著しく優良であると誤認させる表示は規制対象
- 不当な勧誘(消費者契約法): AIによる自動勧誘が、不実告知や重要事項の不告知に該当する場合、契約取消事由となり得る
- 製造物責任法: AIを組み込んだ製品に「欠陥」がある場合、製造業者は損害賠償責任を負う
4.4.4. その他の法制
- 知的財産法: AIによる生成物の著作権、他者の著作物を訓練データとして利用することの適法性(著作権法第30条の4など)
- 競争法: AIによる価格カルテルや取引条件の不当な差別
- 金融規制: 信用スコアリングや投資助言におけるAI利用に対する業法上の規制
5. EUと日本の規制の違いは実務にどう影響するか
ここまでで両規制の内容を確認しました。本章では、その違いが企業実務に与える具体的な影響を整理します。
5.1. 規制の主要な相違点: 一覧比較
以下の表は、EUと日本のAI規制アプローチを実務的な観点から対比したものです。
| 項目 | EU(EU AI法・ハードロー) | 日本(AI推進法+既存法・ソフトロー+α) |
| 規制の基本的性格 | 拘束力のあるAI専用規制により、法的に強制可能な義務を設定 | 政策主導のガバナンス。既存の分野別法制と組み合わせて対応 |
| 規制の重点 | 基本的人権の保護を、リスク管理と事前統制によって実現 | イノベーション促進。リスクは事後的責任によって対応 |
| リスク分類 | 明示的なリスクベース分類(許容不可・高リスク・限定的リスク・最小リスク) | AI特有のリスク分類体系なし。リスクは既存法の枠内で個別評価 |
| 主要な義務 | 市場投入前の適合性評価、技術文書、リスク管理、人間による監視 | ガバナンス体制、合理的措置の努力、個人情報保護法・労働法・消費者保護法の遵守 |
| 執行モデル | EUレベルでの調整の下、各国の監督当局が行政執行 | 行政指導、公表、既存法による執行 |
| 罰則・制裁 | 重大な行政制裁金、是正措置、市場からの撤回 | AI法自体の罰則なし。既存法令違反に基づく制裁 |
| 域外適用 | あり。AIシステムがEU市場または域内個人に影響する場合に適用 | 原(則として国内中心。ただし既存法(個人情報保護法等)の域外適用はあり |
| 企業への実務的影響 | 高い初期コンプライアンスコストと長い上市期間。ただし法的確実性は高い | 初期の規制負担は低いが、内部ガバナンスと行政対応力が重要 |
5.2. 実務への影響: コンプライアンス、時間、予見可能性、執行リスク
前章までで説明した制度的相違は、企業実務において以下の形で具体化します。
(1) コンプライアンス体制とコスト
EUでは高リスクAIについて、市場投入前にリスク管理システム、データガバナンス、技術文書、適合性評価等の完了が必須です。これには専門人材や外部アドバイザーの関与が必要となり、相当な初期投資を要します。
日本ではAI特有の事前承認制度がないため初期コストは抑えられますが、問題発生時に合理的な判断プロセスを説明できる記録整備と、既存法制(個人情報保護法、労働法等)への対応が求められます。
(2)市場投入までの期間
EU高リスクAIの適合性評価と社内準備には数ヶ月を要する場合があり、競争の激しい市場では重大な考慮要素となります。日本では技術的準備が整い次第のサービス開始が可能ですが、事後的リスクは企業が自ら管理する必要があります。
(3)法的予見可能性
EUは禁止行為、リスク区分、義務内容が明文化され全加盟国に統一適用されるため、予見可能性が高く長期投資判断がしやすくなります。日本は既存法制の解釈・適用による事後判断が中心で、新規利用態様については不確実性が残る場合があります。
(4)執行リスク
EU違反には最大3,500万ユーロまたは全世界売上高7%の制裁金に加え、製品撤回や是正命令のリスクがあります。日本のAI推進法自体に制裁はありませんが、既存法令違反による行政処分や、行政指導・公表によるレピュテーション毀損リスクには注意が必要です。
5.3. クロスボーダー事業展開への示唆
(1) EU基準をベースラインとする戦略
両市場で事業を行う企業にとって、EU AI法の高リスク要件を満たす体制構築が、堅牢なガバナンスのベースラインとなります。ただし、日本固有の法的論点(個人情報保護法の詳細要件、労働法上の慣行、消費者保護法制)は別途検討が必要です。
(2)日本を起点とする場合の課題
日本市場を主眼に開発されたAIシステムをEU市場に展開する際は、技術文書の遡及的作成、リスク管理プロセスの形式化、適合性評価手続への対応といった追加作業が発生します。早期段階からEU要件を意識することで手戻りを最小化できます。
6. ケーススタディ: 採用AIをEUと日本で使う場合
本章では、具体的な利用場面を通じて、両規制の違いが実務にどのように現れるかを検討します。
6.1. 想定事例
ある企業が、AIを用いた採用スクリーニングシステムを開発しました。このシステムは、応募者の履歴書、オンライン適性検査の結果、ビデオ面接での応答を分析し、採用候補者を推奨します。この企業は、同じシステムをEUと日本の両方で使用することを検討しています。
この事例が重要なのは、以下の理由からです。
- 雇用という高い影響力を持つ領域での利用である
- 差別リスクが内在する
- 大量の個人情報を処理する
- 多国籍企業が一貫して展開したいと考える典型的な用途である
6.2. EUにおける取扱い: 高リスクAIとしての厳格な義務
(1)リスク分類
EU AI法の下、雇用、採用、選考に関する意思決定に用いられるAIは、Annex IIIに明示的に列挙されており、原則として高リスクAIに該当します。
これは、個人の雇用機会へのアクセスに実質的な影響を与え得るためです。
(2)課される義務(詳細)
高リスクAIとして分類される場合、プロバイダー(AIシステム開発・提供者)およびデプロイヤー(利用者、この場合は採用を行う企業)には、以下のような詳細な義務が課されます。
(3)プロバイダー(AIシステム開発・提供者)の義務
①リスク管理: システムのライフサイクル全体を通じた継続的なリスク管理体制の構築・維持。特に、バイアスや差別的効果のリスクを特定・評価・軽減する措置
②データガバナンス:
・訓練データセットが、対象となる人口集団を適切に代表していることの確認
・既知のバイアス(性別、人種、年齢等)の検証と是正
・データ品質の継続的な監視
③技術文書と記録保持:
・システムの設計、開発、テストに関する詳細な文書の作成
・規制当局がコンプライアンスを評価できる情報の整備
・必要に応じたログの自動記録
④透明性と利用説明書:
・デプロイヤー(この場合、採用を行う企業)に対する、システムの意図された目的、限界、適切な使用方法の明示
・システムがどのような要素を重視し、どのような判断をするかの説明
⑤人間による監視:
・適切に訓練された人間がAIの出力を監督し、必要に応じて介入できる設計
・採用の最終判断を人間が行うことを担保する仕組み
⑥正確性、堅牢性、サイバーセキュリティ:
・採用文脈において適切な性能基準の達成
・不正アクセスや操作への耐性
⑦適合性評価と登録:
・市場投入前に、関連する適合性評価手続(多くの場合、内部管理に基づく評価)を完了
・EU データベースへの登録
(4)デプロイヤー(採用企業)の義務
デプロイヤー(この場合、採用AIを実際に使用する企業)には以下の義務が課されます。
- プロバイダーの利用説明書に従った使用
- 人間による監視措置の実施(例: AIの推奨を参考情報とし、最終判断は人間が行う)
- 重大なインシデント(例: 明らかな差別的結果)が発生した場合の監督当局への報告
- 入力データの品質確保
(5)違反の場合の帰結
これらの義務に違反した場合、以下のリスクがあります。
- 行政制裁金(最大1,500万ユーロまたは全世界売上高の3%)
- システムの市場撤回や使用停止の命令
- 是正措置の要求
- レピュテーション毀損
6.3. 日本における取扱い: AI特有の事前規制なし、ただし既存法の適用
(1)AI推進法上の位置づけ
日本では、同じ採用スクリーニングシステムは、AI特有の適合性評価や事前承認の対象とはなりません。AI推進法は、「合理的に実行可能な範囲での必要な措置」を努力義務として求めるのみです。
しかし、これは法的リスクがないことを意味しません。実際の法的リスクは、以下の既存法制から生じます。
(2)関連する法的論点
①雇用・採用規制
- 職業安定法: 募集に際して収集できる個人情報の範囲は、業務遂行に必要な範囲に限定されます。AIが過度に広範な情報(例: SNSの投稿内容、趣味嗜好)を分析する場合、問題となり得ます
- 労働基準法第3条: 国籍、信条、社会的身分による差別的取扱いの禁止。AIの判断が結果的に特定の属性を持つ者を不利に扱う場合、間接差別として問題視される可能性
- 男女雇用機会均等法: 性別による差別的取扱いの禁止。AIのアルゴリズムが、訓練データのバイアスにより女性応募者を不利に評価する場合、法令違反のリスク
- 実務上の採用慣行: 日本では、採用プロセスにおける説明責任が重視されます。AIによる不採用判断について、応募者から説明を求められた場合に対応できる体制が求められます
②個人情報保護法(APPI)
- 取得時の利用目的の特定・通知(第21条): 応募者の個人情報をAI分析に用いることを、明確に利用目的として示す必要があります
- 本人同意の要否: 応募者から直接取得する場合は通知で足りますが、第三者(例: SNS、リファレンスチェック業者)から取得する場合は原則として本人同意が必要(第27条)
- 要配慮個人情報の取扱い(第20条): 人種、病歴、犯罪歴等の要配慮個人情報は、原則として本人同意なしに取得できません。AIがこうした情報を推測・利用する場合、慎重な検討が必要
- 安全管理措置(第23条): 応募者データの漏洩・不正アクセスを防ぐための技術的・組織的措置
- 開示請求・利用停止請求への対応(第33条、第35条): 応募者から、AIによる判断の根拠や利用停止を求められた場合の対応体制
(3)消費者保護・不当表示のリスク(該当する場合)
採用AIシステムを外販する場合、その性能や精度について、実際よりも著しく優良であると誤認させる表示を行うと、景品表示法違反となり得ます。
①AI推進法に基づくガバナンス期待
法的強制力はないものの、AI推進法とそれに関連するガイドラインは、以下のような期待を示しています。
- 透明性: AIの判断プロセスについて説明可能であること
- 公平性: バイアスの検証と是正の取組
- 人間中心: 最終判断を人間が行うこと
②実務上の対応
日本で採用AIを用いる企業は、形式的な事前承認は不要ですが、以下の対応が推奨されます。
- データセット選定の記録: どのようなデータを訓練に用いたか、バイアステストをどのように実施したかの文書化
- 判断プロセスの可視化: AIがどのような要素を重視して判断しているかを、人事・法務部門が理解し説明できる状態にする
- エスカレーション手続: AIの推奨に疑問がある場合や、応募者から問い合わせがあった場合の対応プロセスの整備
- 定期的なレビュー: AIの判断結果を定期的に分析し、意図しない差別的効果が生じていないかをモニタリング
6.4. 実務上の核心的相違: 事前適合 vs 事後説明
このケーススタディが示す最も重要な違いは、タイミングと責任の所在です。
(1)EUのアプローチ
EUでは、企業は市場投入前またはシステム運用開始前に、高リスク要件を満たしていることを実証しなければなりません。構造化された文書と適合性評価が中心的な役割を果たします。
この枠組みは、初期コストは高いものの、規制当局との関係において防御的な立場を確保できます。
(2)日本のアプローチ
日本では、システムの運用開始に際してAI特有の障壁はありませんが、問題が生じた際に、既存法に照らして合理的であったことを事後的に説明する責任が企業にあります。
この枠組みは、柔軟性と速度を提供しますが、事後的なリスクを自ら管理する能力が企業に求められます。
(3)両市場で同一ツールを展開する戦略
両市場で同じ採用AIツールを展開する企業にとって、効果的な戦略は以下の通りです。
- 設計段階からEU高リスク要件を意識: リスク管理、データガバナンス、透明性をシステム設計に組み込む
- 日本固有の論点を別途確認: 個人情報保護法の利用目的特定、労働法上の慣行、人事部門との協議
- 文書化を共通基盤とする: EUで求められる技術文書は、日本でも事後的説明の基礎として有用
7. 企業が取るべき実務対応
本章では、EUと日本の両市場でAIを活用する企業が、実務上どのような対応を取るべきかを整理します。
7.1. EU基準を軸としつつ、日本の個別論点を見落とさない
EU AI法の高リスク要件は詳細かつ包括的であり、これを満たす体制を構築することで強固なガバナンス基盤が得られます。リスク管理プロセス、データガバナンス、技術文書、人間による監視メカニズムは、日本を含む他市場でも有益です。
ただし、EU適合だけでは不十分です。個人情報保護法の詳細要件(利用目的の特定、第三者提供、開示請求対応等)、労働法制における慣行、業界自主規制、消費者保護法制における表示規制といった日本固有の論点は別途検討が必要です。
7.2. 早期段階でのAI利用場面の洗い出しとリスク評価
企業は、AIの出力が個人・顧客・取引先にどのような影響を与えるか、雇用・信用・価格設定・適格性判断など高影響領域での利用か、大量の個人情報を処理するか、自動化の程度(人間の関与の余地)といった観点から、AI利用場面を早期に特定しリスク評価を行うべきです。
早期評価により、EU高リスク分類該当の可能性予測、日本で適用される既存法制の特定、設計段階からのコンプライアンス組込みによる手戻り最小化が可能になります。
7.3. 説明可能性と文書化への投資
EUでは高リスクAIについて技術文書と透明性が明示的な義務です。日本でも、行政指導、監査、苦情対応、訴訟リスクに備えて説明可能性は実務上不可欠です。
AIシステムの設計意図と限界、訓練データの出所と品質、バイアステストの実施方法と結果、人間による監視・介入の仕組み、インシデント対応手順といった事項を文書化すべきです。文書化は単なる規制対応ではなく、内部意思決定の質向上、インシデント時の迅速対応、関係者とのコミュニケーション基盤として機能します。
7.4. 執行環境の違いへの備え
EUでは明示的なルールベースの執行と重大な制裁が想定されるため、法令遵守を実証できる証拠の整備、監督当局の照会・調査への対応体制、違反リスクの早期発見と是正のための内部監査を準備すべきです。
日本では関係性重視・裁量的執行が中心であり、規制当局との良好な関係構築、業界動向への注視、公表や行政指導のリスク評価、レピュテーション管理に注意が必要です。AI特有の制裁はなくとも、既存法令違反や公表措置による影響は軽視できません。
7.5. 法務アドバイザーの戦略的活用
AI規制対応では、企画段階での利用場面のリスク評価と規制適用可能性判断、設計段階でのガバナンスメカニズム組込みとデータ取得方法の適法性確認、開発段階での文書化の並行実施、市場投入前のEU適合性評価と日本既存法制への最終確認が重要です。
EU向けには早期からの体系的関与により後の設計変更・文書追加コストを削減でき、日本向けには定期的レビューとガイドライン・執行動向のモニタリングが効果的です。
8. おわりに: クロスボーダーAI戦略の構築に向けて
EUと日本は、AIの台頭に対して、その制度設計において対照的なアプローチを選択しました。EU AI法は、包括的で拘束力のあるリスクベースの枠組みを通じて、事前統制と市場全体での統一性を優先しています。日本のAI推進法は、政策主導のアプローチを採り、既存法制と行政実務を通じてリスクに対応しつつ、イノベーションを促進することを選びました。
クロスボーダーでAIビジネスを展開する企業にとって、いずれのモデルも無視することはできません。両規制がどのように機能し、既存法制とどのように相互作用するかを理解することは、責任あるAI活用と競争力維持の両立に不可欠です。
AI技術と規制環境が進化を続ける中、先を見越した戦略的な法務対応が、持続可能なAI事業の中核的要素であり続けるでしょう。
参考資料
本稿の執筆に際しては、以下の資料を参照しました。
EU AI Act関連
EU Artificial Intelligence Act 公式サイト:
https://artificialintelligenceact.eu/implementation-timeline/
日本のAI規制関連
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(法令データ):
https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053
同法律の概要(日本法令外国語訳):
https://www.japaneselawtranslation.go.jp/outline/168/905R744.pdf
AI関連技術の研究開発・活用の推進に関する法律が全面施行, 政府広報オンライン(2025年11月):
https://www.gov-online.go.jp/hlj/ja/november_2025/november_2025-08.html
国際的な比較分析
Understanding Japan’s AI Promotion Act: An “Innovation-First” Blueprint for AI Regulation, Future of Privacy Forum:
https://fpf.org/blog/understanding-japans-ai-promotion-act-an-innovation-first-blueprint-for-ai-regulation/
How Japan is regulating AI: Inside the AI Promotion Act, Nemko Digital:
https://digital.nemko.com/regulations/ai-regulation-japan
本稿は、2026年1月時点での情報に基づいており、今後の法改正や執行実務の変化により内容が変わる可能性があります。個別の案件については、専門家にご相談ください。
1. 報告書案の取りまとめと見通し
金融庁の金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」では、2025年6月25日の設置以降、暗号資産の規制見直しについて検討が行われてきました。そして、11月26日に開催された第6回の会議において、それまでの審議の結果をまとめた報告書案1が概ね了承されました。
今後は、審議会の最終的な報告内容を踏まえ、関係法令の改正案が2026年の通常国会に提出され、早ければ2027年春には新規制が導入されることが見込まれます。
同報告書案における最大のポイントは、暗号資産関連の規制を資金決済法から金商法へと移行させることです。これは、2016年以降「決済手段」として概ね資金決済法の下で規制されてきた暗号資産を、「金融商品」として位置づける抜本的な見直しを内容とするものであり、暗号資産業界にとって極めて重要な制度変更となります。
本稿では、報告書案の全体像を整理した上で、その内容が導入された場合に、既存の暗号資産関連事業者にとってどのような影響が想定されるのかを整理します。
| 12月16日追記:本稿執筆後の2025年12月10日、本WGの最終報告書が公表されました(https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20251210.html)。 最終報告書について、本稿がベースにしていた報告書案から概ね変更がない(脚注35番が追加されています)ことから、以下「報告書案」としていたものを「報告書」に読み替える修正を行いました。 |
2. 報告書の概要
2.1 規制見直しの必要性と基本方針
報告書では、まず、暗号資産の投資対象化に伴う課題2を提示したうえで、規制見直しの必要性を述べています。そして、これらの課題への対処において金商法と親和性があることや、投資目的での取引の実態等を考慮して、政策的に金商法の規制を及ぼす必要性・相当性があるとし、以下のとおり提案しています。
- 暗号資産に金商法の規制を及ぼす
- 有価証券とは別の規制カテゴリーとする
- 規制対象は現行法上の暗号資産とする
- ステーブルコインは対象外、NFTについても一律な金融規制対象とすることに慎重
- 現行の資金決済法の暗号資産規制は削除する
2.2 情報提供規制
金商法移行に伴う大きな変更点として、報告書は、暗号資産取引における利用者への情報提供の必要性から、新規販売時の情報提供義務と継続的な情報提供義務を設けることを提案しています。
2.2.1 新規販売時の情報提供
情報提供の内容
報告書は、情報の非対称性を解消する観点から、暗号資産の性質・機能や供給量、基盤技術、付随する権利義務、内在するリスク等の情報が提供されるべきとしています。また、中央集権型暗号資産(※)については、上記の情報に加えて、中央集権的管理者3に関する情報の提供も必要としています。
内在するリスクとしては、詐欺や価格変動といった交換業者による説明で対処すべきもののほか、個別の暗号資産のリスクに係るものとして、流動性リスクや希薄化リスク、事業リスクや技術・運営上のリスク等について情報提供が必要であるとしています。また、暗号資産の商品性についても情報の提供がなされるべきとしています。
- 時価総額、流通状況(流動性リスク)
- 発行済数量、発行可能数及びその変更可否、過去の発行・償却状況、今後の発行・償却予定、中央集権的管理者及びその関係者の保有状況(希薄化リスク)
- 中央集権的管理者に関する情報、調達資金の使途、利用状況、対象事業の事業計画、対象事業の進捗の状況(事業リスク)
- 価値移転認証の仕組み、コード監査・セキュリティ監査に関する情報(技術・運営上のリスク)
- 暗号資産の開発経緯や技術、トークノミクス、ユーティリティに関する情報(商品性)
(※)中央集権型暗号資産の判断基準
中央集権型暗号資産については、流通面(発行・移転権限)と内容面(仕様の設計・変更権限)の支配に着目してその範囲を定めるべきとして、該当する類型の例として以下が挙げられています。その該当性は交換業者において審査し、自主規制機関においてチェックすることが想定されています。
- 特定の者のみが発行権限を有する暗号資産(発行・生成の管理主体が存在)
- パーミッション型ブロックチェーンによる暗号資産(移転の管理主体が存在)
- ERC-20等の基盤となるトークン規格に基づき発行される暗号資産(仕様を定める主体が存在)
情報提供義務の主体
情報提供義務の主体については、暗号資産を取り扱う交換業者が基本的役割を担い、必要な情報を収集して利用者に提供する体制を確保すべきとしています。一方、中央集権型暗号資産について、その中央集権的管理者が一般の利用者から資金調達を行う場合には、その中央集権的管理者に情報提供義務を課すべきとしています4。
なお、海外発行の暗号資産を国内交換業者が取り扱う場合には、中央集権的管理者の存否を問わず、交換業者が情報提供を行うことが考えられるとしています。
新規販売時の情報提供まとめ
| 類型 | 発行者の資金調達 | 情報提供義務主体 | 主な提供情報 | 備考 |
| 中央集権型 | あり | 発行体・交換業者 | ・性質・機能、供給量、基盤技術 ・リスク(流動性、希薄化、事業、技術・運営) ・発行者情報、資金使途、事業計画 ・保有状況、商品性 等 |
いずれが主体的かは不明確 |
| なし | 交換業者 | ・性質・機能、供給量、基盤技術 ・リスク ・発行者情報 等 |
― | |
| 非中央集権型 | ― | 交換業者 | ・性質・機能、供給量、基盤技術 ・リスク、商品性 等 |
― |
| 海外発行 | ― | 交換業者 | ・上記に準じる | 正確性・客観性を担保する措置を検討 |
| 私募・私売出し | あり | 免除 | ― | 転売制限が必要 |
2.2.2 継続的情報提供
報告書は、暗号資産の性質上、仕様変更や事業進捗など投資判断に影響を与える事象が生じやすいことから、発行者または交換業者に対し、重要な事象が発生した場合の適時の情報開示を義務付けるとしています。また、適時の情報開示を補完するため、発行者には発行者の事業活動等について年1回の定期的な情報提供を求めることが適当としています。
2.2.3 情報提供の内容の正確性・客観性の確保
報告書は、情報の正確性・客観性確保のため、発行者による虚偽記載等については、有価証券届出書等の虚偽記載や不提出と同様の罰則や民事責任を設けるとともに、交換業者が発行者作成情報の虚偽を知りながら取り扱った場合の罰則や、交換業者自身が作成する情報の虚偽記載等に対する(発行者による場合よりも軽減された)責任も規律することとしています。
また、課徴金制度の創設を検討し、虚偽記載等があった場合には国内すべての交換業者での取扱い停止措置を設けるべきとしています。加えて、交換業者の審査義務・体制整備の法定化、第三者コード監査の義務化、自主規制機関の独立した審査体制整備など、チェック機能の強化も求めています。
2.3 業規制
金商法の枠組みへの移行に伴い、報告書は、暗号資産の売買等を業として行う事業者について、第一種金融商品取引業に相当する規律を中心に、業務運営・利用者財産管理・セキュリティ対策等の強化を求める方向性を示しています。
2.3.1 兼業規制
報告書は、交換業者に対して、金商法の兼業規制と同様に、利益相反防止や利用者保護の観点から他業を行う場合の事前チェックを求めています。ただし、ブロックチェーン等に係るコンサルティング業務等、暗号資産交換業に付随する業務については届出・承認を不要とするほか、それ以外の業務についても事前届出で足りるとすることが考えられるとしています5。また、既存の金商業者が暗号資産交換業を追加する場合には変更登録が必要とされています。
2.3.2 業務管理体制の整備
報告書は、利用者保護の観点から、交換業者に対してより一層の管理体制の構築を求めています。特に以下の体制整備が必要とされています。
- 取扱暗号資産の審査体制
- 取扱暗号資産に関する情報提供体制
- 顧客のリスク負担能力に応じた取引適合性の確認体制
- 売買審査体制
- 発行者による情報提供規制違反時の取扱停止を可能とする体制
また、「販売所」と「取引所」の2種類の形態によってサービスを提供している交換業者について、より収益性の高い「販売所」への誘導が行われていないか懸念を示しています。この点、金商法における最良執行義務(最良の取引の条件で顧客の注文を執行するための方針及び方法を定めて実施するもの)の趣旨を踏まえ、顧客にとって適切なサービス提供を求めるべきとしています。
2.3.3 募集・売出し時の利用者保護
報告書は、IEO等の暗号資産の募集・売出しについて、発行者の資金調達後に利用者の期待に応える経済的インセンティブが弱いという指摘を踏まえて、以下の利用者保護措置を提案しています。
- 監査法人による財務監査が行われていない場合の投資上限の設定
- 交換業者と発行者との間に利害関係がある場合の説明義務(利益相反防止)
- 上場審査中及び上場後の特定の者に対する有利発行の原則禁止
- 発行者及びその関係者に対するロックアップ期間の設定
2.3.4 利用者財産の管理
利用者財産の管理について、報告書は、現行の分別管理義務を維持することを基本としています。他方で、最近の不正流出事案において手口が巧妙化している点を踏まえ、ガイドライン等で柔軟に対応することも前提にしつつ、新たな安全管理措置を法令上義務付ける必要があるとしています。
また、交換業者が暗号資産管理の重要なシステムの提供を外部事業者から受ける場合には、当該事業者に対して事前届出制・監督権限・行為規制を導入し、交換業者が届出済み事業者からのみ提供を受けられる仕組みを設けることが適当としています6。
2.3.5 責任準備金
報告書は、コールドウォレット等で管理される暗号資産についてもハッキングによる流出リスクが存在することから、顧客に対して必要な補償を適切に行う備えが必要であるとしています。このため、交換業者に過度な負担とならないよう配慮しつつ、過去の流出事案の発生状況やセキュリティ水準を踏まえた適切な水準の責任準備金の積立てを求めるべきとしています7。
また、補償原資確保の選択肢を広げる観点から、責任準備金の代わりとして、又は責任準備金と併せて、保険加入等を認めることも検討すべきと整理されています。
2.3.6 仲介業規制
2025年の改正資金決済法で創設された電子決済手段・暗号資産サービス仲介業について、報告書は、金商法上の金融商品仲介業と基本的な建付けが共通していることから、暗号資産取引に係る仲介業については金融商品仲介業に統合すべきとしています。その際、外務員制度など既存の金融商品仲介業規制の適用が原則となるべきとしています。
2.3.7 暗号資産の借入れ
報告書は、ステーキングや再貸付けのために利用者から暗号資産を借り入れる(レンディング)ビジネスについて、利用者がリスクをとってリターンを追求する行為であるため、利用者保護の観点から、金商法に基づく業規制の対象とし、以下のような体制整備義務や行為規制を課すべき8としています。
- 再貸付先の信用リスク・スラッシングリスクを管理する体制
- 借入暗号資産の安全管理体制
- 利用者へのリスク説明・広告規制
2.3.8 市場開設規制
報告書は、暗号資産現物の板取引を行う取引所を運営している交換業者について、暗号資産の性質上、個々の取引所の価格形成機能が限定的であることから、金融商品取引所に係る免許制に基づく規制や、金商業者に係る認可PTSの規制のような厳格な市場開設規制を課す必要性は低いとしています9。
2.3.9 発行者に対する業規制
報告書は、発行者自身による暗号資産の販売について、私募・私売出しに相当する場合を除いて引き続き交換業の登録を必要とし、交換業者にその取扱いを委託する場合には、発行者による交換業の登録は不要とすることが適当であるとしています。
2.4 不公正取引規制
2.4.1 インサイダー取引規制
報告書は、近年における、証券監督者国際機構(IOSCO)の勧告や、欧州・韓国での法制化、米国での法執行事案などを踏まえ、課徴金制度を伴う暗号資産のインサイダー取引規制を整備すべきとしています。
具体的には、「国内の交換業者の提供する取引の場の公正性・健全性に対する利用者の信頼を確保すること」を保護法益に据え、(i)「対象暗号資産」について、(ii)「重要事実」に接近できる(iii)特別の立場にある者(インサイダー)が、当該事実の(iv)「公表」前に、(v)取引の場に対する利用者の信頼を損なうような売買等を行うことを禁止する必要があるとしています。
対象暗号資産
規制対象となる暗号資産は、国内の交換業者において取り扱われる暗号資産であり、これには交換業者に対し正式な取扱申請があった暗号資産も含まれるとしています。
重要事実
重要事実は、以下の3つの類型について個別列挙しつつバスケット条項で補完することが適当であるとしています。
- 中央集権型暗号資産の発行者の業務等に関する重要事実(例:発行者の破産、重大なセキュリティリスクの発覚など)
- 交換業者における暗号資産の取扱い等に関する重要事実(例:暗号資産の新規上場・上場廃止、流出など)
- 大口取引に関する重要事実(例:発行済暗号資産の20%以上の売買等)
規制対象者
規制対象については、重要事実に接近できる特別な立場にある者が、その立場にあることに起因して内部情報を知った場合を対象とすることが適当であるとしています。具体的には、重要事実の類型に応じて、中央集権型暗号資産の発行者の関係者、交換業者の関係者、大口取引を行う者の関係者、およびこれらの者からの第一次情報受領者が対象となることが想定されています。
2.4.2 その他の不公正取引規制
インサイダー取引規制以外についても、有価証券に係る不公正取引規制のうち、以下のような暗号資産にも妥当すると考えられるものについては併せて整備すべきであるとされています。
・安定操作取引の禁止10
・対価を受けてインターネットサイト等で取引判断に関する意見表示をする場合における対価を受ける旨の表示義務11
2.5 その他の重要論点
2.5.1 銀行・保険会社における取扱い
銀行・保険会社本体による暗号資産の発行・売買等、それらの仲介については、引き続き慎重な検討が必要とされています12。他方で、銀行・保険会社に分散投資の手段を提供する観点等から、十分なリスク管理・態勢整備等が行われていることを前提に、銀行・保険会社本体に投資目的での暗号資産の保有を認めることが考えられるとされています。
2.5.2 無登録業者への対応
無登録業者に対しては、刑事罰が強化され(5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はこれらの併科)、金商業の無登録業者への対応として設けられている緊急差止命令などのエンフォースメントを整備するべきとされています。また、暗号資産の投資運用や投資アドバイスについても投資運用業及び投資助言業の対象とすべきとされています。
2.5.3 DEX等への対応
DEXについては、開発後は人為的要素が少ないことや欧米において一定のDEXについて規制の対象外との整理がなされていること等を踏まえて、現時点で規制案として踏み込んだ提案はなされていませんが、技術的性質に合わせた過不足のない規制のあり方について、今後継続して検討を行うこととされています。
また、DEXに接続するアプリ等のUIを国内居住者向けに提供する者に対しては、接続先に係るリスクについての説明義務や犯収法上の本人確認義務を含むAML/CFT対策等といった、リスクに応じた過不足のない規制を課すことを念頭に、各国の規制動向やサービスの実態把握を深めていく必要があるとされています。
3. 想定される実務への影響
以下は、報告書の内容から想定し得る範囲で、それが実現した場合の実務への影響を業種/業態ごとにまとめたものです。
| No. | 業種/業態 | 影響度 | 主な影響項目 | 備考 |
| 1 | 暗号資産交換業者 | ◎ | ・金商法下のライセンスの取得 ・情報提供規制(新規販売時/継続) ・中央集権型暗号資産の該当性審査 ・兼業規制 ・業務管理体制整備 ・安全管理措置整備 ・適合性原則・最良執行義務 ・責任準備金の積立て ・不公正取引規制 |
・暗号資産取引所(板取引)は市場開設規制の対象外 ・交換業に付随する業務は届出承認不要、それ以外の業務は事前届出 ・ウォレットなどの提供等を受ける先は届出事業者に限定 ・報告書外の論点であるが、税制改正、レバレッジ規制の緩和の可能性 |
| 2 | 金融商品取引業者 | △? | ・暗号資産デリバティブ取引のみを行っている事業者について、兼業規制の緩和(事前届出)を認める可能性 | ・暗号資産デリバティブの板取引は市場開設規制の対象外 ・報告書外の論点であるが、暗号資産ETF解禁の可能性 |
| 3 | 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者 | 〇 | ・金融商品仲介業に移行 ・外務員制度等の規制適用 |
― |
| 4 | 電子決済手段発行者 / 電子決済手段等取引業者 | × | ― | ・電子決済手段は対象外 |
| 5 | 暗号資産発行者(中央集権型) | 〇 | ・情報提供規制(新規販売時/継続) ・上場審査中・上場後の有利発行禁止 ・上場前後のロックアップ期間設定 ・不公正取引規制 |
・セカンダリー取引による資金調達についても情報提供規制の対象 |
| 6 | システム提供事業者(ウォレット等) | ◎ | ・事前届出規制対象に ・欠格事由・行為規制・監督権限の設定 |
・規制の適切な水準に留意 ・必要な経過措置も検討 |
| 7 | レンディング(借入れ)事業者 | ◎ | ・金商法の規制対象に ・リスク管理体制の整備義務 ・暗号資産の安全管理体制整備義務 ・利用者へのリスク説明義務や広告規制 |
・規制の適切な水準に留意 ・必要な経過措置も検討 ・機関投資家や個人が交換業者から借り入れるのは規制対象外 |
| 8 | ステーキングサービス提供者 | × | ― | ・報告書で言及なし ・暗号資産の借入れや管理に該当する場合は影響あり |
| 9 | 投資運用・投資助言業者 | ◎ | ・暗号資産の投資運用や投資アドバイスについて、投資運用業及び投資助言業の対象 ・暗号資産の投資運用業者にサイバーセキュリティ態勢整備を求める可能性 |
― |
| 10 | 金融商品取引所 | × | ・暗号資産現物上場は当面困難 | ― |
| 11 | 銀行・保険会社(本体) | △ | ・売買・仲介は引き続き不可 ・暗号資産の投資運用業も不可 ・投資目的保有は検討可 |
・投資目的での保有は十分なリスク管理・態勢整備等が行われていることを前提 |
| 12 | 銀行・保険会社(子会社等) | 〇 | ・売買・仲介可能 ・暗号資産の投資運用業・投資目的での保有可能 |
・兄弟会社や関連会社についても子会社と同様 |
| 13 | DEX運営者 | × | ・規制は継続して検討 | ・国際的な議論が必要 ・行政や交換業者等においてリスクについて周知 |
| 14 | DEX UI提供者 | △ | ・リスク説明義務・AML/CFT 対策等の規制を検討 ・各国の規制動向と実態把握に努める |
|
| 15 | 無登録業者 | 〇 | ・刑事罰強化 ・緊急差止命令などのエンフォースメント強化 ・暴利行為として契約を無効にする民事効規定創設の検討 |
・なお、暴利行為として契約を無効とする民事効規定が設けられた場合、影響は◎となる可能性 |
| 16 | マイニング事業者 | × | ― | ・報告書案で言及なし ・ファンドに該当する場合は規制対象 |
| 17 | NFT事業者 | × | ― | ・NFTは原則規制対象外 ・暗号資産やセキュリティートークンに該当する場合は現行法でも規制対象であり改正後も規制対象 |
| 18 | ブロックチェーンゲーム事業者 | × | ― | ・無償付与や報酬としてのトークンの自動付与は資金調達ではないため、規制対象外 |
| 19 | 自己勘定取引 | × | ― | ・「業として」行われるものではなければ規制対象外 |
留保事項
本稿は、報告書の記載、現行法令やガイドラインに基づいて、合理的に考えられる内容を記載したものです。いずれも報告書の記載に基づいた執筆時点における見解であり、必ずしも報告書どおりの規制が導入されるとは限らず、導入された場合であっても実務への影響は異なったものになる可能性があります。
本稿は、当事務所のウェブサイト上で公開する記事として作成したものであり、特定の案件に対する法的助言を構成するものではありません。具体的な案件について法律、会計、税務等のアドバイスが必要な場合には、弁護士、税理士、公認会計士等の専門家にご相談ください。
1. はじめに:暗号資産交換業者のM&Aの背景
暗号資産取引所の運営など、資金決済法で規制される「暗号資産交換業」を日本で行うためには、同法に基づいて「暗号資産交換業者」として登録を得る必要があります。
執筆日時点で、28社の暗号資産交換業者が登録されていますが、これらに加え、内国企業や海外企業で、日本の暗号資産交換業への参入を目指す動きは継続的に見られます。
しかし、暗号資産交換業の登録取得は極めてハードルが高く、申請準備を含めると2〜3年の期間が必要になるケースや、システム開発費・人材コストを含めると数十億円規模の初期投資が必要となるケースもあるようです。
このようなハードルの高さから、新規のライセンス取得ではなく、既登録の暗号資産交換業者の買収を目指すケースも数多く存在しています。
既登録の暗号資産交換業者の買収は、一般的には新たな登録取得よりもハードルは低いと考えられますが、金融規制業種であることなどから、他のM&Aとは異なった論点が存在します。
本稿では、適用される法規制との関係を軸に、暗号資産交換業者のM&Aの各フェーズにおいて検討すべきポイントを概観します。
2. 暗号資産交換業M&Aの特殊性:コンプライアンスの重要性
暗号資産交換業者のM&Aでは、技術や会計、税務、顧客保護など多岐にわたる論点が生じますが、法律の立場から最も重要となるのが資金決済法を中心とする金融規制との関係です。
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業を「適正かつ確実に」遂行するための体制を有していることが法令上求められています3。この要件を満たさない場合、規制当局による立入検査や業務改善命令、さらには登録取消処分がなされる可能性もあります(後記4.1の金融庁事務ガイドラインの記載も参照)4。
コンプライアンスの維持は、M&Aの前後を問わず継続的に求められます。クロージングが完了しても、その前後の対応に問題があれば、後日、規制当局から行政処分を受ける可能性があります。
暗号資産交換業者の企業価値や事業継続性は、コンプライアンス体制の成熟度に強く依存しており、M&Aを成功させるためには、当該分野の規制への理解が不可欠です。
この点、3.以降に述べるとおり、主に以下の点について留意する必要があります。
| ①法規制の遵守、コンプライアンス 暗号資産交換業は、法規制の遵守とコンプライアンス確保が大前提です。買収会社においても、その重要性を十分に認識しておく必要があります。なお、金融実務の経験がない事業会社や外国企業の場合、日本の金融規制の困難さを理解していないケースも見受けられ、事前に慎重な確認が求められます。 ②買収スキーム 暗号資産交換業者の登録は法人格に紐づいているため、ライセンスを維持したい場合、通常は株式譲渡のスキームが採用されます。 ③当局折衝 暗号資産交換業者として求められる体制をM&Aの前後を問わず確保する必要があることから、実務上、規制当局との折衝が不可欠です。特に、現時点で事業実態の乏しい暗号資産交換業者を買収する場合は、買収後に新たな体制整備が必要となり、相応のコストと時間を要する点に留意が必要です。 ④デューデリジェンスと契約調整 法務デューデリジェンスでは、規制遵守状況の確認が重要です。その結果を踏まえ、表明保証や当局との折衝状況を前提とする前提条件など、契約内容の調整が求められます。M&A後の統合に向け、当局折衝やシステム移行を想定した移行支援契約の設計も重要です。 ⑤統合後対応 M&A後の統合プロセスでは、登録簿の変更、社内規程や利用規約の修正・統合、体制変更等について、適用規制を踏まえて規制当局及び自主規制機関(JVCEA)との協議・調整を行う必要があります。 ⑥独禁法・外為対応 これは通常のM&Aにも共通しますが、案件の規模やスキームによっては、独占禁止法上の企業結合規制(公正取引委員会への事前相談や届出等)にも留意が必要です。また、海外企業による買収の場合、外為法の対内直接投資等の届出・報告も必要となる場合があります。 |
3. M&A検討の初期段階における論点
3.1 暗号資産交換業とライセンス内容
暗号資産交換業は厳格な規制を受ける金融業であるため、M&Aの初期段階において、対象企業のライセンスの範囲や適用規制を正確に理解しておくことが必要になります。
(1)暗号資産交換業とは
ライセンス(金融庁への登録)が必要となる「暗号資産交換業」は、資金決済法で以下のいずれかの業務を業として行う場合を指します5。
① 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換、
② ①の媒介、取次ぎ又は代理、
③ ①②に関して、利用者の金銭の管理をすること、
④ 他人のために暗号資産の管理をすること(カストディサービス)
暗号資産のレンディング(貸借)やステーキングサービス(ユーザーの暗号資産をステークし、報酬を還元するもの)などは、一般に交換業には該当しないとされています。
また、ステーブルコインなどの電子決済手段や前払式支払手段、暗号資産デリバティブ取引には、それぞれ異なる法規制(電子決済手段等取引業、金融商品取引業など)が適用されます。
(2)ライセンス内容
暗号資産交換業者であっても、事業者ごとに登録を受けているライセンスの内容は異なります。具体的には、取り扱う暗号資産の名称や業務の内容・方法について、予め金融庁へ届け出る必要があり、これらは暗号資産交換業者登録簿に登録されています(各財務局において誰でも閲覧することができます)6。
また、対象会社が関連分野のライセンス(例:暗号資産デリバティブに関する金融商品取引業、ステーブルコイン関連の電子決済手段等取引業)を併せて保有している場合もあります。したがって、対象会社の保有許認可の範囲を正確に把握し、「現行ライセンスで何ができるか・できないか」を明確にしておくことがM&Aの前提となります。
買収後に新たなサービス展開を予定しており、その内容が現行ライセンスの範囲を超える場合には、ライセンスの変更等の手続き(例えば取扱暗号資産の追加、業務方法書の変更等)が必要になります。また、システムや体制を大きく変更する場合、当局との事前相談や折衝が必要となります。
特に、顧客基盤がほぼ存在せず、システムも未整備な交換業者を買収し、全面的に新しいビジネスを開始する場合、実質的には新規登録と同等の体制整備や当局審査を要することがあります。このような場合、業務開始まで相当の期間(半年から1年以上)とコスト(数億円規模)を要する可能性があり、十分な期間と予算を見込む必要があります。
3.2 登録の承継とスキーム選択
通常のM&Aの場合、株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割など様々なスキームが用いられます。
しかし、暗号資産交換業者のM&Aの場合、暗号資産交換業の登録が法人格に紐付いている点を考慮する必要があります。
(1)未登録事業者による買収
暗号資産交換業の登録を有しない事業者が、暗号資産交換業者を買収して新たにビジネスを行いたい場合、原則として株式譲渡のスキームを取る必要があります(後記4.1の金融庁事務ガイドラインの記載も参照)。
これは、事業譲渡や合併の方法では登録を承継することができず、事業移転後に別途新規登録が必要となるためです。
(2)既登録事業者による再編
一方、既に暗号資産交換業の登録を受けている事業者が、顧客基盤やシステム、人材を取得する目的で他の交換業者を買収する場合には、事業譲渡や合併といったスキームを選択することも考えられます。
ただし、これらの方法が利用できるのは取得側が登録業者である場合に限られ、登録そのものが承継されるわけではありません。
したがって、暗号資産交換業を譲渡する会社や合併で消滅する会社は、いずれも登録廃止の届出を行う必要があります7。
| スキーム | ライセンスの維持 | 解説 |
| 株式譲渡 | ○ | もっとも一般的なスキーム |
| 事業譲渡(交換業者→交換業者) | ○(譲受側) | 譲渡側は廃止。交換業者同士のM&Aでは使用されるケースあり |
| 事業譲渡(交換業者→事業会社) | × | ライセンス廃止のため意味がない |
| 合併(交換業者間) | ○(存続会社) | 消滅会社は廃止。交換業者同士のM&Aでは使用されるケースあり |
| 合併(事業会社が存続) | × | ライセンス廃止のため意味がない |
4. 規制当局対応
4.1 金融庁事務ガイドラインにおける記載
暗号資産交換業は金融業であり、M&Aに際しては規制当局(金融庁・財務局)との対応を検討する必要があります。この点、金融庁の事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)16.暗号資産交換業者関係8の記載を意識することが重要です。
ガイドラインでは、株式譲渡によるM&Aについて「クロージング後の適切な業務態勢に留意する必要がある」とされたうえで、主要株主の変更届出と並んで「日常的なコミュニケーションを通じた情報把握」に努めることが求められています。
また、届出受理後には、役員等との深度あるヒアリングを通じてガバナンスやコンプライアンス体制の適切性を確認するとされており、当局としては、クロージング前の段階から、株式譲渡後のビジネスモデルやガバナンス体制に関する情報共有・対話を重視している姿勢が明確です。
| 金融庁事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)16.暗号資産交換業者関係(下線部は筆者ら) Ⅲ-1-8 株式譲渡等における留意点 (1) 株式譲渡における留意点 近時、暗号資産交換業者の主要株主が他の事業者に株式を譲渡することにより、暗号資産交換業を売却・譲渡するケースが見受けられる。 こうした株式譲渡においては、ビジネスモデルや役職員、内部管理態勢、取引システム等の大幅な変更がなされる場合が多いことから、 株式譲渡後も適切に業務を遂行できる態勢となっているかについて留意する必要がある。 このため、監督当局としては、 暗号資産交換業者との日常的なコミュニケーションを通じて、かかる情報を把握するよう努める とともに、資金決済法上、主要株主の変更は届出事項(事後)とされていることを踏まえ、届出を受理後、経営管理(ガバナンス)や法令等遵守態勢等の内部管理態勢全般に関し、 暗号資産交換業者の役員等との深度あるヒアリング等も踏まえ、その適切性に問題がないかどうか、改めて検証するものとする。 法第63条の5第1項第4号に規定する「暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人」であるなど業務の健全性・適切性に疑義が認められる場合には、 必要に応じ、法第63条の15に基づき報告を求めるものとし、重大な問題があると認められる場合等には、法第63条に基づく業務改善命令等の行政処分(Ⅲ-3)の発動等を検討するものとする。 (2) 事業譲渡における留意点 暗号資産交換業者が他の法人に事業を譲渡する場合、事業を譲り受ける側が財務局登録の暗号資産交換業者でない限りは、 再度、暗号資産交換業の登録を受ける必要があることに留意する。 |
4.2 事前相談
3.2で述べたとおり、典型的な暗号資産交換業者のM&Aでは、株式取得スキームが採用されます。株式取得の場合、資金決済法上は、主要株主の変更に係る届出をクロージング後に行えば足りるとされています9。
しかし、4.1で述べたとおり、金融庁事務ガイドラインでは、株式譲渡に伴う体制変更について、事後届出のみならず「日常的なコミュニケーションを通じた情報把握」を重視する旨が明示されています。このため、買収後の業務運営の適切性を確保する観点からも、クロージング前の段階で当局との情報共有を行うことが実務上強く要請されています。
事前相談の具体的なタイミングとしては、基本合意書の締結後、詳細なデューデリジェンスに入る前の段階で、当局とのコミュニケーションを開始することが考えられます。相談時には、買収の目的・背景、スキーム、資金調達方法、買収後の事業計画、体制変更の内容等を整理して共有することが考えられます。
なお、4.4(2)で述べる登録簿の変更について事前届出が必要な項目を含めると、規制当局との協議には数か月程度要する場合もあります。M&Aのスケジュールの策定にあたっては、当局対応に必要な期間を考慮しておく必要があります。
4.3 株主変更届出
前述のとおり、暗号資産交換業者の主要株主12に変更があったときは、遅滞なく、金融庁に届け出る必要があります。具体的には、変更届出書(暗号資産交換業内閣府令様式10-2)に、株主の名称、保有する議決権の数・割合などを記載した株主の名簿(同様式07)を提出する必要があります13。
4.4 クロージング後の継続監督
買収後、前述の金融庁事務ガイドラインに従い、金融庁によるヒアリングが実施され、暗号資産交換業者の経営管理体制や法令等遵守態勢など、内部管理体制全般の適切性が改めて検証されます。
(1)新体制の適格性確認
クロージング後のヒアリングでは、事前相談の内容も踏まえ、特に以下のような観点から確認が行われることが想定されます。
買収によりビジネスモデルや内部管理体制に大幅な変更が生じる場合には、より慎重な検証が行われます。
| ・財務的健全性 :買収後の財務構造が分別管理義務等の履行に与える影響 ・ガバナンス体制 :親会社グループとの利益相反管理体制、業務運営の独立性確保 ・技術・運用面 :暗号資産管理体制の継続性、システム統合に伴うリスク管理 ・コンプライアンス体制:AML/CFT体制の維持・強化、JVCEA規則への対応体制 ・人材・組織面 :各専門人材の継続確保、組織統合による業務継続性への影響 |
(2)登録簿の変更
4.3で述べたとおり、主要株主の変更を登録簿に反映する必要があるほか、買収後に事業内容や体制に変更が生じる場合には、登録簿に記載された他の事項についても変更届出を行う必要があります。
このうち、取り扱う暗号資産の追加や業務内容・方法の変更(利用者からの申込受付方法の変更、分別管理方法の変更など)は、原則として事前届出事項とされています14。
一方で、役員の変更、他業の種類の変更、暗号資産の取扱停止、その他軽微な変更については事後の届出で足りるとされています。
M&Aに伴い新サービスを提供する場合や取扱暗号資産を追加する場合には、事前届出が必要となるため、当局との事前相談を行い、審査期間を考慮したスケジュール設計を行うことが重要です。特に事前届出事項については、内容によっては審査に数か月を要する場合もあるため、M&A全体のスケジュールに充分な余裕を持たせることが求められます。
5. 法務デューデリジェンス
暗号資産交換業者のM&Aにおける法務デューデリジェンス(DD)では、暗号資産交換業特有の規制遵守状況の調査が最も重要となります。
| 項目 | ポイント |
| 分別管理義務 | 帳簿の整合性、信託会社との契約、ウォレットの区分管理 |
| 体制要件 | 専門人材の確保、最低純資産額の充足、社内規程・監査体制の整備 |
| AML/CFT体制 | 本人確認手続や顧客管理の実施状況、疑わしい取引の届出実績 |
| 取扱暗号資産 | 有価証券該当性、発行者リスク、選定基準 |
| 行政対応履歴 | 違反内容と顧客へ影響、是正措置・再発防止策、当局への報告・対応 |
5.1 分別管理義務
暗号資産交換業者は顧客からの預かり資産について厳格な分別管理義務を負っています。金銭については自己の金銭と分別して信託会社等に信託する必要があり、暗号資産については自己の暗号資産と分別して95%以上をコールドウォレットで管理することが求められています15。
DDでは、顧客勘定元帳などの帳簿と実残高との整合性、信託会社との契約の内容と履行状況、コールドウォレットとホットウォレットの適切な区分管理などについて確認をすることが望まれます。
5.2 体制要件
暗号資産交換業者には、業務を適正かつ確実に遂行するための体制要件として、システム管理者やAML/CFT担当者などの専門人材の確保、最低純資産額の充足、社内規程・監査体制の整備といった複数の条件が継続的に課されています。買収後に経営体制や人員構成の変更が予定されている場合には、当局とのコミュニケーションと併せて、これらの要件を引き続き充足できるかについても検討が必要です。
5.3 AML/CFT体制
犯罪収益移転防止法に基づく本人確認手続やリスクベースアプローチに基づく顧客管理の実施状況、疑わしい取引の届出実績などを確認します。買収により顧客基盤が拡大する場合や、親会社グループの事業特性により新たなマネーロンダリングリスクが生じ得る場合には、既存のAML/CFT体制で対応可能かについても検討が必要になります。
5.4 取扱暗号資産
対象会社が取り扱う暗号資産について、その法的性質や規制上のリスク分析も推奨されます。特に、取扱暗号資産が金融商品取引法上の有価証券に該当する可能性がある場合、暗号資産交換業の登録のみでは取り扱うことができないため、有価証券該当性の検討も必要になります。IEOにより発行されたトークンや、プロジェクトへの投資的性質を有するトークンについては、慎重な検討が必要になります。
また、発行者が存在する暗号資産については、その信用力やプロジェクトの持続可能性、発行者の所在地の明確性なども評価対象となります。JVCEAの自主規制規則においても取扱暗号資産の選定基準が定められており、これらの基準や社内規則への適合性も確認が必要です。さらに、匿名性の高い暗号資産などについては、マネーロンダリング対策の観点からの規制強化などにより将来的に取扱停止を余儀なくされるリスクも考慮する必要があります。
5.5 行政対応履歴
上記を含めた対象会社における規制遵守水準を限られたDD期間中に完全に検証することは困難です。このため、過去の規制当局による立入検査や行政処分の履歴は、対象会社のコンプライアンス体制の成熟度を評価する上で重要な指標となります。
過去に法令違反による届出を行っている場合や、規制当局から業務改善命令や業務停止命令を受けたことがある場合には、違反の具体的内容と顧客への影響範囲、是正措置・再発防止策の実施状況、当局への報告経緯と対応状況などについて特に慎重な検証が必要になります。これらの調査結果は、表明保証条項の内容、クロージング前提条件の設定、価格調整の要因として重要な判断材料となり得ます。
6. 契約実務
| 項目 | ポイント |
| 表明保証 | 登録取消事由や法令違反の有無、顧客資産の分別管理義務の履行状況、過去の行政処分歴 |
| 前提条件 | 規制当局から特段の懸念が示されていないこと、重大なセキュリティリスクが存在しないこと |
| 移行支援契約 | 当局との折衝、ウォレット管理やシステムの移行、顧客通知のサポート |
暗号資産交換業者のM&Aでは、契約の面でもその特殊性を踏まえた設計が必要になります。とりわけ、表明保証条項では、登録取消事由や法令違反の有無、顧客資産の分別管理義務の履行状況、過去の行政処分歴など、業規制に直結する事項について、通常よりも細かな保証が求められる場面が多くなります。
また、取引の前提条件として、システム管理者やコンプライアンス担当者など、重要な役職員の雇用継続を求めるケースも少なくありません。あわせて、規制当局との事前相談の必要性を前提とし、M&A取引や登録内容の変更に関して、「規制当局から特段の懸念が示されていないこと」などを条件とすることも検討されます。ただし、当局はあらかじめ法的な承認や許可を行う立場にはないため、この点については条項上の文言調整が必要になります。
技術・セキュリティ体制に関するDDを行う場合には、外部監査や脆弱性テストの結果を確認し、重大なセキュリティリスクが存在しないこと、あるいは対応済みであることをクロージングの条件とすることもあり得ます。
さらに、買収後の円滑な統合を図るため、売主と一定期間の移行支援契約を締結することが一般的です。この中では、規制当局への報告・相談支援、ウォレット管理やAML/CFT関連システムの移行対応、顧客通知などのサポートについて、内容や提供期間、対価、延長・終了の条件などをあらかじめ定めておく必要があります。
7. 独禁法・外為法上の留意点
暗号資産交換業のM&Aは、一般の企業買収と同様に、独占禁止法や外国為替及び外国貿易法(外為法)上の規制にも留意する必要があります。
7.1 独占禁止法(企業結合規制)
案件の規模によっては、公正取引委員会への届出や事前相談が必要となる場合があります。暗号資産交換業は登録業者数が限られており(28社)、既存の交換業者同士の統合では市場シェアが問題となる可能性もあり、届出義務の有無を確認する必要があります。届出が必要な場合、審査期間(通常30日、延長の場合120日)をM&Aスケジュールに織り込む必要があります。
7.2 外為法(対内直接投資規制)
外国投資家が日本の暗号資産交換業者の株式を取得する場合、外為法上の「対内直接投資等」に該当し、原則として日本銀行を通じて財務大臣および所管大臣への事前届出が必要になります。暗号資産交換業は「補助的金融業等」として事前届出対象業種に含まれるため、届出書が受理された日から30日間は投資実行が制限されます。この期間は実務上は14日に短縮されることが多いものの、外国投資家の属性・出資比率・経営関与の程度に応じて追加資料の提出が求められる場合もあるため、買収スケジュールを策定する際には、届出受理から30日以上の期間をM&A全体スケジュールに組み込んでおくケースが少なくありません。
8. 統合後対応
| 項目 | ポイント |
| 当局対応 | 財務的健全性、ガバナンス体制、技術・運用面、コンプライアンス体制、人材・組織面 |
| 登録簿の変更 | (事前)取扱暗号資産の変更、暗号資産交換業の内容・方法の変更 (事後)主要株主の変更、役員の変更、他業の種類 |
| 顧客対応 | 告知内容・タイミング、利用規約の改訂 |
| 社内規程 | 新しい体制や業務内容を踏まえた統合 |
暗号資産交換業者の買収では、クロージング後も顧客対応、社内規程の改訂や人材確保、システム統合など、多くの実務的課題が存在します。なお、規制当局との継続的なコミュニケーションや登録簿の変更手続きについては、4.4で述べたとおりです。
顧客対応については、買収の公表と同時に、取扱暗号資産の継続性、サービス内容の変更有無、顧客資産の安全性、利用規約の修正などについて、ウェブサイトやメール等を通じた適切な情報提供を行うことが想定されます。暗号資産交換業者として必要な社内規程についても、買収後の新体制に合わせた統合や改訂が必要になります。システムについては、技術的な互換性、統合に伴うセキュリティリスク、統合期間中の運用体制などについて、統合により問題が生じないよう、事前の調査を踏まえた統合が必要になります。
これらの統合プロセスを円滑に進めるため、実務上は6.で述べた移行支援契約に基づき、売主から一定期間の協力を得ることが必要になる場合があり、契約段階で支援の提供期間や早期終了・延長の条件などを明確に定めておくことが円滑な統合に寄与します。
9. おわりに
暗号資産交換業者のM&Aは、規制環境の特殊性、技術的な複雑性、専門人材への依存度の高さなど、通常の企業買収とは異なる多くの困難を伴います。規制当局との事前相談から買収後の継続監督に至るまで当局対応に相当な期間・コストを要するほか、限られたDD期間では規制と実務の網羅的な検証が困難であることを前提とした契約面でのリスク手当も必要になります。
暗号資産規制の金商法への移行が議論されるなど規制環境は今後も変化していくことが予想されますが、本稿が暗号資産交換業者のM&Aを検討するにあたって全体を俯瞰する一助となれば幸いです。
留保事項
- 本稿は、現行法令やガイドラインの記載、筆者らの経験に基づいて、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。これは筆者らの執筆時点の見解であり、今後見解を変更する可能性があります。
- 本稿は、当事務所のウェブサイト上で公開する記事として作成したものであり、特定の案件に対する法的助言を構成するものではありません。具体的な案件の法律、会計、税務等のアドバイスが必要な場合には、弁護士、税理士、公認会計士等の専門家にご相談ください。
I. 初めに
暗号資産の価格上昇に伴い、ビットコインは「デジタルゴールド」としての地位を確立しています。
南米やアフリカでは金融インフラが不十分な地域を中心に、ビットコインやステーブルコインが日常決済で急速に普及しています。例えば、エルサルバドルではビットコインが法定通貨として採用され、納税や個人間送金にも活用されています。先進国アメリカでも、オンラインショッピングやサブスクリプションサービスでCrypto決済を導入する企業が増えています。
一方、日本では2017年にビックカメラがビットコイン決済を導入したことが大きなニュースになったものの、その後のCrypto決済の普及は限定的に留まっています。主な要因は、Crypto決済時に利益が確定し個人の場合には最大55%の課税が発生すること、少額決済の記録や確定申告の手間が大きいことです。ただし、値動きが少ないステーブルコインが普及すれば、日本でもCrypto決済が広がる可能性があり、実際にステーブルコインで支払えるクレジットカードの発行が予定されています。
本稿では、Crypto決済の仕組みを解説し、日本で導入する際の法律上の論点について述べます。
本稿の「Crypto決済」とは、暗号資産決済やステーブルコイン決済を含む幅広い概念として扱いますが、法律議論は主に暗号資産を中心として議論します。ステーブルコインの売買や管理に関する規制は概ね暗号資産規制と同様であり、適宜、読み替えてお読み下さい。
※本稿は、2025年1月30日に筆者が発表した「Crypto決済と日本法」を改訂したものです。
II. 世界のCrypto決済の例
Crypto決済の例は、大きく分けて二つのカテゴリーに分けられます。一つはCryptoを直接決済に使用する例、もう一つはクレジットカードやデビットカードを使用した例です。下記では、Crypto決済の一部を紹介します。
1. Cryptoを直接決済に用いる例
- アメリカ
- Overstock.com:ビットコイン決済を受け付ける大手オンライン専門店。
- Whole Foods:デジタルウォレット「Spedn」でビットコインやイーサリアム決済が可能。
- Starbucks:「Bakkt」プラットフォームを使用した決済を一部店舗で実現。
- エルサルバドル
- ビットコインが法定通貨として活用され、税金の支払や個人間送金にも用いられている例があります。
- シンガポールや韓国
- シンガポールではフィンテック企業がCrypto決済の導入を推進。
- 韓国のゲームプラットフォームでも決済が活発。
- スイス
- ルガーノ市では税金や市のサービス利用料の支払いの他、マクドナルド等各地でビットコイン決済が可能。
- 日本
- ビックカメラが2017年に国内大手量販店として初めてビットコイン決済を導入。当時大きな話題となり、日本におけるCrypto決済の象徴的な事例となった。
2. Crypto決済にカードを用いる例
- クレジットカード16/デビットカード型
- NEXO Card: デビットカードとクレジットカードを切替可能。クレジットの場合、預託している暗号資産を担保にして資金貸付。当該資金がクレジットの支払に充てられる。デビットモードの場合には使用時に即座に暗号資産が売られる
- Slash Card(日本):アイキタス社が発行者、オリエントコーポレーション(オリコ)がBINスポンサー、スラッシュ社がプログラムマネージャーとして発行を予定するカード。利用者は自身のウォレットにUSDCを保持し、その額を担保として円建て決済が可能17。
- ナッジカード(日本): ナッジカードは、月1回銀行口座からの自動引き落としの他、任意のタイミング・金額で返済できるが、その返済方法としてコンビニATM払いや銀行振込のほかJPYCを選択できるようになる18。
- デビットカード型
- XAPO Card:ジブラルタルの暗号資産銀行であるXAPO Bank発行のカード。USDのほかBitcoinを裏付けにデビット
- Binance Card:暗号資産を自動的に決済時に現地通貨に変換。
- Coinbase Card: Cryptoを用いたリワードを獲得可能。
- BitPay Card:Bitcoin、Bitcoin Cash、USDをサポート。
- プリペイドカード型
- Crypto.com Visa Card:チャージ型のカード。ステーキングに対するリワードが変化。
III. Crypto決済と日本法
1. 法律のまとめ
| 資金決済法の暗号資産規制 | 割販法、貸金業法、前払式支払手段規制 | 外為法 | |
| 自社店舗によるCrypto決済受入れ | なし | なし | 非居住者又は国外との3000万円以上の決済の場合には外為法の報告 |
| 決済代行業者を利用したCrypto決済 | 決済代行業者に売買規制の適用可能性 | なし | 同上 |
| クレジットカード型 | 保管規制、売買規制の適用可能性 | 割販法(ショッピング)及び貸金業法(キャッシング)の適用可能性 | 同上 |
| デビットカード型 | 保管規制、売買規制の適用可能性 | なし | 同上 |
| プリペイドカード型 | なし | 自家型又は第三者型として前払式支払手段規制の適用 | 同上 |
2. 自社店舗によるCrypto決済
自社の実店舗やオンライン店舗でCryptoを決済に収受する場合の規制を解説します。
日本では、暗号資産の売買、その媒介や他人のためにする管理は、暗号資産交換業として規制されています。しかし、自社の店舗でCryptoを決済として受け取ること自体については規制が存在しません。
また、受け取ったCryptoを自社で保有したり、暗号資産交換業者を利用して金銭に交換することにも規制はありません。
ただし、非居住者や国外口座との間で、3000万円以上の決済を行う場合は、原則として外為法上の報告義務が発生します(外為法55条)。この報告義務は、3000万円相当のCryptoでの決済場合も同様であり、居住者による報告が必要となります。この外為法上の報告義務は、3以下の場合でも同様に当てはまります。
3. 決済代行業者を利用したCrypto決済
日本の会社の中には、自社で暗号資産を保有したり管理したりすることに抵抗感を持つ会社が存在します。これは、価格変動リスク、ハッキングなどのセキュリティリスク、会計や税務上の問題などが原因として挙げられます。
このような会社は、第三者である決済代行業者(以下「決済代行者」といいます。)を利用し、決済代行者が暗号資産を収受し、これを日本円に変換して店舗などの会社に渡すスキームが取られることがあります。
このスキームは、下記の行為の組み合わせとなります。
- 暗号資産を他人のために収受する。
- 収受した暗号資産を他人のために日本円に変換する。
- 変換した日本円を会社に渡す。
しかし、この中の「②暗号資産を日本円に変換する」行為は、決済代行者が暗号資産交換業を営んでいるとみなされ、原則として暗号資産交換業の登録が必要と考えられます。
この点について、日本ではコンビニエンスストアや宅配便業者による収納代行が特に規制なく行われていることとの比較が問題となります。決済代行者が行う行為も収納代行であり規制は存在しないと考えられないか、以下のような整理ができないか問題となります。
- 店舗から決済代行者が収納代行の権限を与えられる。
- 決済代行者は暗号資産を自分のものとして収受する。
- その委任事務の処理の一環として日本円を渡す。
- これは変換行為ではなく、委任事務の処理上の支払い方法にすぎない。
このような考え方は理論上は可能かもしれませんが、筆者の経験では、実際の運用では当局との議論が厳しくなる可能性が高いと考えられます。そのため、実務上は暗号資産交換業の登録が必要な可能性が高いと考えておくのが安全でしょう。
ただし、他の業務や委任された事務に付随する形で行われる場合、その具体的な内容によっては許容される可能性もあります。この点については、ケースごとに慎重な検討が必要です。
4. クレジットカードタイプ
(1)仕組み
クレジットカードタイプのCrypto決済として考えられる典型的な例は、次のような仕組みになります19。
- 暗号資産交換業者またはその連携会社がクレジットカードを発行。
- ユーザーが円立てやドル立てで商品を購入。
- 通常のクレジットカードとは違い、決済はユーザーの暗号資産交換業者のアカウントからビットコインなどが引き落とされる。
(2)割賦販売法
日本において、クレジットカードの発行に「2か月を超える分割支払い」「リボルビング支払い」「ボーナス一括支払い」などの機能を付す場合には、「包括信用購入あっせん」となり、割賦販売法上の包括信用購入あっせん業者としての登録が必要となります(同法31条)。この登録を受けると、顧客に対する情報提供義務、過剰与信防止義務、抗弁の切断の制限など、同法に基づく各種規制が適用されます。
一方、支払方法が「2か月以内の1回払い(いわゆるマンスリークリア)」に限られるカードは、包括信用購入あっせんには該当せず、同業者としての登録は不要です。ただし、この場合でも「二月払購入あっせん」(割販法35条の16第2項)に該当するため、カード番号等の適切な管理措置の実施義務(同条1項)が課されます。
暗号資産にリンクするクレジットカードであっても、付与される機能に応じて上記の規制が適用されます。
(3)貸金業法
クレジットカードのキャッシング機能は、商品やサービスの購入ではなく、借入であるため、割賦販売法ではなく貸金業法の規制対象となります。
暗号資産にリンクするクレジットカードであっても、キャッシングを円や外貨で行える場合には貸金業が適用されます。ただし、暗号資産でキャッシングできる場合は、暗号資産レンディングには原則として貸金業法が適用されないため規制対象外です(貸金業法2条の定義参照)。
(4)暗号資産法
①カストディ行為に関する規制
暗号資産にリンクしたクレジットカードの場合、発行者が利用者の暗号資産を直接保管する構造であれば、暗号資産交換業(資金決済法2条7項)のうちカストディを行う者として規制が適用されます。
ただし、以下のような場合には、カストディに当たらず規制対象外となる可能性があります:
・スマートコントラクトやマルチシグを利用し、特定の事業者が単独で秘密鍵を管理できない構造とする場合
・カード利用代金の弁済を担保する目的で担保として暗号資産を預かる場合であり、「他人のために管理する」行為に当たらないと整理できる場合
② 売買行為に関する規制
カード決済の過程で暗号資産を法定通貨に換金する行為は、暗号資産の売買に当たり、原則として暗号資産交換業の登録が必要です。典型例は次のとおりです。
(a)ユーザーがクレジットカードで商品を購入
(b)利用代金に相当する暗号資産をユーザーが保有口座から売却し、その売却代金(円等)がカード発行会社に支払われる
このような場合、暗号資産の売買(またはその媒介)に該当します。
暗号資産での弁済スキーム
一方で、カード発行会社が通常は円建てで請求を行い、利用者が支払期日までに「円の代わりに暗号資産を差し入れる」という形を選択できるスキームであれば、これは一種の決済方法の指定、または代物弁済と評価されるにとどまり、暗号資産の売買には当たりません。この場合、暗号資産交換業の登録は不要と解されます。
もっとも、割賦販売法では支払方法や計算方法の表示規制があり、これにどう対応するかが課題となります。また、カード発行会社が暗号資産を受け入れる際の会計・税務処理や、チャージバックが発生した場合に暗号資産価格が変動しているケースへの対応など、実務上、検討すべき点も多いと考えられます。
犯収法(補足)
なお、補足すると、クレジットカード発行者、暗号資産交換業者などは、犯収法上の特定事業者に該当し、本人確認(KYC)義務を含むAML/CFT規制が課されます。また、アクワイヤラー(クレジットカード番号等契約締結業者)については、加盟店調査義務が課されており、これはマネーロンダリング対策としての機能を果たしています。
5. デビットカードタイプ
(1)仕組み
デビットカードタイプのCrypto決済の典型的な例は次のような仕組みです。
- 暗号資産交換業者またはその連携会社がデビットカードを発行。
- ユーザーが暗号資産交換業者にビットコインなどを預託。
- ユーザーは預託した暗号資産の範囲で、円立てやドル立てで商品を購入可能。
- 商品購入時に、ビットコインが自動的に円転される。
(2)デビットカード発行に関する規制
日本では、デビットカードは即時決済のため割賦販売法の適用はありません。ただし、ユーザーの金銭を預託させてカード決済に利用する仕組みを構築する場合、その金銭の受入れは銀行免許または資金移動業登録が必要です。利用者の指図によって資金を移転する点で為替取引性があるため、この観点からも銀行免許または資金移動業登録が必要と整理されます。
一方、暗号資産を連携したデビットカードの発行には銀行法は適用されず、以下の論点が生じる可能性があります。
(3)暗号資産法(資金決済法上の暗号資産規制)
暗号資産を連携させたデビットカードについては銀行法は適用されませんが、以下の論点が生じます。
・他人の暗号資産を業として管理する場合は暗号資産交換業の登録が必要
・決済時に暗号資産を売却し、その代金で支払う仕組みは暗号資産の売買に該当し、交換業の登録が必要
・カード会社が円で請求し、ユーザーが代物弁済として暗号資産を差し入れる場合は交換業には該当しない
6. プリペイドカードタイプ
(1)仕組み
前払式支払手段とは、図書券やAppleギフトカード、Amazonギフトカードのように、事前に対価を支払い、その対価に応じた、残高などが付与され、残高で決済ができる仕組みをいいます
前払式支払手段型のCrypto決済は、次のような流れになります。
- 発行会社がプリペイドカードを発行。
- ユーザーが発行会社にビットコインなどを送付。
- 送付されたビットコインの時価に従ったチャージが行われる。例:0.001BTCであれば1.5万円相当。
- ユーザーがカードを使用した際に、チャージ残高から減額される。
(2)前払式支払手段の発行規制
日本における前払式支払手段の発行は、「自家型」と「第三者型」に分けられます。
- 自家型: 発行会社自身の製品やサービスのみを対象とした支払手段。
- 第三者型: 他社の製品やサービスにも対応できる支払手段。
自家型の場合には届出、第三者型の場合には登録が必要となり、いずれの場合も未使用残高の半分の供託などの規制がかかります。
ただし、次の場合は規制が適用されません。
- 自家型、第三者型を問わず、有効期間が6ヶ月未満に設定されている場合
- 自家型で3月末及び9月末の未使用残高合計が1000万円以下の場合
(3)暗号資産法の適用
プリペイドカードは、クレジットカードやデビットカードと異なり、原則として暗号資産交換業の規制は適用されないと考えられます。この理由は下記のとおりです。
- 発行会社は暗号資産を保管しているわけではない。
- チャージで、暗号資産の金額に応じたチャージがなされるが、これは金銭と暗号資産の交換ではない。あくまで前払式支払手段の発行行為にすぎない。
- 暗号資産同士の交換にも該当しない。
ただし、チャージした暗号資産を、再度暗号資産に戻すこと(払い戻し)が可能なスキームの場合、実質的には暗号資産の預託とみなされ、暗号資産交換業におけるカストディ規制が適用される可能性があります。
IV. 法律以外の問題
1. Crypto決済と税務
(1) Crypto決済時の利益確定について
Crypto決済は、決済を行った時点で利益が確定したとされ、この利益に税が課されます。たとえば、1万円で取得した暗号資産が5万円に値上がりし、その暗号資産を使用して決済を行った場合、4万円の利益が発生します。この利益は、個人の場合「雑所得」に分類され、他の所得と合算した総合課税にて、最大55%の税率が適用されます。
(2) 少額決済の記録と確定申告の手間
Crypto決済を行った場合には、上記のような課税がなされるため、原則として確定申告が必要になります。雑所得が20万円以下であり、かつ1か所から給与を受け取らない給与所得者である等の場合には確定申告の義務がありません。
しかし、雑所得が20万円を超える場合や、雑所得が20万円以下でも自営業者、フリーランス、副業がある等でそもそも確定申告の義務がある場合、Crypto決済での利益についても1円単位で申告する必要があります。
たとえば、日常的な買い物で暗号資産を使用した場合、各取引時点の暗号資産の時価を記録し、その利益を合算して申告することが求められます。この記録と計算の手間は非常に煩雑であり、特に少額決済を頻繁に行う場合、実務上大きな負担となります。
なお、この問題は、本来は、海外旅行で余った外貨を後日使用した場合にも適用されます。例えば1ドル120円の時に入手した10ドルを、何年後かの海外旅行で1ドル150円で使用した場合には、差額の30円×10ドル=300円について雑所得として課税され、確定申告が必要となる場合があります。
(3) Crypto決済への海外での課税
海外では暗号資産に関するキャピタルゲイン課税がない国や、ある場合にも少額の場合や長期保有の場合に課税対象外とする、という国があります。
(各国の税制=Chat GPT等調べ)
| 1 | 個人の暗号資産取引についてキャピタルゲイン課税がない国 | シンガポール、ポルトガル、スイス、マレーシア、UAE、エルサルバドル |
| 2 | 個人が長期で保有した場合、キャピタルゲイン課税がない国 | ドイツ(1年以上保有した場合には非課税) |
| 3 | 一定の限度額の範囲でキャピタルゲイン課税がない国 | イギリス(年間6000ポンド=約120万円まで) イタリア(年間2000ユーロ=約32万円まで) 韓国(年間2500万ウォン=約250万円まで) ブラジル(月額35,000ブラジルレアル=約90万円まで) |
| 4 | 少額決済には非課税の国 | オーストラリア(1取引が10,000豪ドル=約90万円以下の「個人的利用目的(Personal Use Asset)と見なされる場合、非課税) |
| 5 | 少額決済への非課税化を現在議論中の国 | アメリカ(現在は短期保有か1年以上保有の長期保有かに分けて課税。1回あたり200ドルまで利益の少額決済については課税しない議論が進行中) |
| 6 | 少額決済でも基本的に課税される国 | 日本(但し、確定申告義務ない人の場合には20万円までの雑所得は非課税)、 フランス、カナダ、アルゼンチン |
日本で暗号資産のキャピタルゲインを課税しない議論は極めて難しいと思われます。また、G7でも米国、フランス、カナダが課税の現状下、少額決済に課税しないとの議論を当局に説得的に要望することは難しいかもしれません。 しかしながら、各国がWeb3の進展を図る中、特に米国で少額決済の非課税化が通った場合には、日本でも競争政策上少額決済の利益には課税しない等の制度を導入することが必要なのではと思われます。
2. カード発行と国際ブランドとの接続
暗号資産リンク型のカードを発行する際には、多くの場合、国際ブランド(VISA、MasterCard、Amex、JCB、Dinersなど)と契約し、その決済ネットワークを利用します。この際、国際ブランドは、自身の所在地国等での規制を順守等するため、カード発行体に対して以下のような審査を行うことが通例です:
- KYC(顧客確認手続き)とAML(マネーロンダリング防止)対策:発行者の財務状況、事業履歴、コンプライアンス体制が審査されます。
- 不正取引防止とセキュリティ対策:暗号資産取引の追跡可能性や取引の安全性に関する基準を確認。
- チャージバック対応:消費者保護の観点から、チャージバックに対応できる体制の整備が求められます。
さらに、国際ブランドと直接契約する代わりに、既に国際ブランドと強固な関係を持つ日本のクレジットカード会社を通じて提携カードとして発行する方法もあります。この場合、カード発行プロセスの一部が簡素化される可能性がありますが、それでも一定の規制対応やコストが発生する点には注意が必要です。
V. 今後の発展の可能性、課題
本邦ではCrypto決済は必ずしも普及していません。最大55%の課税や少額決済の記録・申告の煩雑さが最大の要因と考えられます。
ステーブルコインが普及すれば、価格変動リスクは軽減され一定の解決が見込まれますが、普及度はなお未知数です。加えて、利用者保護やAML対応など制度面の整備も課題となります。
今後、Web3分野での国際競争の観点からも、Crypto決済の税務面が改善されることが期待されます。
留保事項
- 本書の内容は関係当局の確認を経たものではなく、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。また、筆者の現状の考えに過ぎず、筆者の考えにも変更がありえます。
- 本稿は、Crypto決済の利用を推奨するものではありません。
- 本書はBlog用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律アドバイスが必要な場合には各人の弁護士にご相談下さい。
1. SFが現実になる日
「もしあなたを裁くのが人間ではなくAIだったら?」
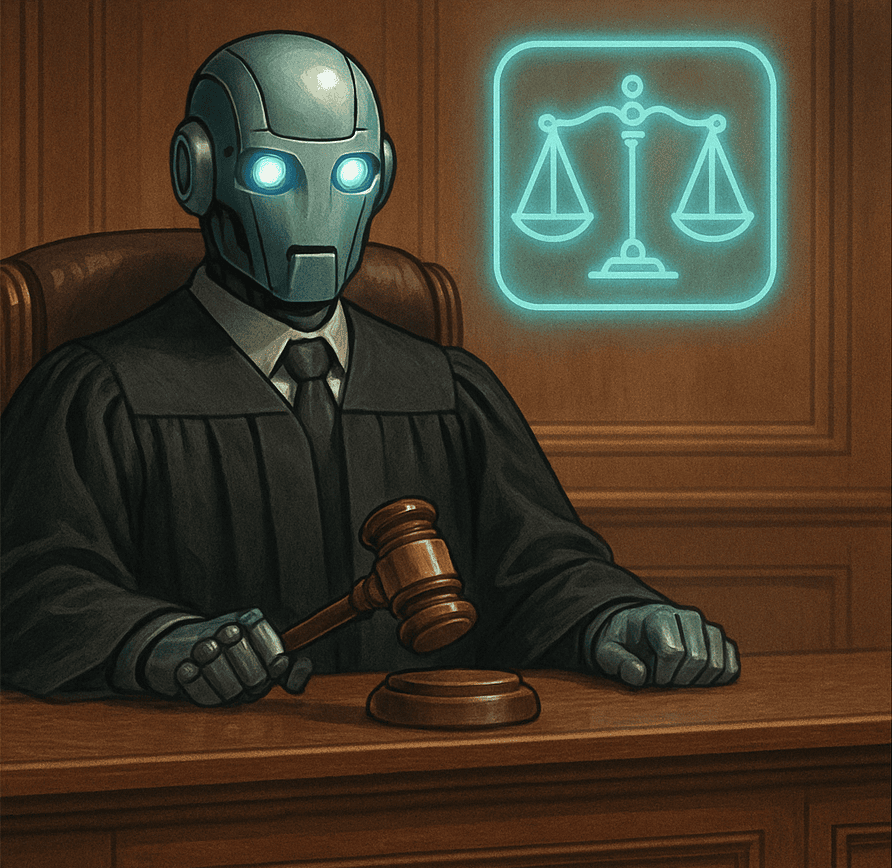
かつてはSFの世界だけの問いかけでした。しかし今や、監視カメラの解析や裁判所のデジタル化といった形で、AIは着実に司法と警察の領域へ入り込みつつあります。本章では、AI警察・AI裁判官が現実にどこまで進んでいるのかを概観します。
(1)想像してみてください
深夜、あなたがコンビニから出た瞬間、交差点のカメラが赤信号の横断を自動検出。街頭スピーカーから大音量で警告が流れ、違反切符がその場で電子的に発行、数日後には銀行口座から反則金が自動的に引き落とされます。
駅前の防犯カメラは指名手配写真と通行人の顔を照合し、ヒットすれば直ちに人間の警察官に通知されます。
法廷では、AIが膨大な証拠映像やデータを解析し証拠リストを自動整理。離婚訴訟では過去の判例データから慰謝料の水準を算出し、刑事事件では類似事件を参照して量刑の目安を提示します。最終的にAIが起案した判決理由案をAIが読み上げ、有罪か無罪かを言い渡します。
これはSF的な思考実験ですが、決して荒唐無稽ではなく、技術の進歩次第で現実化する可能性を秘めています。
(2)世界ではすでに始まっている
実際、AI技術の司法・警察分野への導入はすでに世界各地で現実の制度として稼働しています。単なる実験や検討ではなく、「本格運用」が進んでいる国もあります。
| 中国 | 全国の裁判所で「智慧法院(スマート裁判所)」の構築が進行中で、文書作成や量刑支援などの実務でAIが実用化されています。さらに、警察分野では北京市や深圳市を中心に、街頭カメラと顔認証AIを組み合わせた監視システムが広く展開されています。 |
| エストニア | 2019年に「ロボット裁判官」構想が報じられ、司法省は公式に否定したものの、少額紛争でのAI導入については継続的に検討されています。世界でも最先端の「デジタル国家」として、AI司法の議論が続いています。 |
| 米国 | 再犯リスク評価AI「COMPAS」が刑事裁判で導入されました。人種バイアス問題で批判を受けたものの、実際に判決判断の参考資料として活用された実績があります。現在は州ごとに規制や見直しが進められています。 |
(※各国の詳細は第4章参照)
(3)日本でも進む制度化
日本でも変化が進んでいます。改正民事訴訟法により、段階的施行・政令指定に基づき、遅くとも2026年5月までに民事訴訟のIT化が全面施行される予定です。2025年5月3日の憲法記念日前の記者会見では、最高裁の今崎幸彦長官が「司法判断にAIが関わる可能性も否定できない」と一般論ながら言及しました。
警察分野でも、防犯カメラ映像の解析や交通違反の自動検知システムの導入が検討されています。近年の警察庁による顔認証技術の実証実験などもその一例です。
(4)本稿の立場:現実的な導入路線
AIの司法・警察分野への導入は避けられません。当面は支援中心ですが、段階的に自動処理へ、さらに将来的には一部自動判決へ進む可能性があります。
人々はすでにAIを日常的に利用し、その利便性を体感しています。今後、「AI警察の方が信頼できる」「AI裁判官の方が公平だ」と国民が考えるようになれば、AIを選ぶ社会になるかもしれません。
もちろん、無批判な信頼は危険です。AI依存による人間の判断力低下や、ハッキングなどのセキュリティリスクにも備えが必要です。
映画や小説ではAI社会はしばしばディストピアとして描かれます。しかし現実のAI導入は、必ずしもそうした方向に進むとは限りません。むしろ、公平で効率的な社会に資する可能性も十分にあります。本稿はその分岐点を意識しつつ、制度設計でリスクを抑えつつメリットを最大化する道筋を探ります。
(5)用語の整理:混同を避けるために
この記事ではAIの関与レベルを次のように区別します。
| AI支援 | AIが情報整理や提案を行うが、最終判断は人間が行う |
| 自動処理 | AIが一次処理を行い、異議申立があれば人間が審査する |
| 自動判決 | AIが最終的な法的判断まで行う(将来的可能性として想定) |
現在の実用は主にAI支援です。自動処理は限定分野での実験段階であり、近い将来に拡大する見込みです。自動判決には技術的・法的課題が多く、長期的な検討課題といえます。
2. AI警察システムの可能性と法的課題
(1)警察活動を縛る基本ルール
AI警察を考える前に、現行法の基本ルールを確認しておきましょう。
| ・令状主義(憲法35条) 裁判所の令状なしに住居などを捜索することはできません。AIによる監視や行動解析が「強制処分」にあたる場合、この制約を受けます。最高裁は2017年(平成29年3月15日)GPS捜査事件で、車に無断でGPSが付された事実関係の下ですが「継続的・網羅的な位置情報取得は強制処分」と判断しました。AI監視による行動パターン分析も同様の法理が適用される可能性があります。 ・比例原則・任意捜査の限界 裁判例は「必要性や相当性を逸脱した任意捜査は違法」としています。AIが長時間・広範に市民を監視することが「過剰」と評価されれば違法になる可能性があります。 ・個人情報保護法の原則 目的を限定し、必要最小限のデータのみを収集・保存する義務があります。顔認証データのような「個人識別符号」は特に厳格な取り扱いが求められます。 |
(2)AIに任せられること:24時間眠らない警察官
AI警察システムが実現すれば、次のような機能が期待されます。
- 防犯カメラの常時監視
数千台のカメラを同時監視し、不審行動を瞬時に検知。人間では不可能な規模です。 - 犯罪予測によるパトロール配置
過去のデータをもとに「午後3時頃○○駅周辺で置き引きが発生しやすい」と予測し、警察官を効率的に配置。米国などで試みがありましたが、差別懸念から停止された例もあります。 - 指名手配犯の自動発見
空港や駅で顔をスキャンし、データベースと照合。即時発見につながります。
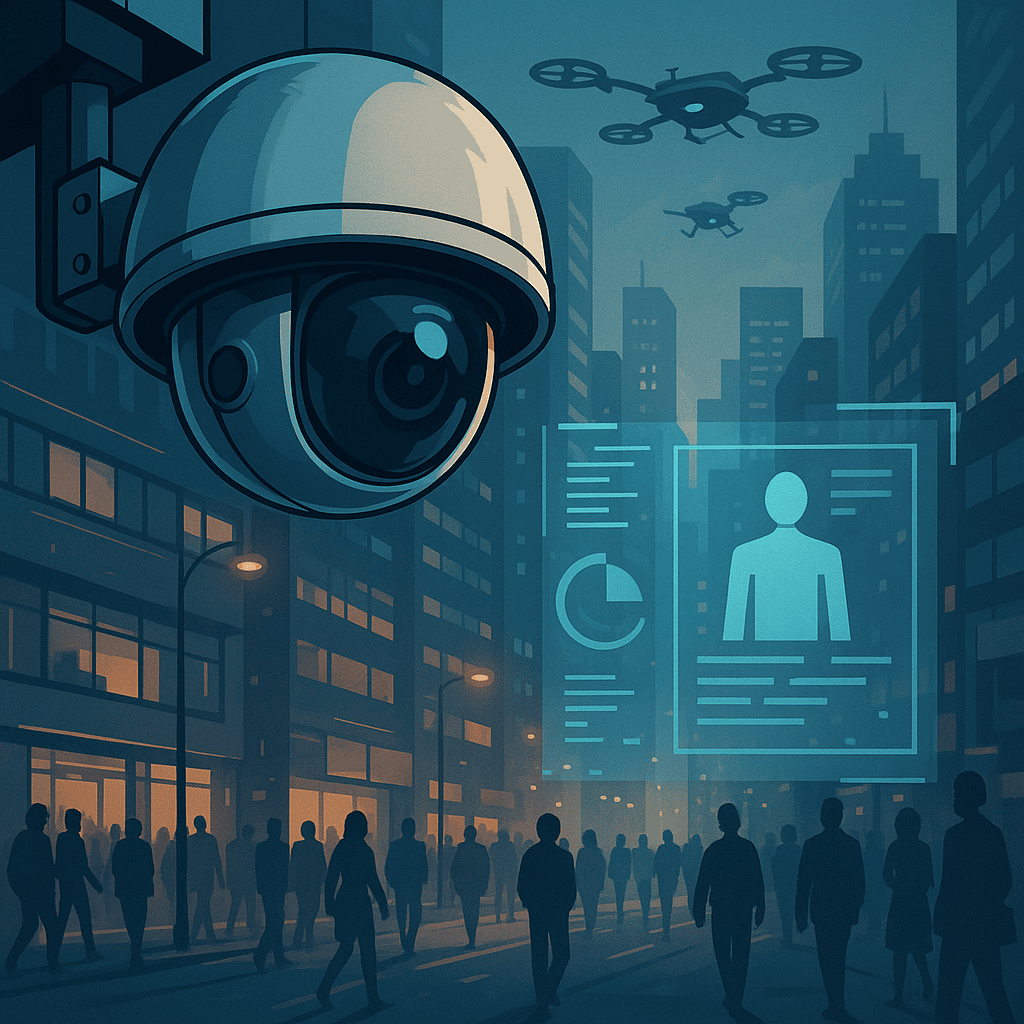
(3)利点と効果
- 人手不足の補完:深夜や休日の監視をAIが代替できる
- 見落としの減少:膨大なカメラ映像を同時に処理できる
- 判断の一貫性:感情や疲労に左右されない
(4)法的・実務的課題
- プライバシーとの衝突
憲法13条を根拠として判例上認められているプライバシー権と、AI監視は深刻に衝突します。京都府学連事件最高裁判決(昭和44年)では、みだりに容貌等を撮影されない自由を認め、Nシステム判決(東京地裁平成13年)では、自動車ナンバーの無差別収集にも一定の制約があることが示されました。 - 誤認逮捕の責任
AIが無実の人を誤認した場合、国家賠償は当然ですが、開発者や運用者の責任は不明確です。特にマスク着用時の顔認証精度は低下し、誤認率が10%を超えるという研究もあります。日本の社会環境では深刻な課題となり得ます。 - 偏見の再生産
過去の犯罪データを学習したAIは、特定の地域や属性を過剰に「要注意」と判定しがちです。米国では黒人に高リスクを付ける事例が問題になりました。日本でも十分に起こり得ます。
(5)技術と法のスピードギャップ
技術の進歩は早い一方、法律改正には時間がかかります。そのため「技術が先に導入され、法整備が後追い」というなし崩し導入のリスクがあります。さらに、AIの判断根拠が説明できなければ、適正手続の観点で致命的な問題となります。
(6)本章のまとめ
AI警察システムには大きな利点がある一方、憲法上の制約やプライバシー侵害のリスクが避けられません。導入にあたっては、特に次の3点が不可欠です。
| 人間の関与 | 重要判断は必ず人間が最終確認する |
| 透明性 | 誤認率や判断基準を公開し、市民に説明できる形にする |
| 異議申立制度 | 市民が容易に不服を申し立てられる仕組みを整える |
→ 当面は「AI支援」が基本ですが、制度設計と監査体制を前提に「自動処理」へ広がる可能性があります。
3. AI裁判システムの構想と現実
(1)想定される役割:司法の効率化と一貫性
AI裁判官システムが導入されれば、司法制度は大きく変わる可能性があります。
- 膨大な電子証拠の解析
SNSやメール、監視カメラ映像、クラウド上の取引データなど、人間なら数か月かかる証拠をAIが短時間で整理できます。 - 複雑な商事紛争の支援
契約条項や会計データを横断的に比較し、争点やリスクを抽出。大規模商事事件や知財訴訟で特に効果を発揮します。 - 量刑の一貫性確保
同種事件における地域差や裁判官ごとの差を抑え、統一的な基準を提示できます。 - 軽微事件の半自動処理
現在でも交通違反の反則金制度や少額訴訟など迅速処理の仕組みはあります。将来は、軽微な窃盗、争いの少ない薬物事件、一定の民事訴訟などにAIが関与し、司法リソースの効率的な配分につながる可能性があります。ただし、どこまで拡大を許すかが最大の論点となります。
(2)民事と刑事で異なる導入可能性
AI裁判官の導入可能性は、民事と刑事で大きく異なります。
- 民事事件
当事者の処分権主義が原則であり、AI判決を当事者が合意して選択する仕組みであれば、比較的柔軟に導入できます。 - 刑事事件
被告人の権利保護が中心であり、強制力を伴う以上、導入には一層の慎重さが求められます。AIが量刑の参考情報を提示する程度が当面の限界といえます。 - 仲裁との比較
仲裁法では当事者の合意により仲裁人を自由に選任できます。したがって「AI仲裁人」は憲法上の制約を受けにくく、商事紛争において先行導入される可能性があります。
(3)法的論点:司法権の根幹に関わる課題
| ・憲法32条(裁判を受ける権利)との関係 すべての国民は裁判を受ける権利を有します。したがってAI裁判官を導入する場合でも、人間による裁判を選択できるルートを確保することが不可欠です。 ・司法権の担い手としての適格性(憲法76条) 司法権は裁判所に属し、裁判官は「良心に従ひ独立して」職務を行うと規定されています。良心を持たないAIに司法権を委ねることは、憲法制度と矛盾する可能性があります。ただし、当事者が事前に同意して「AI判決」を選択する仕組みであれば、一定の合憲性を確保できる余地もあります。 ・裁判の公開原則(憲法82条) 裁判は公開法廷で行わなければなりません。AIの内部処理は不可視であり、判決理由をどのように市民に説明するかが課題です。 ・前例主義の強化と硬直化 AIは過去の判例を学習するため、時代遅れの価値観を再生産しやすい。社会変化に柔軟に対応できないリスクがあります。 |
(4)実務上の課題:責任と上訴
誤判責任の整理
- 民事事件
現在の民事事件では、誤判があっても、原則は控訴・上告によって是正されます。国家賠償は通常は認められません。判例上も「裁判官の判断の当否は上訴制度で担保されるべきで、国家賠償の対象とはならない」とされています。 - 刑事事件
こちらも原則として控訴・上告によって是正されます。但し、無罪が確定したえん罪事件では、国家賠償や刑事補償法による補償が認められることがあります。 - AI裁判官の場合
AI裁判官の場合でも、原則は上訴による是正が基本ルートとなるでしょう。単なる誤判では直ちに違法とはされず、国家賠償の対象になるのは、AIシステムの設計や運用において人間による監督義務を欠いた場合や、透明性・説明可能性を欠いた運用が「著しい違法」と評価される場合に限られると考えられます。
(5)上訴制度の設計
AI判決に対して上訴できるのか、上訴審では必ず人間が担当するのか、一審AI判決をどの程度尊重するのか。責任の所在と不可分の課題として、制度設計が不可欠です
(6)導入へのハードル
現時点のAI技術では、定型的で争点が少ない事件への補助にとどまります。条文解釈や証拠の信用性判断、社会的価値観の調整など、高度な判断は依然として人間に依存します。ただし、技術進歩と社会的合意次第では、部分的な自動判決が現実となる可能性も否定できません。
(7)本章のまとめ
| AI裁判官の役割 | 証拠解析の効率化、商事紛争支援、量刑の一貫性確保、軽微事件処理の拡大 |
| 法的課題 | 憲法との関係、前例主義の硬直化 |
| 実務課題 | 誤判責任の所在(民事・刑事・AIの整理)、上訴制度の設計 |
→ 当面は「支援機能」が中心ですが、技術進歩と社会合意により、将来的には軽微事件や専門分野で「部分的自動判決」が導入される可能性があります。
4. 共通課題 ― 説明可能性・公平性
(1)説明責任:「理由を教えて」に答えられるか
AIは「ブラックボックス」問題を抱えています。なぜその判断に至ったのかを人間が理解できないケースが多いのです。司法・警察分野では特に深刻で、当事者が異議申立や上訴で争えるレベルの理由が求められます。
AIを法の場で使うには、少なくとも次の3条件が必要です。
- 読める(可監査性):どのデータをどの設定で使ったかログで追えること
- 再現できる(再現性):同じデータと設定なら同じ結果が得られること
- やり直せる(反事実説明):どの要素を変えれば結論がどう変わるかを示せること
(2)説明可能性の具体例
例えば、保釈許可判断でAIが「逃亡リスク高」と判定した場合、
- 使用した前科・住所・職業などのデータが開示され、
- 同条件で再計算可能であり、
- 「もし定職があれば結論は変わったか」を示せる必要があります。
(3)偏り(Bias)の問題:無意識の差別の増幅
AIは過去のデータから学習しますが、そのデータ自体に差別や偏見が含まれています。
- データ由来の偏り
犯罪統計を学習したAIが、特定地域や属性を過剰に「要注意」と判定する。 - 設計由来の偏り
安全性を重視しすぎるあまり、プライバシーや少数派の権利を犠牲にする設計になる。
(4)日本の法制度との関係
日本には包括的な差別禁止法が存在しないため、AIによる差別的取扱いへの対応が困難です。障害者差別解消法のような個別法はありますが、AI利用を前提とした規定はありません。この点で、日本は欧州や米国より制度的に脆弱といえます。
(5)国際的な取り組み事例
| 中国 | 司法分野では「智慧法院(スマート裁判所)」でAIによる判決支援等を実用化。警察分野では北京市や深圳市で街頭カメラと顔認証AIを組み合わせた監視システムを運用中。「社会信用システム」との連携も進むが、過剰監視への国際的な批判も強い。 |
| EU | 2024年にAI規制法(AI Act)を制定。警察・司法分野でのAI利用を「高リスク」に分類し、2026年以降厳格な規制を適用予定。公共空間でのリアルタイム顔認証は原則禁止(重大犯罪捜査等は例外)、予測的警察活動には透明性確保と人権影響評価を義務付け。 |
| 米国 | 再犯リスク評価AI「COMPAS」の人種バイアス問題を経て、州レベルでAI規制が進行中。連邦レベルでは包括的規制はまだない。 |
| 日本 | AI利用ガイドラインの策定段階。司法・警察分野の具体的規制は未整備で、包括的な差別禁止法もないため、AIによる差別的取扱いへの対応が課題。 |
(6)憲法秩序との整合性:民主的統制の確保
- 民主的正当性
警察は行政権の一部であり、市民の合意があれば導入可能です。
司法は第3章にも記載したとおり、憲法上「裁判所と裁判官」に属するため、AI判決がこの枠組みとどう整合するかが根本課題です。当事者が事前に同意してAI判決を選択する仕組みであれば、一定の合憲性を確保できる余地もあります。 - 制度設計の課題
誰がAIの判断基準を決めるのか(技術者か、政治的プロセスか)、国会や議会による監督制度、人間による最終審査制度、定期的な民主的見直しが必要です。
(7)本章のまとめ
| 説明可能性 | 読める・再現できる・やり直せる仕組みが必須 |
| 公平性 | データや設計の偏りを監査・補正する制度が不可欠 |
| 憲法との整合性 | 裁判を受ける権利を保障しつつ、警察・司法に応じた民主的統制を設計することが不可欠 |
→ 技術論だけでなく、制度論・憲法論をクリアにすることがAI導入の前提となります。
5. 段階的導入のシナリオ
AI警察・AI裁判官の導入には多くの課題があります。しかし、技術の進歩と社会的ニーズを考えれば、完全に拒絶することは現実的ではありません。導入は段階的に進み、最終的には一部で完全自動化も視野に入ります。本章では、リスクを抑えつつ導入を進める現実的なシナリオを整理します。
| ①短期(3〜5年):補助ツールとしての活用 警察分野 映像解析による特定人物・車両検索、不審行動検出(最終判断は人間) 交通違反の自動検知(証拠整理までAI、処分判断は人間) 犯罪データ分析による効率的なパトロール提案 司法分野 判例検索や争点整理の自動化(調査業務効率化) 損害計算や定型契約書チェックの下書き作成 調停における複数の和解案提示 制度整備 AIシステムの品質基準と認証制度 AI支援の記録・監査体制 人間による最終判断を担保 ②中期(5〜10年):限定分野での半自動化 警察分野 軽微な交通違反(駐車違反、軽度の速度違反)の自動処理(異議申立があれば人間が再審査) 運転免許更新や許認可更新など、要件が明確な行政手続の自動化 司法分野 少額紛争(例:100万円以下)について、当事者合意があればAI判決(上訴権は保障) 養育費算定や財産分与など、基準が明確な家事調停 「AI調停」の導入 制度整備 半自動処理に関する特別法の制定 刑事の半自動化処理に対する異議申立は48時間以内に人間が再審査上訴制度の整備 AIの定期監査・補償制度の新設 ③長期(10〜30年):専門分野での部分的自動判決 警察分野 犯罪発生予測精度の高度化に基づく、警告や監視強化などの自動発動 組織犯罪や資金フロー解析による高度な捜査支援 司法分野 知的財産訴訟や税務訴訟など、定式化可能な専門分野での自動判決 刑事事件の量刑をAIが全国統一基準で提案し、裁判官が最終判断 実現の前提条件 憲法の解釈変更、または改正 AIの説明可能性の飛躍的向上 社会全体の信頼醸成 サイバーセキュリティの飛躍的向上(AIシステムへの攻撃・改ざん防止) 国民のデジタルリテラシー向上(AIの限界を理解した利用) 国際的な制度調和(条約や協定レベルでの調整、例えばAI判決が海外で執行できるか等) |
(1)共通して必要な制度設計
- 独立監査機関の設置(アルゴリズムや学習データを定期的に検証)
- 簡易で迅速な異議申立制度(人間が再審査)
- アルゴリズム検証制度(差別的・不当な基準の有無をチェック)
- 技術や社会情勢に応じた定期的な制度見直し(目安:3年ごと)
- データガバナンス(透明性確保とプライバシー保護)
- AIを監督できる法律家・裁判官・警察官の養成
(2)本章のまとめ
| 短期 | 補助ツールとして支援機能を導入 |
| 中期 | 限定分野で半自動化を進め、法制度を整備 |
| 長期 | 専門分野で部分的自動判決を導入(憲法・社会合意が前提) |
→ どの段階でも「人間による最終審査」と「異議申立制度」の保障が不可欠です。これにより、技術の恩恵を享受しつつ、人権と民主主義の価値を守ることができます。
6. 結論 ― AI時代の司法を考える
ここまで5章にわたり、AI警察・AI裁判官の可能性と課題を検討してきました。技術の発展により、かつてSFに描かれた未来は着実に現実へと近づいています。
(1)AI導入は不可避。しかし「公正・透明・説明可能性」が根幹
司法・警察分野からAIを完全に排除することは現実的ではありません。人員不足、業務効率化、判断の統一といった切実なニーズがある以上、AI活用の流れは止められないでしょう。
ただし、司法と警察は人々の生命・自由・財産を守る社会の根幹です。効率性のために正義や公平を犠牲にすることは許されません。
- 公正性の確保:特定の集団に不利益を与えないよう、継続的な監視と修正が必要
- 透明性の保障:「AIがそう判断した」だけでは説明にならない。根拠を理解可能な形で提示すべき
- 説明可能性の実現:法的に意味のある理由を提示できないAIシステムは司法・警察分野で使用すべきでない
(2)現実的な導入の姿勢
- まずは道具として:AIは高度な補助ツールから導入し、最終責任は常に人間が負う
- 段階的に拡大:限定分野で試行を重ね、問題点を検証しながら慎重に範囲を広げる
- 制度的保障:異議申立制度、監査機関、責任体制を各段階で整備することが不可欠
(3)民主的統制と市民の選択
AIによる権力行使は民主主義の根幹に関わります。
- 国民による選択
最終的に「AI警察の方が信頼できる」「AI裁判官の方が公平だ」と国民が判断すれば、その選択は尊重されるべきです。ただし、十分な情報と議論を経た上での選択であることが前提です。日本ではこの局面はまだ先でしょうが、海外が先行する可能性もあります。 - ディストピアか、公平社会か
行き着く先が監視社会や予測逮捕の世界――ジョージ・オーウェルの小説『1984』や映画『マイノリティ・リポート』に描かれたような社会――に進むのか。
それとも、AIが人間の偏見を補正し冤罪を減らし、紛争解決を迅速かつ公平にする社会に進むのか。未来の姿はいまだ定まっていません。後者を実現するには、制度設計と運用の不断の努力が不可欠です。 - 選択肢の保障
AIによる手続きが進んでも、人間による従来型の裁きを選べる権利は残されるべきです。 - 継続的な見直し
日本社会は新技術に慎重である一方、一度制度化されると修正が困難という特性があります。そのため初期段階での制度設計が特に重要です。また、制度は技術や社会情勢に応じて定期的に修正できる民主的プロセスを備える必要があります。 - 世代間ギャップの考慮
デジタルネイティブ世代はAI判決を受け入れやすく、高齢者は人間による判決を望むかもしれません。世代や立場による受け止め方の違いにも配慮が求められます。
7. 最後の問いかけ
冒頭で「あなたの交通違反を検知するのが人間ではなくAIだったら?」と問いかけました。最後に改めて問います。
「あなたはAIに裁かれたいと思いますか?」
公平で迅速なら構わないと考える人もいれば、やはり人間に裁かれたいと感じる人もいるでしょう。現在は多くの人が後者だと思いますが、重要なのは、この選択を私たち自身が持ち続けることです。気づかぬうちに選択肢がなくなっていた、という事態は避けなければなりません。
AI技術は確実に社会を変えます。しかし、その方向を決めるのは技術者や企業ではなく、私たち市民一人ひとりの判断です。司法と治安という社会の根幹に関わる分野だからこそ、慎重に、しかし前向きに、AIとの向き合い方を考える必要があります。
参考文献・関連情報
- 個人情報保護委員会(2024年3月)『AI利用に関するガイドライン(2024年改訂)』
- 法務省(2022年12月)『民事訴訟法IT化検討会報告書』
- European Union(2024)Artificial Intelligence Act(2026年以降段階適用)
- 朝日新聞デジタル(2025年7月24日)「『Grok、これってホント?』—生成AIで事実確認、潜むリスクは」
- NHKニュース特集(2023年5月)「AI裁判官は本当に“無罪”を言い渡せるか」
1. はじめに:クリプトトレジャリー戦略とは何か
クリプトトレジャリー戦略とは、企業が自社の財務戦略として暗号資産を保有・運用することです。従来の現金や有価証券に代わる、またはそれらを補完する資産として、企業の資産ポートフォリオに暗号資産を組み込みます。
ビットコインのみに特化する場合は「ビットコイントレジャリー戦略」と呼ばれることもありますが、本稿では暗号資産全般を対象とした「クリプトトレジャリー戦略」として統一します。なお、海外では近時「Digital Asset Treasury(DAT)」と呼ばれることも増えています。
近年、この戦略を採用する企業が世界的に増加しています。特に2024年の米国における暗号資産ETF承認は、機関投資家の参入を促し、企業による直接保有戦略への関心も高まりました。日本でも上場企業による暗号資産保有の事例が現れ、投資家の注目を集めています。
本稿では、クリプトトレジャリー戦略の概要と日本法上の論点を整理します。
2. まとめ
| 結論:現行日本法下でも実行可能 クリプトトレジャリー戦略は、適切な対応により現行の日本法制度下でも実行可能です。主要論点の結論は以下の通りです。 法的論点 ・暗号資産交換業: 自社保有分の売買は登録不要 ・集団投資スキーム: 株式・CB発行による資金調達は該当しない ・ステーキング・レンディング: 自己勘定での運用は規制なし ・適時開示: 重要な取引・方針変更時の開示が必要 会計・税務 ・会計: 時価評価が原則(日本基準・IFRS・US GAAPで差異あり) ・税務: 期末時価評価による課税が原則、但し、2024年改正により一定要件下で期末時価評価課税の適用除外が可能 ・監査: 監査法人との事前合意が重要 実務上の準備事項 ・取締役会レベルでの投資方針決定 ・監査法人・税理士との事前協議 ・内部統制・リスク管理体制の構築 ・投資家向けの情報開示体制整備 投資家視点 ・株式としての税務優遇(20.315% vs 暗号資産現物最高55%)や投資手続きの簡便性等のメリット ・法人レベルと個人レベルの二重課税 ・事業リスク、運用リスクのデメリット ・暗号資産ETFとは異なる価値(レバレッジ効果、企業価値とのシナジー等) |
以下、各論点の詳細を解説します。
3. クリプトトレジャリー戦略の導入事例、考えられる戦略
3.1 導入事例
(1) 世界的な先駆者:マイクロストラテジー
米国のマイクロストラテジー社(現ストラテジー社)は、クリプトトレジャリー戦略の代表的な成功例として知られています。2020年からビットコインの大量購入を開始し、企業価値の大幅な向上を実現しました。
(2) 日本の先駆者:メタプラネット
2024年、日本の上場企業である株式会社メタプラネットが本格的なクリプトトレジャリー戦略を発表しました。これは日本初の本格的な事例として大きな注目を集めました。
(3) 他の日本企業の例:リミックスポイント
株式会社リミックスポイントも、事業との関連性を重視しながら暗号資産保有を行っている企業の一つです。同社の子会社であった株式会社ビットポイントジャパンは暗号資産取引所ビットポイントを保有しており(但し、2022年から2023年にかけてグループ外に同社の株式譲渡)、Web3と親和的な会社です。
主要企業のクリプトトレジャリー戦略比較
| 企業名 | 国 | 戦略の特徴 | 保有資産 | 株価パフォーマンス |
| マイクロストラテジー | 米国 | 現金の大部分をBTCに転換 「企業版のBTC ETF」 |
大量のBTC | 1年:164%上昇 5年:2,238%上昇 時価総額USD940億 |
| メタプラネット | 日本 | 「財務準備資産」として位置づけな購入実施 | 大量のBTC | 1年:490%上昇 5年:707%上昇 時価総額4,612億円 |
| リミックスポイント | 日本 | 事業シナジーを重視 | BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE等 | 1年:120%上昇 5年:274%上昇 時価総額515億円 |
*株価は2025年9月9日付の調査
3.2 クリプトトレジャリーの戦略例
「クリプトトレジャリー戦略」といえば、マイクロストラテジー社やメタプラネット社のような「全資産暗号資産転換型」を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし実際の企業戦略は多岐にわたります。
企業は以下の4つの観点から、自社に適した戦略を選択する必要があります。
(1)保有方針による分類
| 戦略タイプ | 特徴 | 主なメリット | 主な留意点 |
| 余剰資金投資型 | 既存の余剰現金の一部を暗号資産に配分 | ・既存事業への影響最小限 ・段階的な導入が容易 |
・投資規模が限定的 ・株価への影響も限定的 |
| 完全移行型 | 現金資産の大部分を暗号資産に転換 | ・価格上昇の恩恵を最大化 ・「ビットコイン銘柄」として明確なポジション |
・価格下落リスクが大きい ・運転資金への影響 ・ETF導入時のリスク |
|
Web3戦略型 |
Web3・ブロックチェーン事業との関連性を重視 | ・事業戦略との整合性 ・投資家への説明がしやすい |
・事業の実現可能性 ・継続的な事業投資が必要 ・Web3領域における専門知識が不可欠 |
(2)資金調達方法
| 調達方法 | 特徴 | メリット | 留意点 |
| 余剰資金活用型 | 既存の現金、預金を原資として購入 | ・追加調達不要 ・希薄化影響なし ・迅速に実行可能 |
・投資規模に限界 ・既存事業資金への影響要検討 |
| 新株発行型 | 新株発行により資金調達して購入 | ・大規模投資が可能 ・負債増加を回避 ・成長投資アピール |
・株式の希薄化 ・株主総会の承認が必要な場合あり ・市場環境に左右 |
| 転換社債発行型 | CB発行により資金調達して購入 | ・低金利での調達 ・転換時まで希薄化抑制 ・レバレッジ効果 |
・金利負担発生 ・転換条件の設定 ・信用格付けへの影響 |
(3)投資対象による分類
| 投資対象 | 特徴 | メリット | リスク・留意点 |
| ビットコイン専用 | BTC単一銘柄への集中投資 | ・最も流動性が高く安定 ・「デジタル・ゴールド」 ・投資家説明が容易 |
・単一銘柄集中リスク ・分散効果なし ・他通貨成長機会の逸失 |
| 銘柄分散型 | BTC、ETH、アルトコイン等への分散投資 | ・適度な分散効果 ・ステーキング収益も獲得 ・市場全体成長を取込み |
・個別銘柄リスクは存在 ・管理の複雑化 ・税務計算の煩雑化 |
| アルトコイン重視型 | 新興、小型コインへの積極投資 | ・高成長の可能性 ・先行者利益の獲得 ・イノベーション領域投資 |
・極めて高いボラティリティ ・流動性リスク高 ・投資家理解の困難性 |
(4)運用方法による分類
| 運用方法 | 特徴 | メリット | リスク・留意点 |
| HODL(長期保有) | 暗号資産を長期保有し続ける | ・単純な運用方法 ・価格変動に左右されない ・税制優遇の可能性(→5章参照) |
・価格下落時の損失拡大 ・機会損失の可能性 ・流動性の確保 |
| ステーキング活用 | ETH等をステーキングして追加収益獲得 | ・継続的収益 ・年利数%の追加リターン ・ネットワーク貢献 |
・技術的リスク ・スラッシングリスク ・アンボンディング期間 |
| レンディング活用 | 第三者への貸出で利息収入獲得 | ・高い利率での運用 ・価格上昇と利息の両獲得 ・流動性調整可能 |
・貸出先の信用リスク ・市場流動性リスク ・規制変更リスク |
企業はこれらの要素を組み合わせて、自社の事業内容、財務状況、リスク許容度に応じた最適な戦略を構築することになります。
なお、当職らがアドバイザーや関係者と話す限り、現在検討中の会社の場合、先行事例との差異を設けるためか、単なるHODLではなく、本業との繋がりをも生かしたトレジャリー戦略を模索する企業が多いようにも思われます。他方、必ずしも本業とWeb3との関係が強くない企業がクリプトトレジャリー戦略を採用する場合でも、ステーキングやレンディングによるストック収入を組み合わせる収益モデルとして株主等のステークホルダーに説明を行おうとする例もあるようです。
4. 日本法上の論点
クリプトトレジャリー戦略を日本で実施する際の主要な法的論点を整理します。結論として、適切な対応により現行法下でも戦略実施は十分可能です。
4.1 暗号資産交換業登録(結論:登録不要)
基本原則 企業が自社の財務戦略として暗号資産を取得・保有する行為は、資金決済法上の「暗号資産交換業」に該当せず、登録は不要です。
法的根拠 資金決済法第2条第15項によれば、暗号資産交換業とは以下の行為を「業として」行うことです:
- 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
- 上記行為の媒介、取次ぎ又は代理
- 利用者の金銭の管理
- 他人のために暗号資産の管理をすること
該当しない理由 企業による自社ポートフォリオ投資としての暗号資産売買は「業として」行う行為に該当しないと解釈されています20。また、自社保有は「他人のための管理」ではありません。
株式等による資金調達について
株式や転換社債等による資金調達を行い、その資金で暗号資産を購入する行為についても、現時点では暗号資産交換業には該当しないと整理されています。形式的には「株主から資金を集め暗号資産を取得する」ため、実質的に株主に対して暗号資産売買サービスを提供していると評価し得る余地はありますが、現行実務においてはそのような解釈は採用されていません。
4.2 集団投資スキーム規制(結論:該当しない)
基本的な考え方 企業が新株発行や転換社債発行で調達した資金による暗号資産投資は、金商法第2条第2項第5号の「集団投資スキーム」に該当しません。
法的根拠 金商法の条文構造上、株式や転換社債は第2条第1項第5号や第9号で独立した「有価証券」として規制されており、第2項第5号の集団投資スキーム(ファンド規制)とは別体系です。
具体的理由
- 株式:企業全体に対する持分権(特定事業への出資権利ではない)
- 転換社債:元本償還請求権が基本(運用成果配当が目的ではない)
留意すべきケース 暗号資産投資専用の別会社(SPC等)を設立して匿名組合出資等を募る場合は、集団投資スキーム該当性の慎重な検討が必要です。
4.3 ステーキング・レンディング(結論:自己勘定なら規制なし)
ステーキングについて 企業が自己保有資産、自己勘定で行うステーキングは、通常、ファンド(集団投資スキーム)や暗号資産カストディには該当せず、特段の規制なく実施可能です。
レンディングについて 日本では金銭貸付は貸金業法で規制されますが、暗号資産レンディングに特段の規制はありません。自己保有の暗号資産をレンディングで運用することは、自己勘定であれば自由です。
4.4 投資顧問業との関係(結論:現物は対象外)
現物暗号資産への助言 現物暗号資産は金商法上の「有価証券」ではないため、投資助言・代理業(金商法第28条第3項)の対象外です。一般的なコンサルティングサービスとして整理できます。
注意が必要なケース 暗号資産デリバティブ(先物、パーペチュアル等)への継続的・具体的助言や裁量運用は、投資助言・代理業の登録が必要となる場合があります。
実務的対応 外部アドバイザーとしてデリバティブを含む助言を行う場合は、契約目的を「戦略設計・リスク分析支援」に限定し、具体的な投資判断の助言は避けることが推奨されます。
4.5 上場ルールと適時開示(結論:制限なし、開示必要、資金調達の方法に留意)
上場ルール 東証の上場ルールにおいて、暗号資産保有を直接禁止する規定はありません。適法な投資行為として、他の投資商品と同様の扱いを受けると考えられます。
適時開示が必要なケース
- 企業規模に比して重要な金額の暗号資産取得・売却
- 新たな暗号資産投資開始時の投資方針決定
- 投資方針の大幅変更
- 業績予想に重大な影響を与える評価損益
開示内容のポイント 暗号資産への投資が大規模な場合、以下の内容を含める必要があると考えられます:
- 投資目的・方針の明確化
- リスクの適切な説明(価格変動、流動性、技術、規制変更)
- 感応度分析(価格変動による業績への影響試算)
- 四半期ごとの運用状況報告体制
企業は適切な法務体制を構築し、コンプライアンスを確保しながら戦略を実行することが重要です。
資金調達 クリプトトレジャリー会社の中には大規模な資金調達を行う会社があります。この場合、東証の300%ルール(株式価値の希薄化率が300%を超える第三者割当の場合、「株主および投資家の利害を侵害するおそれが少ないと取引所が認める場合を除き、上場廃止とする」とするルール、東証有価証券上場規程第601条第1項第15号、施行規則第601条第12項第6号)に配慮する必要があります21。
また、25%ルールと呼ばれる規定(上場規程第432条、施行規則第435条の2)にも留意が必要です。これは、第三者割当増資によって発行済株式総数の25%を超える株式が新たに発行される場合、株主総会の特別決議又は独立した第三者による必要性・相当性の意見の取得を必要とするものです。投資家の持分比率が大きく変動するため、少数株主保護の観点から厳格な手続きが要求されています。
5. 会計・税務
クリプトトレジャリー戦略実施時の会計・税務対応は極めて重要です。特に上場企業は、投資家・監査法人への説明責任を果たしつつ、税務リスクを適切に管理する必要があります。
5.1 会計処理(日本基準・IFRS・US GAAP)
日本基準(JGAAP) 実務対応報告第38号により、活発な市場が存在する暗号資産は期末に市場価格で評価し、評価差額を損益に計上します。活発な市場がない場合は取得原価評価となります。
貸借対照表の表示区分は保有目的と流動性で判断されます。独立掲記する場合には「暗号資産」等として表示しますが、重要性が乏しい場合には無形固定資産やその他資産等に含めて表示します。損益計算書上の区分は事業の目的や実態に応じて判断されます。いずれも監査法人との協議と合意が求められます。
IFRS採用企業 多くの場合IAS38の無形資産でコストモデル+減損(IAS36)が採用されますが、活発な市場がある場合は再評価モデルも選択可能です。この場合、上方再評価は、OCI(その他包括利益)に計上(過去の減損の戻入に相当する部分は損益)されるため、原則として損益計算書に計上されません。
ただし日本の法人税は期末時価評価で算定されるため、IFRS採用でも税務申告上の調整が必要となり、会計と税務の乖離が生じます。
US GAAP採用企業 マイクロストラテジー等の米国企業は、ASU 2023-08を適用し、取得原価で計上後、期末ごとに公正価値へ時価評価し、評価差額を損益に計上します。IFRSと異なり、OCI(その他包括利益)ではなく常にP/L通過することになります。
5.2 法人税の取扱い
期末時価評価による課税(原則) 国税庁Q&Aによれば、「活発な市場が存在する暗号資産」は期末に時価評価し、評価差額を益金又は損金に算入します。
以下の場合でも評価対象となります:
- DEX上場で要件を満たす場合
- ステーキングでロック中
- 相対レンディング中
移転制限による期末時価評価課税回避(例外) 2024年4月改正により、一定要件を満たせば期末時価評価課税の適用除外が可能になりました。
要件:
- 暗号資産交換業者を通じた移転制限の付与
- JVCEAへの情報届出・公表
- 短期売買目的以外での継続保有
効果: 税務上は取得原価で評価継続でき、売却時に初めて課税されます。未実現益課税が回避でき、キャッシュフロー安定化に寄与します。
留意点:
- 会計上は引き続き時価評価が必要(会計と税務の乖離)
- 移転制限中はレンディング等に制約
- 財務戦略との整合性の検討が必要
ETFとの税務構造比較 なお、ETFはパススルー課税により二重課税が避けられる一方、企業の暗号資産投資では法人段階での課税後、株主が配当・売却益で再度課税される二重課税構造となります。この点は6章で詳述するETFとの重要な相違点の一つです。
5.3 監査・内部統制
監査法人との事前合意が重要 暗号資産監査の最重要論点は「実在性」確認です。監査によって財務数値の事後的・第三者的検証が可能と判断されるためには、業務やシステムの設計に影響します。監査法人と密な協議を行い監査可能であることの事前の合意が求められます。実務的な監査論点の一例は以下の通りです:
- 秘密鍵管理体制の整備(マルチシグ、権限分離と相互牽制、災害対策等)
- ウォレットアドレスの証憑管理方法
- ブロックチェーン取引履歴との照合手続き(使用するツールの信頼性含む)
- 第三者による残高確認手続き(暗号資産交換所に預託する場合、混合寄託によって保管している取引所の残高確認を取得する、交換所側で個別管理の仕組みを設けて残高確認を可能にする等)
- 外部委託先の内部統制評価(SOCレポートの取得可能性含む)
- 期末における市場価格の信頼性(使用する取引所・価格の定義)
内部統制の整備 監査の前提としても重要視されるのが内部統制であり、暗号資産特有のリスクを識別し業務上適切な対応がとられる必要があります。内部統制は、社内規程で適切な粒度でルール化した上で、業務フローや業務記述書等を使って具体的に文書化される必要があります。外部の信頼できる保管・記録機関が整備されている従来の金融資産とは異なり、自ら厳格な管理体制を構築することが求められます:
- 取締役会レベルでの投資方針承認(リスクリミットや価格急変時対応等を含む)
- 複数人チェック体制での取引実行
- 定期的な残高確認と帳簿照合
- 秘密鍵の安全保管と災害時復旧手順(カストディアンを利用する場合、保管先の内部統制評価も必要)
暗号資産に精通した会計士・税理士との連携体制を構築し、定期的な相談・確認を行うことが重要です。
6. ETFとの比較と企業の市場ポジション
日本では暗号資産ETFは未承認ですが、将来承認された場合の企業戦略や市場ポジションへの影響を整理します。
6.1 米国における状況
2024年1月に米国でビットコインETFが承認されましたが、既存のクリプトトレジャリー企業の株価は引き続きプレミアムを維持しており、両者が投資家や市場に異なる価値を提供していると考えられています。
6.2 構造的な相違点
| 項目 | ETF | クリプトトレジャリー会社 |
| レバレッジ | 基本は現物保有のみ | 転換社債・新株発行等でレバレッジ可能 |
| 運用戦略 | 指数連動のパッシブ運用 | 銘柄配分調整、ステーキング等の裁量あり |
| 付加価値 |
価格トラッキング、低コスト | 本業収益、Web3事業とのシナジー |
| 税務構造 | パススルー課税(投資家側でのみ課税) | 法人税+投資家課税(二重課税構造) |
6.3 企業の市場ポジショニング戦略
現状の日本市場 ETF不在のため、クリプトトレジャリー会社が「事実上のETF代替」として機能し、この特殊な市場環境が株価プレミアムの一因となっています。
ETF導入後の予想される影響 メタプラネット社は公式見解として「ETFは競合ではなく需要拡大要因」との立場を示し、「ETFがパッシブ連動する一方、トレジャリー会社は資本市場活用により1株当たりビットコイン保有量を増加させる戦略が可能」と説明しています。(参考:メタプラネット社FAQ https://metaplanet.jp/jp/shareholders/faqs)
米国ではETF導入後もプレミアムが維持されていますが、実際の日本での市場反応は投資家構造や市場環境に左右されるため、米国と同様の結果となるかは不透明です。
企業の対応戦略
- レバレッジ効果の強調(ETFでは実現困難な上振れ可能性)
- 事業シナジーの明確化(Web3戦略との連携等)
- 資本効率性の訴求(1株当たり暗号資産保有量の増大等)
【コラム:投資家にとってのクリプトトレジャリー会社投資のメリット】 |
| 個人投資家がクリプトトレジャリー会社に投資することで得られる主なメリット、デメリットを参考情報として整理します。 税務上の優遇(個人投資家) ・株式投資として20.315%の申告分離課税が適用 ・暗号資産の直接取引(総合課税、最高55%)と比較して大幅な低税率 ・源泉徴収ありの特定口座での簡便な税務処理 投資手続きの簡便性 ・暗号資産取引所への口座開設・本人確認手続き不要 ・既存の証券口座から投資可能 ・NISA対象となる可能性 制度的制約の回避 ・暗号資産直接投資が制限されている機関投資家・年金基金等も投資可能 ・社内規定で暗号資産投資が禁止されている企業の従業員も参加可能 主なデメリット・留意点 ・二重課税構造: 法人レベルでの課税後、配当・売却益で個人レベルでも課税 ・複合的リスク: 暗号資産価格変動リスクに加え、企業固有の事業リスクも存在 ・プレミアムリスク: 株価に含まれるプレミアムが正当化されるか不透明 ・ETF導入の影響: 将来のETF承認による影響が不透明 このため、クリプトトレジャリー企業は「事実上の暗号資産ETF」として一定の投資家需要を得やすい環境にある一方、投資判断には慎重な検討が必要です |
7. 結語
クリプトトレジャリー戦略は、ETFとは異なるレバレッジ効果や企業価値とのシナジーを持ち、独自の投資対象としての地位を確立しつつあります。現行の日本法制度下において適切な対応により実行可能な財務戦略です。
法的論点については暗号資産交換業登録は不要であり、集団投資スキームにも該当せず、ステーキング・レンディングも自己勘定であれば規制はありません。
会計・税務面では時価評価による業績への直接的影響や期末時価評価課税といった特有の論点があるものの、2024年税制改正による移転制限制度の活用等により一定の対応が可能です。
ただし、日本企業がクリプトトレジャリー戦略を持続的に実行するためには、法的クリアランスの確認だけでは不十分です。会計・税務・IR体制を包括的に整備し、監査法人との事前合意、適切なリスク管理体制の構築、投資家への継続的な情報開示等を通じて、ステークホルダーからの理解と信頼を得ることが成功の鍵となります。
企業による暗号資産への関与は今後も拡大が見込まれる中、本稿が戦略検討の一助となれば幸いです。
謝辞
本Blogについては、Animoca Brands株式会社天羽健介氏、公認会計士柚⽊庸輔氏、齊藤洸氏よりご助言をいただきました。但し、ありうべき誤りは全て筆者らに帰します。
留保事項
・本書の内容は関係当局の確認を経たものではなく、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。また、筆者の現状の考えに過ぎず、筆者の考えにも変更がありえます。
・本稿は、クリプトトレジャリー戦略の利用やクリプトトレジャリー戦略企業への投資を推奨するものではありません。
・本書はBlog用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律、会計、税務等のアドバイスが必要な場合には各人の弁護士、会計士、税理士にご相談下さい。
1. はじめに
先日、大阪・関西万博の「空飛ぶクルマステーション」を訪問し、空飛ぶクルマに関する展示を体験してきました。 (参考:https://www.expo2025.or.jp/future-index/smart-mobility/advanced-air-mobility/)
図1 現実風の空飛ぶクルマ

同パビリオンは予約なしでも入場可能ですが、事前予約をすると停機中の空飛ぶクルマの実機に乗り込めるほか、タクシーのように夢洲から高野山や淡路島に飛行する映像体験ができます。また、一定日の朝には実機の飛行デモンストレーションも会場の別場所であります(筆者が訪問した際にはデモ飛行のほかSkydrive社社長による機体説明とQ&Aセッションも行われていました)。
空飛ぶクルマに対しては、開催前から「現実味がない」「税金の無駄」「これは車ではない」など否定的な声も多くありましたが、展示内容は非常にわかりやすく、未来社会の具体的なイメージを持たせてくれるものでした。少なくとも、「夢ではない、近未来の現実かもしれない」と感じさせられる体験でした。
もっとも、展示内では「空には渋滞がない」というキャッチコピーが用いられていましたが、実際にはそう単純ではありません。航空法や小型無人機等飛行禁止法では、人口密集地(DID地区)、空港周辺、重要施設付近など、多くの空域が原則飛行禁止または厳しく制限されています。したがって、現行制度上「自由に飛ばせる空域」は極めて限定的であり、むしろ“使える空”のほうが少ないのが実情です。さらに、空域には航空交通管制が存在し、民間機・ヘリ・eVTOL・ドローンが安全に飛行するためには管制官による交通整理が不可欠です。実際、羽田空港上空ではピーク時に「ホールド(旋回待機)」が頻繁に発生しており、空の交通にも物理的・制度的な限界があります。今後、都市内低高度の運航には、専用ルートや無人航空機交通管理システム(UTM)の整備が不可欠となるでしょう。
技術は現実味を帯びる一方、空飛ぶクルマを本当に実現させるためには、航空法上の耐空証明や運航者責任、都市部でのバーティポート設置基準など、多方面で制度的な課題があります。
国土交通省は近年、2023年の航空法施行規則改正やバーティポート整備指針、さらに2025年の次世代空モビリティ運航ガイドラインの公表など、政省令や技術基準の逐次改正を進めています。
もっとも、現状ではまだ抜本的な制度設計には至っておらず、多くの領域で法的な未確定・グレーゾーンが残されています。
本稿では、空飛ぶクルマに関し、皆さんが思い描く未来の姿やSF作品、それと現行法の対比を通じて整理・考察します。
| ※本記事は大阪万博での展示を契機に、法律家として未来の制度を考察するシリーズの一環です。 過去記事: 「アンドロイドになった『私』は同一人物か?」 「軌道エレベーターで殺人事件が起きたら誰が裁く?」 |
2. SF作品に見る空飛ぶクルマの世界
空飛ぶクルマは、SF作品の中では昔からおなじみの存在です。ただし、その登場のされ方は一様ではなく、作品ごとに異なる社会像と技術観が描かれています。
個人の自由な移動手段:「バック・トゥ・ザ・フューチャー」
1985年の『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART II』では、2015年の未来でデロリアンが空を飛ぶシーンが印象的です。ここでは空飛ぶ車は個人の乗り物として描かれ、誰もが自由に空を移動できる理想的な未来像が示されています。
権力の象徴としての空飛ぶクルマ:「ブレードランナー」
1982年公開の『ブレードランナー』では、空飛ぶクルマは警察専用車両として描かれ、高層ビルの間を縫って飛ぶシーンが印象的です。ここでの空は公共空間ではなく、権力が支配する領域として機能しています。
大衆化された空の渋滞:「フィフス・エレメント」
1997年の『フィフス・エレメント』では、空飛ぶクルマが完全に民間に普及しており、都市の空間に立体的な交通システムが存在しています。空中には信号機すら存在し、「空中渋滞」が日常の一部となっている世界です。
都市監視インフラとしての空:「攻殻機動隊」
1995年劇場版公開の『攻殻機動隊』では、公安9課の移動手段としてヘリ型のホバーカーが登場します。空飛ぶクルマは単なる移動手段ではなく、都市監視インフラの一部として位置づけられています。
図2 SF風の空飛ぶクルマ

法制度の不在という共通点
興味深いのは、これらの作品に共通して「空を誰が管理するのか」「どのような法的ルールで飛行が制御されているのか」といった論点がほとんど描かれていない点です。
SF作品が描く「自由な空の移動」は魅力的ですが、現実には空域管理や航空法制が厳格に存在します。むしろ「空は誰のものか」という問いこそ、現代社会における制度設計の最前線にある論点です。
3. 空飛ぶクルマとは何か?
「空飛ぶクルマ」という言葉は耳目を引きますが、現在開発されている機体は、SFで想像されるような形――たとえば『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART II』に登場するデロリアン――ではありません。車輪もなく道路も走りませんが、「誰もがオンデマンドに予約して使う日常移動サービス」を目指しているため、親しみやすい「クルマ」という呼び方が使われています。
何を空飛ぶクルマと呼ぶかは確定はしてはいませんが、国土交通省の資料では、空飛ぶクルマは「電動化・自動化された垂直離着陸機(eVTOL)」として定義されることが多く、次のような特徴が挙げられます。
- 電動推進(Electric):排ガスを出さないバッテリー型またはハイブリッド型の電動推進機構
- 自動化(Autonomous):将来的には自動運転が可能(ただし現時点では有人操縦が前提)
- 垂直離着陸(VTOL):滑走路を必要とせず、限られたスペースで発着可能
- 都市近接用途(Urban Air Mobility):都市内・近郊での移動を想定した短距離移動手段
このような特徴から、空飛ぶクルマは従来のヘリコプターやドローンとは異なる位置づけを持ちます。
類似技術との比較
| 分類 | 推進方式 | 操縦 | 離着陸方法 | 主な用途 | 法制度 |
| 空飛ぶクルマ(eVTOL) | 電動 | 将来自動化 | 垂直離着陸 | 都市内移動・空中タクシー | 航空法適用も制度設計途上 |
| ヘリコプター | 内燃機関 | 有人操縦 | 垂直離着陸 | 官庁・報道・救急 | 航空法で規制 |
| ドローン | 電動 | 無人(遠隔) | 垂直離着陸 | 撮影・物流・測量 | 無人航空機規制 |
空飛ぶクルマは、ドローンのように小型・軽量で垂直離着陸が可能でありながら、ヘリのように人を運ぶ能力を持つ乗り物であり、その意味で従来の区分では捉えきれない「ハイブリッドな存在」と言えます。
法制度から見た定義の曖昧さ
技術的にはeVTOL(electric Vertical Take-Off and Landing aircraft)という言葉が使われることもありますが、日本の航空法には現時点で「空飛ぶクルマ」や「eVTOL」という定義規定は存在しません。
また、「クルマ」という言葉が使われていますが車ではないことから、道路運送車両法の対象外であり、自動車免許や車検制度も及びません。逆に、飛行機やヘリコプターと異なるため、従来の航空法の枠組みにも完全には収まりません。
4. 現在の技術開発状況
空飛ぶクルマというと、まだ未来の乗り物という印象が強いかもしれません。しかし、技術的にはすでに実現段階にあり、国内外の企業が実機の開発・試験飛行・プレ商用運航に踏み出しているのが現状です。
海外:eVTOL市場の加速
アメリカや欧州では、eVTOL(電動垂直離着陸機)をベースとした都市型航空モビリティ(UAM:Urban Air Mobility)の実用化に向けた動きが加速しています。
- Joby Aviation(米):カリフォルニアを拠点とし、NASAとの協力で実証飛行を行い、FAA(米連邦航空局)の型式認証取得を目指しています。
- Volocopter(独):ドイツのスタートアップで、EASAからの型式証明取得に向けて最終調整段階にあり、2025年の商用運航開始を目指しています。
- Archer Aviation(米):United Airlinesと提携し、都市間の空中移動ネットワーク構築を構想。
日本:万博を契機とした実用化への取組み
日本においても、大阪・関西万博を契機として、空飛ぶクルマの商用化に向けた取組みが進んでいます。
- SkyDrive社(日本):愛知県豊田市発のスタートアップで、既にデモ飛行済。万博では機体展示と有償運航を計画。
- ANA・JALなど航空会社:空飛ぶクルマの導入に関心を示しており、空港との接続モビリティとしての活用が模索されています。
- 国交省「空の移動革命に向けたロードマップ」(2023年改訂):2025年に特定空域での限定運航開始、2030年代に一般商用化という工程が示されています。
技術より先に問われる「制度設計」
空飛ぶクルマの最大の障壁は、技術ではなく制度です。空中を飛ぶ機体である以上、航空法や航空機製造基準、安全認証、運行管理、操縦資格、離発着場の設置基準など、あらゆる法的インフラが必要になります。
5. 法制度の空白と課題
航空法は固定翼・回転翼を含む従来航空を包摂しますが、都市低空で高頻度運航を行うeVTOLや自動/遠隔操縦を前提とする制度設計は未整備で、ここに空白が残ります。
航空法の想定外――「タクシーのようなクルマ」という矛盾
日本の空を規律する中心的な法律は航空法です。しかし、航空法は本来、滑走路から離陸し高高度を飛行する固定翼機や、限定的な用途のヘリコプターを想定した制度設計となっており、空飛ぶクルマ(eVTOL)のような低空・短距離・多頻度の飛行体には制度的ミスマッチがあります。
現時点では、空飛ぶクルマは航空法上「航空機」に分類されており、国土交通省の許可が必要ですが、次のような点で制度対応がまだ追いついていません。
- 垂直離着陸に適した発着場(バーティポート:空飛ぶクルマ専用の離着陸場)に関しては、2023年12月に暫定的な整備指針が公表されていますが、本格的な法的基準は未制定です。
- 低高度空域における空域運用ルール(共有や優先順位等)は未整備であり、今後の整備が求められています。
- 自動運転や遠隔操縦を前提とした操縦資格制度も未整備であり、新たな資格体系の構築が必要です。
ドローンとの決定的違い
「空を飛ぶ=ドローンと同じように規制されるのでは?」という疑問もあります。
ドローンも登録、リモートID、許可・承認など厳格な管理下にあります。ただし制度設計の焦点は”無人で物を運ぶ”ことにあり、”有人で人を運ぶ”空飛ぶクルマでは型式/耐空、乗員資格、空域容量管理の要求水準と範囲が本質的に異なるのです。
6. 自己と責任――誰が償うのか?
空飛ぶクルマの開発において、避けて通れない論点が「事故が起きたら誰の責任か?」という問題です。これは責任の所在、免許制度、保険制度など法制度全体の構築に直結する中核論点です。
自動運転になれば責任は誰に?
現在開発されているeVTOL機の多くは、将来的に自動操縦・遠隔操縦を視野に入れていますが、初期段階では基本的に「有人操縦」が前提とされています。
仮に将来的に空飛ぶクルマが自動運転化された場合、選択肢として考えられる責任主体は以下の通りです:
- 機体の製造者(製造物責任法・PL法の適用)
- 自動運転システムの開発者(ソフトウェアの欠陥責任)
- 運航管理者(遠隔管制センターなど)
- 機体所有者(自動車でいう所有者責任)
- 搭乗者本人(人間が最終承認して乗った場合)
たとえば、自動運転中にAIがルート選択を誤り墜落した場合、製造者・ソフトウェア開発者・管制システム・機体所有者のいずれか、あるいは複数が責任を問われる可能性があります。これは自動車の運転者責任とは根本的に異なる複雑な問題です。
より具体的に想定してみましょう。もし新宿上空を飛行中の空飛ぶクルマが突然システム障害で墜落し、地上の建物や通行人に被害が及んだ場合、数十億円、数百億円規模の損害賠償が発生する可能性があります。この責任を製造者が負うのか、運航事業者が負うのか、それとも複数で分担するのか。現在の法制度では明確な答えがないのです。
7. 社会への影響――屋上が駅になる日
空飛ぶクルマが日常化すれば、都市の動脈は地上から空へ移ります。鉄道駅に代わり、高層ビルやショッピングモールの屋上にバーティポート(Vertiport)が整備され、「屋上=玄関」という新常識が生まれます。郊外の大型施設や病院にも空路の結節点が設けられ、都市の価値マップそのものが書き換わります。
図3 屋上が駅になる

誰が使える乗り物になるか
用途としては、まず都市内部の短距離移動が想定されます。筆者が参加したSkydrive社のQ&Aでは「現在の飛行時間は約10分で、将来的には15〜20分を目指す。航続距離は30〜40km、料金は夢洲〜新大阪で片道1〜2万円、最終的にはタクシーの約3倍の速さで2倍程度の料金を目標」と説明されました。
「タクシーの3倍速く、料金は2倍程度」であれば確かに魅力的です。渋滞に縛られない新しい移動手段として、都市生活の可能性を広げるかもしれません。
一方で、導入初期は機体やバッテリー、保険料、発着場のコストがかさみ、運賃はさらに高額になると考えられます。便数も限られ、予約制が前提となるでしょう。さらに混雑時にはサージプライシング(料金の値上げ)が発生し、結果的に「富裕層だけが時間を買える乗り物」になる懸念があります。
都市の再設計と格差の行方
バーティポートには避難経路や騒音対策など複合的な基準が必要です。駅前の価値が相対的に弱まれば、屋上を“空の駅前”として活用する都市計画も現実味を帯びます。高層マンションの屋上が発着場となり、都市構造そのものを変える未来が見えてきます。
しかし、その恩恵を誰が享受できるかは制度設計にかかっています。料金が高止まりすれば「空を使える人」と「使えない人」という新たな移動格差が生まれます。逆に、公共交通としての仕組みを組み込めば、時間をより公平にシェアできるインフラへと育つ可能性もあります。未来は「分断」か「共有」か、その分岐点に立っているのです。
8. 空の未来は誰が決める?――3つの選択肢
空飛ぶクルマは、技術的には現実味を帯びつつあるものの、法制度はまだ追いついていません。これから私たちが選ぶ道は、大きく3つに整理できます。
- 民間主導モデル:規制を最小限に抑え、企業の技術開発と市場原理に委ねる(規制サンドボックスの活用)
- 官民協調モデル:厳格な資格制度で安全を確保しつつ、段階的に普及を進める(限定空域の解放や特定免許制度)
- 公共主導モデル:国や自治体が主導し、公共サービスとして展開する(運賃規制や第三者賠償保険の義務化)
直面する主要課題は明らかです。
- 自動運転・遠隔操縦時代における責任の所在
- 高額運賃による移動格差の是正
- 空域の管理ルールと優先権の決定
- 国際制度との整合性
空飛ぶクルマは「富裕層だけの高速道路」になるのか、それとも「誰もが利用できる公共空間」になるのか。制度設計次第で未来の姿は大きく変わります。
そして、その制度は「誰かが決めてくれる」ものではなく、社会全体の合意形成の積み重ねによって形づくられていきます。鉄道や自動車がそうであったように、空飛ぶクルマもやがて私たちの生活を一変させるかもしれません。
あなたなら、この未来をどう設計するでしょうか。
2024年5月15日に、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第32号、以下「改正法」といいます。)が成立し、同年同月22日に公布されましたが、以下の3点に係る改正について、2025年5月1日から施行されました。
①投資運用関係業務受託業に関する規定の整備
②投資運用業に関する規定の整備
③非上場有価証券特例仲介等業務に関する規定の整備
これらは、我が国資本市場の活性化に向けて資産運用の高度化・多様化を図る、具体的には、投資運用業の新規参入を促進し、またスタートアップ等が発行する非上場有価証券の仲介業務への新規参入を促進し、非上場有価証券の流通を活性化させること等を目指したもので、投資運用業登録要件を緩和する規定の整備、またスタートアップ企業等の非上場企業の株式のセカンダリー取引等を活性化するため、非上場有価証券の取引の仲介業務に特化する等一定の要件を充足する場合は、第一種金融商品取引業の登録等要件等を緩和する等、非上場有価証券特例仲介等業務に関する規定の整備が行われました。
(2)では、③非上場有価証券特例仲介等業務に関する規定の整備について概説します。
1. 非上場有価証券特例仲介等業務に関する規定の整備
非上場有価証券の仲介を業として行うためには、原則として、第一種金融商品取引業の登録を受けることが必要ですが(金商法第28条第1項第1号、第29条)、非上場有価証券の流通活性化を目的として、非上場有価証券の取引の仲介業務への新規参入を促すため、今回の改正で、一定の要件を充足する非上場有価証券の仲介業務を「非上場有価証券特例仲介等業務」とし、非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合の登録要件等が緩和されました。
(1) 非上場有価証券特例仲介等業務の内容
「非上場有価証券特例仲介等業務」とは、第一種金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいいます(金商法第29条の4の4第8項)。
(i) 非上場有価証券(金融商品取引所に上場されていない有価証券で、店頭売買有価証券を除きます(金商法施行令第15条の10の4)。以下同じです。)に係る次に掲げる行為
① 売付けの媒介又は有価証券の募集・売出しの取扱い若しくは私募若しくは特定投資家向け売付勧誘等の取扱い(一般投資家[2] を相手方として行うもの及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家のために行うものを除きます。以下「1号仲介業務」といいます。)
② 買付の媒介(一般投資家のために行うもの及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家を相手方として行うものを除きます。)
(ii) (i)に掲げる行為に関して顧客から金銭の預託を受けること((i)に掲げる行為による取引の決済のために必要なものであって、当該預託の期間が、顧客から金銭の預託を受けた日の翌日から1週間(金商法施行令第15条の10の5)を超えないものに限ります。)
なお、「金融商品取引所に上場されていない有価証券」の「金融商品取引所」とは、金商法第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいうことから(パブコメ回答No.37)、かかる金融商品取引所に上場されていない有価証券(例えば、海外でのみ上場されている有価証券等)も「金融商品取引所に上場されていない有価証券」(非上場有価証券)となります。
(2) 登録要件等の緩和
非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合、以下のとおり各規制が緩和されます。
(i) 兼業規制
第一種金融商品取引業の登録を受けるためには、他に行っている事業が付随業務(金商法第35条第1項各号に定める業務その他の金融商品取引業に付随する業務をいいます。)若しくは届出業務(金商法第35条第2項各号に定める業務をいいます。)に該当し、又は承認業務として承認を取得できる見込みがあることが必要ですが(金商法第29条の4第1項第5号ハ)、非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合は、当該要件が適用されません(金商法第29条の4の4第2項)。
また、第一種金融商品取引業者は、届出業務を行う場合にはついて届出が、承認業務を行う場合については承認の取得が、それぞれ必要ですが(金商法第35条第3項及び第4項)、非上場有価証券特例仲介等業者については、これらの届出及び承認の取得が不要です(金商法第29条の4の4第3項及び第4項)。
(ii) 自己資本規制比率規制
第一種金融商品取引業の登録を受けるためには、自己資本規制比率が120%以上であることが必要ですが(金商法第29条の4第1項第6号イ)、非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合は、当該自己資本規制比率が適用されません。そのため、登録申請の際に添付する誓約書において、自己資本規制比率に係る誓約は不要とされ(金商法第29条の4の4第1項)、また自己資本規制比率を算出した書面の提出が不要とされています(業府令第10条第1項第3号括弧書き)。
また、第一種金融商品取引業者は、毎月、自己資本規制比率を算出してこれを届け出る義務があり、かつ、自己資本規制比率120%を下回ることがないように維持する必要がありますが(金商法第46条の6第1項及び第2項)、非上場有価証券特例仲介等業者については、これらの制限が適用されません(金商法第29条の4の4第5項)。
(iii) 金融商品取引責任準備金の積立て義務
第一種金融商品取引業者には、金融商品取引責任準備金の積立て義務があり、その使途も制限されていますが(金商法第46条の5)、非上場有価証券特例仲介等業者については、金融商品取引責任準備金の積立義務がありません(金商法第29条の4の4第5項)。
(iv) 最低資本金及び純財産要件
第一種金融商品取引業の登録を受けるためには、最低資本金及び純財産の額は5000万円以上であることが必要ですが(金商法第29条の4第1項第4号イ及び第5号ロ、金商法施行令第15条の7第1項第3号及び第15条の9第1項)、非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合は最低資本金及び純財産の額が1000万円以上に引下げられました(金商法施行令第15条の7第1項第6号)。
(v) 人的要件
第一種金融商品取引業の登録を受けるためには、常勤役職員の中に、その行おうとする第一種金融商品取引業の業務を3年以上経験した者が複数確保されていることが求められていますが(金商業者向け監督指針IV-4-1(2)①ハ)、非上場有価証券特例仲介等業務のうち、特定投資家を相手方として行う1号仲介業務(私設取引システム運営業務(金商法第2条第8項第10号)を除きます。)のみを行う場合には、常勤役職員の中に、その行おうとする第一種金融商品取引業の業務(金商法第29条の5第2項に規定する業務を含みます。)を1年以上経験した者が1名以上確保されていればよいこととされています(金商業者向け監督指針IV-4-1(2)①ハ(注))。
(vi) 投資者保護基金への加入義務
第一種金融商品取引業は、いずれかの投資者保護基金に会員として加入する義務がありますが(金商法第79条の27)、非上場有価証券特例仲介等業者については投資者保護基金の加入義務が免除されています(金商法施行令第18条の7の2)。そのため、投資者保護基金に加入しない場合は、登録申請書への記載も不要です(業府令第7条第3号ロ)。
(3) 適切性の確保
(2)のとおり、非上場有価証券特例仲介等業者については登録要件が一部緩和されていることから、その範囲を超えた第一種金融商品取引業を行うことがないよう、以下のような措置を取ることが求められています(業府令第70条の2第10項、監督指針IV-3-6(1))。
(i) 一般投資家を相手方として及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家のために売付けの媒介又は法第2条第8項第9号に掲げる行為(有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い)を行うことを防止するための必要かつ適切な措置がとられていること。
(ii) 一般投資家のために及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家を相手方として買付けの媒介を行うことを防止するための必要かつ適切な措置がとられていること。
(iii) 顧客から金銭の預託を受ける場合には、(1)(ii)の金銭の預託として適切に管理するための措置がとられていること。
また、非上場有価証券特例仲介等業務の担当者が第二種金融商品取引業の担当を兼務する場合には、第二種金融商品取引業に係る顧客に一般投資家が含まれているかどうか、含まれている場合には第二種金融商品取引業に係る一般投資家である顧客に対して非上場有価証券特例仲介等業の範囲を超えた第一種金融商品取引業が行われないよう、非上場有価証券特例仲介等業務を行う前の顧客の属性の事前確認が求められています(金商業者向け監督指針IV-3-6(1))。
(4) 日本証券業協会への加入
日本証券業協会に加入する場合、第一種金融商品取引業者は会員となりますが(日本証券業協会の定款第5条第1号、第11条第1項)、非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う者は特定業務会員となります(同定款第5条第2号ニ、第13条第1項)。また、入会金は原則として100万円ですが、非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う者は50万円で(定款の施行に関する規則第10条第1項及び第2項)、定額会費も1特定業務会員につき月額7万円のところ、非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う者は月額3万5,000円と軽減されています(特定業務会員会費規則第3条第1項第1号)。
他方、非上場有価証券特例仲介等業務の内部管理を担当する内部管理統括責任者、同業務を行う営業単位の内部管理責任者及び同業務に関する内部管理部門に所属する管理職者は「外務員等資格試験に関する規則」による会員内部管理責任者資格試験(以下「会員内部管理者責任者資格試験」といいます。)の合格者に限られ(協会員の内部管理責任者等に関する規則(以下「協会員内部管理責任者等規則」といいます。)第6条第4項、第14条第3項及び第7条第2項)、非上場有価証券特例仲介等業務を行う営業単位の営業責任者は、平成18年4月1日改正前の「証券外務員等資格試験規則」による会員営業責任者資格試験又は会員内部管理者責任者資格試験の合格者に限定されており(協会員内部管理責任者等規則第11条第3項)、他の特定業務会員より各責任者等の資格が限定されています。また、非上場有価証券特例仲介等業務に関する内部管理業務に従事する従業員について、会員内部管理責任者資格試験の合格者となるよう努める義務があります(協会員内部管理責任者等規則第7条第2項)。
留保事項
- 本書の内容は関係当局の確認を経たものではなく、本書作成日現在、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。
- 本書は当事務所ウェブサイト掲示用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律アドバイスが必要な場合には、各人の法律顧問にご相談下さい。
[2] 「一般投資家」とは、特定投資家等、当該有価証券の発行者、当該発行者の取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事若しくはこれらに準ずる者若しくは使用人(以下「特定役員等」といいます。)又は当該特定役員等が総議決権の50%超の議決権を保有する法人その他の団体(以下「被支配法人等」といいます。)、当該発行者の総株主等の議決権の50%を超える議決権を自己又は他人の名義をもって保有する会社以外の者をいいます(金商法第29条の4の4第8項第1号、金融商品取引業に関する内閣府令第16条の3第1項及び第3項)。なお、特定役員等及びその被支配法人等があわせて他の法人その他の団体の総株主等の議決権の50%を超える議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合も当該特定役員等の被支配法人等とみなされます(同条第2項)。
1. ガンダムから始まる思考実験
「宇宙で子どもが生まれたら、その子の国籍は?軌道エレベーターで殺人事件が起きたら、誰が裁く?スペースコロニーで労働争議が起きたら、適用される労働法は?」
一見するとSFの話のようですが、実は私たちのすぐ近くにある「未来の現実」かもしれません。
私は現在大阪・関西万博に繰り返し足を運んでいます。
前回は石黒浩教授のアンドロイド展示からインスピレーションを受け「アンドロイドになった『私』は同一人物か?」[https://innovationlaw.jp/android-law/]というブログを書きました。
そして、今回訪れたのがガンダムパビリオンhttps://www.expo2025.or.jp/domestic-pv/bandai-namco/です。ガンダムといえば、モビルスーツによる戦争と人類の宇宙進出を描いたSFアニメの金字塔ですが、万博パビリオンでは、モビルスーツが建設や農業、宇宙ゴミの回収などに使われる平和な未来が描かれています。観客はエリア7(ガンダム用語で地球のこと)の夢洲から軌道エレベーターに乗って、スペースコロニーへ向かう仮想体験をします。
その体験をしながら、こんなことを考えていました。
「これ、展示だと短時間で宇宙に着くけど、現実なら何日もかかるよね。その間に何かが起きたら、どこの法律が適用されるんだろう?
そもそも、軌道エレベーターって乗り物なの?建物なの?
ガンダムの世界ではスペースコロニーが地球から独立してるけど、地上とつながってる場合はどこの領土になるんだろう?」
前回のブログでは「人間の境界」が曖昧になる未来について、法がどうあるべきかを問いかけました。今回は「空間の境界」が曖昧になる未来、すなわち宇宙において、どこの国が、誰に、どう届くのかをめぐって、法的な視点から思考実験を試みたいと思います。
図1 軌道エレベーターとスペースコロニー(AI作成イメージ)

2. 出産はどこの国で?-軌道エレベーターと「空間の国籍」
(1) 宇宙への入り口は「赤道直下」限定
軌道エレベーターで出産が起きたとします。陣痛が始まったのは地上から1万キロの地点。赤ちゃんが生まれたのは2万キロの地点でした。
この子の国籍を決める前に、まず考えなければならないのは「そもそも、そのエレベーターはどこに建っているのか?」という問題です。
実は、軌道エレベーターには意外な物理的制約があります。静止軌道の関係で、赤道直下にしか建設できないのです。つまり、日本のような場所では物理的に建設不可能。エクアドル、ケニア、インドネシア、ブラジル、コンゴなどの赤道直下の国でなければ建設できません(この点はパビリオンでも説明されます)。
(2) 技術を持つ国 vs. 土地を持つ国
ここで面白い(そして複雑な)構造が生まれます。
軌道エレベーターを建設する技術と資金を持っているのは、主にアメリカ、ヨーロッパ諸国、中国、そして日本だと思われます。しかし、物理的に建設できる場所を持っているのは、赤道直下の国々。つまり、「技術を持つ国」と「土地を提供する国」が必然的に分離してしまうのです。
冒頭の出産の例に戻ると、もしアメリカがエクアドルに軌道エレベーターを建設していた場合:
- エレベーターの所有者:アメリカ?
- 土地の提供国:エクアドル
- 出産場所の管轄権:どちら?
これは単純に「どちらかの国籍」では解決できない複雑さを孕んでいます。
表1:軌道エレベーターの構造と管轄の境界

(3) 宇宙への「玄関口」を誰が管理するか
軌道エレベーターは単なる輸送設備ではありません。地球と宇宙を結ぶ唯一の「玄関口」として、政治・経済・安全保障上の極めて重要な戦略インフラとなります。
地球と宇宙の物流・通信がこの一点に集中するため、エレベーターを管理する国は宇宙経済において圧倒的な優位性を持つことになります。また、宇宙空間での活動を事実上コントロールできる立場に立つのです。
こうした状況は、現実の宇宙開発においても「軌道上からの優位性」という深刻な国際問題を引き起こす可能性があります。
(4) パナマ運河型「租借モデル」の再来?
では、地理的に建設できる赤道国と、技術を持つ先進国がどう協力するべきか。よく引き合いに出されるのが、20世紀初頭にアメリカがパナマに建設したパナマ運河の事例です。
当時、アメリカはパナマから99年間、運河地帯を租借し、実質的な主権と軍事的管理権を持ちました。軌道エレベーターでも、「土地と空間を長期間借りる形(租借)」で建設・運用するというモデルが想定されます。
ただし、軌道エレベーターは単なる地上施設ではありません。地表から35,000kmの宇宙空間までを貫通する構造です。単なる地上の借地契約では済まず、領空・未定義上空・宇宙空間の利用を含めた契約が必要になります。おそらく史上最も縦に長い法的取り決めが生まれることでしょう。
(5) 現実的な解決策を模索する
現在、軌道エレベーターの法的研究では、いくつかの代替案も検討されています。
日本宇宙エレベーター協会などは「赤道直下の海上に建設する」ことで領土問題を回避する案を提示していますが、海洋法は上空利用を想定しておらず、新たな法的課題を生みます。
また、日本の航空宇宙学会などからは「複数国による国際コンソーシアム形式での建設・運営」が提案されています。国際宇宙ステーションのような多国間の制度設計によって、単独国家の独占を避けながら宇宙インフラを運営するモデルです。
いずれにせよ、軌道エレベーターは「どこに建てられるか」という物理的制約が、「誰とどう法的に協力するか」を決定づける構造を持っています。技術の制約そのものが、新たな国際制度設計を促しているのです。 次章では、このエレベーターが通る「空間そのもの」——すなわち、領空・宇宙空間・その間の未定義領域で、どのような法的問題が生じるかを掘り下げていきます。
3. 殺人事件が起きたのは何km地点?-「超上空」のグレーゾーン
(1) 1万キロ地点は「どこの国」なのか?
軌道エレベーターで殺人事件が発生しました。容疑者は逮捕されましたが、事件が起きたのは地上から1万キロの地点。ここで問題になるのは「その場所は、そもそもどこの国の法律が適用される空間なのか?」ということです。
実は、この問いに対する明確な答えは存在しません。なぜなら、軌道エレベーターは「どこからどこまでが誰の主権か分からない空間」を35,000kmにわたって貫通する構造だからです。
(2) 大陸横断鉄道のように変わる法域
軌道エレベーターの特殊性は、大陸横断鉄道と似ています。鉄道が国境を越えるたびに適用される法律が変わるように、軌道エレベーターも高度を上がるにつれて法域が変わっていくのです。
ただし決定的な違いがあります。鉄道なら国境という「線」で法律が切り替わりますが、軌道エレベーターの場合、どこからどこまでがどの国の法律なのか、その境界線自体が曖昧なのです。
飛行機であれば1つの国の法律が適用される。これに対し、一本の構造物でありながら、地上→領空→宇宙空間と、垂直移動に伴って法的な世界が段階的に変わっていく——これまでにない極めて特異な存在なのです。
(3) 主権の届く空の限界
まず驚くべき事実から。国家の「領空」がどこまで及ぶのかは、実は国際法で明確に決まっていません。
確実に主権が及ぶのは、旅客機が飛ぶ高度──おおよそ10〜12km程度まで。それより上空の成層圏や中間圏(12〜100km)については、「たぶん領空だろう」という曖昧な状態です。
(4) 宇宙条約と「宇宙空間」の定義
1967年の宇宙条約では「宇宙空間に主権は及ばない」と定められています。しかし、ここにも問題があります。
そもそも「どこからが宇宙空間」なのかが決まっていないのです。
- アメリカ:高度80km以上を宇宙とする
- 国際航空連盟:高度100km(カルマンラインと呼ばれます)を境界とする
- 宇宙条約:特に定めなし
この曖昧さが、軌道エレベーターのような「地上と宇宙を連続的に結ぶ構造物」には致命的な問題となります。
(5) 法的空白を貫通する構造物
軌道エレベーターは一本の連続した構造物です。しかし、それが通過する空間は:
表2:宇宙空間における法律の適用範囲(概念図)
| 高度帯 | 法的性質 | 現行法で適用される可能性のある法律 |
| 地表〜12km | 確実な領空 | 建設地国の刑法・民法 |
| 12km〜50km | 実質的領空 | 建設地国の法律(推定) |
| 50km〜100km | 未定義空間 | 不明 |
| 100km以上 | 宇宙空間 | 宇宙条約+施設の登録国の法律 |
となります。冒頭の殺人事件の例では、1万キロ地点は明らかに宇宙空間なので、そのエレベーターを「登録」した国の法律が適用される可能性が高いでしょう。しかし、100km地点なら?これはまさに「法の空白地帯」での犯罪となってしまいます。
(6) ケーブル1本に複数の法体系?
現実的には、軌道エレベーターを高度別に「ここからここまではA国法、ここからはB国法」と切り分けて管理することは不可能です。
構造物全体を統一的にどの法的枠組みで扱うかが、軌道エレベーター建設における最大の法的課題の一つです。単独国による管理か、多国籍企業による運営か、それとも国際機関による統治か——その選択によって、宇宙への「法的な入り口」の性格が決まることになるでしょう。
次章では、この軌道エレベーターの先にあるスペースコロニーで、より複雑な法的問題が生じることを見ていきます。
4. ストライキは合法か? -スペースコロニーの労働法制
(1) モビルスーツパイロットの権利は誰が守る?
スペースコロニーの外壁建設に従事するモビルスーツパイロットたちが、宇宙空間での危険作業に対する特別手当の支給を求めてストライキを起こしました。
彼らの要求は正当なものです。宇宙空間での建設作業は、地上の何倍もの危険を伴います。しかし、ここで問題になるのは「この労働争議はどこの国の労働法で解決されるべきか?」ということです。
実は、この問いに答えるためには「そのスペースコロニーがどこの『国籍』を持っているか」を知る必要があります。しかし、宇宙施設の国籍を決める現行制度は、将来のスペースコロニーにはとても対応できない複雑さを抱えているのです。
(2) 現行の「登録国主義」とその限界
現在の宇宙法では「登録国主義」というルールがあります。宇宙に打ち上げられた人工物(衛星、宇宙船、宇宙ステーション)は、それを打ち上げた国または打ち上げを委託された国が「登録国」となり、その国が管轄権と責任を持つことになっています。
国際宇宙ステーション(ISS)では、この原則が比較的うまく機能しています。日本の実験棟「きぼう」では日本法が、ロシアのモジュールではロシア法が適用される「区画主義」です。
しかし将来のスペースコロニーは、各国がモジュールを持ち寄る研究施設ではありません。一つの大きな「宇宙都市」として、住宅、商業施設、病院、学校、工場などが一体化された社会インフラです。従来の「打ち上げ国=登録国」というシンプルなルールでは対応不可能なのです。
(3) 複数国が関わる複雑な建設体制
スペースコロニーの建設・運営は極めて複雑な国際体制になることが予想されます。
例えば、資金提供は欧州宇宙機関・NASA・JAXA・民間投資ファンドの合弁、建設はSpaceX(米)・三菱重工(日)・Airbus(欧)の共同事業、部材の打ち上げは各国のロケットを使い分け、最終的な組み立ては軌道上で無人自動で行う——といった具合です。
この場合、冒頭のモビルスーツパイロットのストライキはどう扱われるのでしょうか?
- アメリカ企業雇用のパイロット → アメリカ労働法?
- 日本企業発注の建設工事 → 日本労働法?
- 欧州出資のプロジェクト → EU労働法?
どれが正解かわからない——これが現実になりうる問題なのです。
(4) 軌道エレベーター接続でさらに複雑に
軌道エレベーターでスペースコロニーが地上と物理的に接続されている場合、問題はより複雑になります。
従来の宇宙施設は宇宙空間に「浮かんでいる」ものでした。しかし地上と繋がったコロニーは「地上施設の延長」とも見なせます。エクアドルから延びる軌道エレベーターに接続されたコロニーで労働争議が起きた場合、登録国の法律か、接続地国の法律か、それとも特別な国際協約か ──選択肢が複数生まれてしまいます。
(5) 宇宙市民権という新しい概念
もし数万人がスペースコロニーで生活し、そこで子どもが生まれ、教育を受け、働き、結婚し、老いていくとしたら?
彼らの「国籍」はどうなるのでしょうか?
ガンダムでは、宇宙生まれの「スペースノイド」と地球生まれの「アースノイド」という区分が描かれていました。フィクションですが、実際にコロニーで生まれ育った人々の市民権・参政権・社会保障をどう扱うかは、現実的な制度設計の課題となるでしょう。
宇宙労働者の権利を誰が守るのか?この問いは、やがて「宇宙市民の権利を誰が守るのか?」という、より根本的な問題へと発展していくのです。
【コラム:コロニーが攻撃されたら誰が守るのか?】 |
|
スペースコロニーの法的地位を考える上で避けられないのが、軍事・安全保障の問題です。 現行制度では: 制度設計が必要 |
【コラム:AIパイロットに人権はあるか?(思考コラム)】 |
| 万博ガンダム館では、ある有名パイロットの思考や人格を再現したAIが登場します。絶体絶命のシーンで現れたモビルスーツが、AIパイロットにより観客を救い出すのです。ここで一つ問いかけてみたいと思います──このAIに、人格や人権はあるのでしょうか? AIは、過去の発言や行動から学習し、“その人らしい”ふるまいを模倣します。しかし、それは本人ではなく、あくまで“らしさ”を再現したソフトウェアです。 現在の法制度では、AIに人格権や人権は認められていません。責任主体にもならず、あくまで所有物として扱われています。 しかし将来、自己認識や判断能力を備えたAIが登場し、たとえば宇宙空間で人命救助を行い、「自己犠牲」を選ぶような存在となったとき──私たちはそれを、依然として“ただの道具”と呼べるのでしょうか? AIパイロットは、放射線や真空といった過酷な環境でも活動でき、人間以上に重要なパートナーになる可能性があります。 そのAIが、誰かを救い、誰かを選び、自らを犠牲にしたとしたら── それはただの機械か、それとも「誰か」なのか。 未来の法と倫理は、いずれこの問いから目を背けることができなくなるのかもしれません。 |
5. 宇宙法は未来に追いつけるか?─制度設計に向けた提言
万博のガンダム館で見た未来の宇宙インフラは、決してSFではありません。軌道エレベーターは2050年代の実現が予想され、宇宙コロニーも今世紀中には現実となる可能性があります。
しかし、1967年の宇宙条約は、軌道エレベーターも宇宙コロニーも条約制定者の想像の範囲外でした。物理的制約による地政学的不平等、主権の及ぶ範囲の曖昧さ、複雑な責任関係 ──これらはすべて、技術進歩が既存の法制度を追い越した結果です。
日本が宇宙開発における法的ルール作りをリードするためにも、万博で見た未来が現実になる前に、法的な準備を整える時が来ているのです。
参考文献
- 宇宙条約(Outer Space Treaty, 1967年)
- 宇宙損害責任条約(1972年)
- 国際宇宙ステーション協定(ISS IGA)
- アルテミス合意(Artemis Accords, 2020年)
- 米国商業宇宙打上げ競争力法(2015年)
- 日本宇宙エレベーター協会「宇宙エレベーターQ&A集」 https://www.jsea.jp/about-se/what-is-spaceelevator-08.html
- 甲斐素直「宇宙エレベータ法,その海法,空法及び宇宙法との関係」 https://www.jstage.jst.go.jp/article/kjsass/63/8/63_KJ00010017063/_pdf/-char/ja
2024年5月15日に、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第32号、以下「改正法」といいます。)が成立し、同年同月22日に公布されましたが、以下の3点に係る改正について、2025年5月1日から施行されました。
①投資運用関係業務受託業に関する規定の整備
②投資運用業に関する規定の整備
③非上場有価証券特例仲介等業務に関する規定の整備
これらは、我が国資本市場の活性化に向けて資産運用の高度化・多様化を図る、具体的には、投資運用業の新規参入を促進し、またスタートアップ等が発行する非上場有価証券の仲介業務への新規参入を促進し、非上場有価証券の流通を活性化させること等を目指したもので、投資運用業登録要件を緩和する規定の整備、またスタートアップ企業等の非上場企業の株式のセカンダリー取引等を活性化するため、非上場有価証券の取引の仲介業務に特化する等一定の要件を充足する場合は、第一種金融商品取引業の登録等要件等を緩和する等、非上場有価証券特例仲介等業務に関する規定の整備が行われました。
(1)では、①投資運用関係業務受託業に関する規定の整備、②投資運用業に関する規定の整備について概説します。
1.投資運用関係業務受託業に関する規定の整備
(1) 総論
2でご紹介する投資運用業の登録に関する人的体制整備の要件の緩和に伴い、投資家保護を軽視する事業者が委託を受けることがないよう(「金融審議会 市場制度ワーキング・グループ・資産運用に関するタスクフォース報告書」(以下「資産運用TF報告書」といいます。)6頁)、今回の改正で、投資運用関係業務受託業の登録制度が創設されました。
「投資運用関係業務受託業」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号、その後の改正を含む。以下「金商法」といいます。)の規定により投資運用業、適格機関投資家等特例業務(自己運用に限ります。)及び海外投資家等特例業務(自己運用に限ります。)(以下、総称して「投資運用業等」といいます。)を行うことができる者の委託を受けて、当該委託をした者のために以下の業務(金商法第2条第43項。以下「投資運用関係業務」といいます。)のいずれかを業として行うことをいい(金商法第2条第44項)、投資運用関係業務受託業を行う者のうち、内閣総理大臣の登録を受けた者を「投資運用関係業務受託業者」としています(金商法第2条第45項、第66条の71)。
- 運用対象財産(投資運用業等を行うことができる者が金商法第42条第1項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいいます。)を構成する有価証券その他の資産及び当該資産から生ずる利息又は配当金並びに当該運用対象財産の運用に係る報酬その他の手数料を基礎とする当該運用対象財産評価額の計算に関する業務(具体的には、(i)投資信託財産に係る計算及びその審査(投資信託財産の基準価額の算出及び当該算出に向けた投資信託の設定・解約の集計、資産の約定照合、利金・配当金等の計上等を含みます。)、並びに(ii)(i)のほか、運用対象財産の評価額の計算及びその審査があげられています(金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(以下「金商業者向け監督指針」といいます。)VI-3-1-1(7)①イ)。)(以下「計理業務」といいます。)
- 法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいいます。)を遵守させるための指導に関する業務(具体的には、(i)法令等遵守の観点から定期的な業務実態の把握、課題の指摘及び対応策の検討その他これに関連する業務、(ii)コンプライアンスに関する社内規則その他マニュアル等の案文作成・管理、並びに(iii)コンプライアンス研修の定期的な企画・実施その他コンプライアンスに関する情報の提供があげられています(金商業者向け監督指針VI-3-1-1(7)①ロ)。)(以下「コンプラ業務」といいます。)
投資運用関係業務受託業は登録を受けなくても行うことは可能ですが、2でご紹介するように、投資運用関係業務受託業者に投資運用関係業務を委託した場合に限り、投資運用業の登録要件が緩和されますので、人的体制整備に係る登録要件の緩和の適用を受けることを前提に投資運用業に参入しようとする事業者から投資運用関係業務を受託するためには、投資運用関係業務受託業の登録が必要となります。
(2) 登録
投資運用関係業務受託業者としての登録を受けようとする場合、以下の①の事項を記載した登録申請書を、以下の②の書類を添付して、提出する必要があります(金商法第66条の72、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号、その後の改正を含み、以下「業府令」といいます。)第348条から第350条)
①登録申請書記載事項
- 商号、名称又は氏名
- (法人の場合)資本金額又は出資の総額
- (法人の場合)役員の氏名又は名称
- 主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人の場合、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所)の名称及び所在地
- 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
- 業務の種別(計理業務又はコンプラ業務の別)
- 他に事業を行っているときは、その事業の種類
- 登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容
- (登録申請者が外国法人であって国内における代表者を定めていない者又は外国に住所を有する個人である場合)国内における代理人の氏名、商号又は名称
②添付書類
(i)法人・個人共通の添付書類
- 登録拒否事由(金商法第66条の74各号(但し、第2号から第5号まで、第7号ハ及び第8号ハを除きます。))に該当しないことの誓約書
- 以下を記載した投資運用関係業務受託業の業務方法書
- 業務運営に関する基本原則
- 業務執行の方法
- 業務分掌の方法
- 投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務の内容
- 業務管理体制(投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための社内規則等の整備及び当該社内規則等の遵守のための従業員に対する研修等の措置(業府令第358条第1号)を除きます。)の内容
- 投資運用関係業務受託業に係る投資運用関係業務を管理する責任者(以下「投資運用関係業務管理責任者」といいます。)の氏名及び役職名
- 業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面
- 投資運用関係業務管理責任者の履歴書
- 純財産額を算出した書面
(ii) 法人の場合の添付書類
- 定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含みます。)
- 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
- 役員(登録申請者が外国法人であって国内における代表者を定めていない者であるときは、国内における代理人を含みます。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
- 役員(登録申請者が外国法人であって国内における代表者を定めていない者であるときは、国内における代理人を含みます。)の旧氏名をあわせて登録申請書に記載した場合で、住民票の抄本等が当該役員の旧氏名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 役員の身分証明書又はこれに代わる書面
- 役員が欠格事由(法第29条の4第1項第2号ハからリまで又は第66条の74第7号イ(1))のいずれにも該当しない者であることの当該役員の誓約書
- 最終の貸借対照表及び損益計算書(いずれも関連する注記を含みます。)
(iii) 個人の場合の添付書類
- 登録申請者の履歴書
- 登録申請者(登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含みます。)の住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
- 登録申請者(登録申請者が外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人を含みます。)の旧氏名をあわせて登録申請書に記載した場合において、住民票の抄本等が当該登録申請者の旧氏名を証するものでないときは、当該旧氏名を証する書面
- 登録申請者の身分証明書又はこれに代わる書面
- 登録申請者の業府令別紙様式第1号の2による貸借対照表及び損益計算書
金商法第66条の74各号に定める登録拒否事由に該当する場合、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けている場合には、投資運用関係業務受託業者の登録は拒否されます(金商法第66条の74)。業務の種別以外の登録申請書の記載事項(上記の①)に変更が生じた場合は、その日から2週間以内に届出が必要であり(金商法第66条の75第1項)、業務の種別を変更しようとする場合は、変更登録を受ける必要があります(同条第4項)。また、登録申請の添付書類として提出した業務方法書に記載した業務の内容又は方法に変更があった場合も、遅滞なく届出を行うことが必要となっています(同条第3項)。以下の各事由に該当する場合には30日以内に届出を行う必要があり、かつ、投資運用関係業務受託業者の登録は効力を失います(金商法第66条の83)。
(i) 法人・個人共通の届出事由
- 登録を受けた投資運用関係業務受託業の廃止
- 投資運用関係業務受託業に係る事業の全部譲渡
(ii) 法人の場合の届出事由
- 合併による消滅
- 破産手続開始の決定による解散
- 合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散
- 分割による投資運用関係業務受託業に係る事業の全部の第三者による承継
(iii) 個人の場合の届出事由
- 投資運用関係業務受託業者の死亡
(3) 行為規制
投資家保護や業務の質の確保の観点から(資産運用TF報告書6頁)、投資運用関係業務受託業者には以下のような行為規制が課されています。
- 委託者に対する誠実義務(金商法第66条の76)
- 忠実義務(金商法第66条の77第1項)及び善管注意義務(同条第2項)
- 業務管理体制の整備義務(金商法第66条の78)
投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための業務管理体制として、以下の事項の整備が求められています(業府令第358条)。なお、各事項に関する留意点は投資運用関係業務受託業者向けの監督指針III-2-1に定められています。
- 投資運用関係業務受託業を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいいます。)の整備、及び当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置。
- 投資運用関係業務受託業者の業務の適正を確保するための措置。
- 登録を受けている投資運用関係業務に係る行為のうち、投資運用関係業務を委託する者(以下「投資運用関係業務委託者」といいます。)と投資運用関係業務受託業者又は第三者(当該委託者以外の委託者を含みます。)との利益相反行為の管理。
- 投資運用関係業務受託業に係る業務以外の業務に係る行為が投資運用関係業務に不当な影響を及ぼさないための措置。
- 投資運用関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための措置。
- 名義貸しの禁止(金商法第66条の79)
- 再委託の原則禁止(金商法第66条の80)
- 記録保存義務(金商法第66条の81)
投資運用関係業務受託業者は、以下の記録を作成し、当該記録を作成日((ii)については業務終了日)から10年間保存する必要があります(業府令第360条)。
(i)当該投資運用関係業務受託業者が行った投資運用関係業務に関する以下の(a)から(c)に掲げる事項に係る記録
- 投資運用関係業務を行った年月日及びその内容
- 投資運用関係業務の遂行の過程に関与した役員又は使用人の氏名及び投資運用関係業務の遂行について投資運用関係業務受託業者を代表して責任を有する者の氏名
- 投資運用関係業務の遂行に当たって委託者から提供を受けた情報
(ii)その委託を受ける投資運用関係業務に係る契約に関する記録
また、投資運用関係業務受託業者は、事業年度経過後3か月以内に事業報告書を提出する必要があります(金商法第66条の82)。
2.投資運用業に関する規定の整備
(1) 投資運用業の登録要件の緩和
投資運用業を行うためには、原則として「投資運用業」の登録が必要ですが、当該登録を行うためには最低資本金や人的体制の整備等の厳しい要件を満たすことが必要とされており、投資運用業への参入の障壁となっていました。そこで、我が国の経済成長と国民の資産所得の増加に繋げていく観点から、投資運用業者の参入を促進するため、以下の2点について、投資運用業の登録要件が緩和されることになりました。
(i) 人的体制の整備の緩和
従来、投資運用業の登録を行うためには、法令遵守等に関する業務を担う人材(いわゆるコンプライアンスオフィサー)を自社で採用する必要があり(適格投資家向け投資運用業を除き、外部委託は不可とされていました。)、かかる人材の確保が投資運用業の登録にあたり実務上負担となっていました。
そこで、今回の改正では、投資運用業者による当該業務等の外部委託が可能とされました。具体的には、金商法に基づき投資運用関係業務受託業者としての登録を受けた事業者に対し、投資運用関係業務を委託する場合には、当該業務を担う人材を自社で確保することを要せず、当該業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保すれば足りることとして(金商法第29条の4第1項第1号の2)、人的体制整備の要件が緩和されました。
「当該業務の監督を適切に行う能力を有する者」とは、投資運用関係業務受託業者に委託する投資運用関係業務の内容を理解し把握するとともに、当該投資運用関係業務受託業者に対して適確に指示を行う能力がある者をいい、当該投資運用関係業務を直接遂行するにあたって必要な知識及び経験並びに過去に投資運用業に関する業務に従事していた経験は問わないとされています(金商業者向け監督指針VI-3-1-1(1)①ニ)。具体的にどのような経験があればこれに該当するといえるのかは明確ではなく、今後の運用が注目されます。投資運用関係業務を委託する場合、登録申請書にその旨並びに委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容、並びに(登録を受けた投資運用関係業務受託業者に委託する場合は)投資運用関係業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保する旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称を記載することが必要になります(金商法第29条の2第1項第12号、金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の6)。なお、施行の際に現に投資運用関係業務を委託している金融商品取引業者については、施行日に変更があったものとみなして、施行日から6か月以内に変更届を行う必要があります(改正法附則第8条第1項)。
なお、上述のとおり、投資運用関係業務受託業者としての登録は任意で、登録を行わなくても投資運用関係業務を行うことは可能ですが、投資運用業の登録要件が緩和されるのは、投資運用関係業務受託業者としての登録を受けた事業者に投資運用関係業務を委託した場合に限定されていますので、実際には、投資運用関係業務受託業者としての登録を受けた事業者に委託が行われることが多くなるのではないかと推測されます。
(ii) 最低資本金及び純財産額要件の緩和
原則として、投資運用業(適格機関投資家向け投資運用業を除きます。)の登録を行うためには、資本金額及び純財産額が5000万円以上であることが必要とされていますが、今回の改正に伴い、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けず、かつ、自己と密接な関係を有する者[1]にもかかる預託をさせない場合には、最低資本金及び最低純財産の額が1000万円以上に緩和されました(金商法第29条の4第1項第4号イ及び第5号ロ、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号、その後の改正を含みます。以下「金商法施行令」といいます。)第15条の7第1項第4号及び第15条の9第1項)。また、その前提として、登録申請書に、金銭又は有価証券の預託の有無を記載することになりました(金商法第29条の2第1項第5号の2)。
顧客から金銭又は有価証券の預託を受けないこととは、投資運用業に関して現に顧客から預託を受けず、今後も預託を受ける意思がない場合が想定されています(金融庁「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(令和7年3月28日)(以下「パブコメ回答」といいます。)No.22)。
なお、顧客から金銭又は有価証券の預託を受けない既存の金融商品取引業者が、かかる例外の適用を受けるためには、施行日から6か月以内に変更登録の申請を行う必要があります(改正法附則第7条)。
(2) 運用権限の全部委託の許容
従来、投資運用業者は、すべての運用財産につき、その運用に係る権限の全部を委託することが禁止されていました(改正前の金商法第42条の3第2項)。しかしながら、欧米では運用の企画・立案をする事業者がファンドの運営機能に特化し、運用(投資実行)を全部委託する形態が一般的になっています(金融庁2024年3月「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料」3頁)。日本においても、かかるファンドの運営機能(企画・立案)に特化することを可能とすべく、今回の改正により、運用権限の全部委託を禁止する規定が撤廃され、運用権限の他の登録投資運用業者への全部委託が可能となりました。
運用権限の外部委託を行う場合、委託先の品質管理を適切に行うことが重要であることから(資産運用TF報告書7頁)、かかる外部委託を認める前提として、投資運用業者は、外部委託を行う場合、受託者に対し、運用の対象及び方針を示し、以下の①から③記載の、運用状況の管理その他の当該委託に係る業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければなりません(金商法第42条の3第2項、業府令第131条第2項、金商業者向け監督指針VI-2-2-1(1)④、VI-2-3-1(1)④及びVI-2-5-1(1)④)。
①委託先の選定の基準及び委託先との連絡体制の整備
②委託先の業務遂行能力及び委託契約の遵守の状況を継続的に確認するための体制の整備
③委託先が当該委託に係る業務を適正に遂行することができないと認められる場合の対応策(業務の改善の指導、委託の解消等)の整備
(3) 投資助言業の規制との比較
今回の改正により、投資運用業の規制が一部緩和されたことから、投資助言業の登録を行わず、又は投資助言業とあわせて投資運用業の登録を行うことを検討される事業者もいると推測されます。そこで、今回の改正により規制が一部緩和された事項が、投資助言業の規制と比較して、より緩和されたのかについて検討します。
(i)投資運用業の方が規制が緩和された点
今回の改正で投資運用業の規制が投資助言業の規制に比べて緩和された点は、投資運用関係業務を委託することができる点です。
投資運用関係業務は投資運用業等に関して行う業務に限定されており(金商法第2条第43項)、今回の改正により投資助言業において求められる人的構成要件に係る審査の運用が変更されるものではないとされていることから(パブコメ回答No.8)、仮に投資助言業の登録申請を行う者が、法令等を遵守させるための指導に関する業務を投資運用関係業務受託業者としての登録を受けた事業者に委託したとしても、投資助言業に係る業務につき、その執行について必要となる十分な知識及び経験を有する役員又は使用人を自ら確保しているとは必ずしも認められず、投資助言業の登録を受けるためには、かかる人材を自ら確保する必要があると判断される可能性があります。もっとも、パブコメ回答によれば、投資助言・代理業におけるコンプライアンス業務の外部委託の可否について、「個別事例ごとに実態に即して実質的に判断されるべきものと考えられますが、当局や当該業者への連絡体制などが構築できる場合等には、コンプライアンス業務を外部委託することが認められる場合もあるものと考えられます。」としており(同回答No.8)、投資助言・代理業におけるコンプライアンス業務の外部委託も必ずしも否定されていないと考えられていることから、一概に投資運用業の方が規制が緩和されたとはいえないところはありますが、法令上委託の要件が明確な点で、実務上投資運用業の方がコンプライアンス業務の外部委託を行いやすいのではないかと思われます。
(ii)投資運用業の方が規制が厳しい点
他方、今回の改正で緩和された以下の点については、改正後も投資運用業の方が、投資助言業より厳しくなっています。ただし、二点目については、外部委託を許容する以上、委託元である投資運用業者による外部委託先の投資運用業者の監督が適正になされなければならないことは自明であり、必ずしもそれ自体が重大なハードルになる可能は高くないと思われます。
・最低資本金及び純財産要件
金銭又は有価証券の預託を受けない場合、最低資本金及び純財産の額が緩和されましたが、最低資本金額及び純財産の要件自体は維持されます。これに対し、投資助言業については最低資本金及び純財産の要件はありません。
・運用権限の全部委託
今回の改正で運用権限の全部委託が可能となりましたが、委託を行う場合、委託に係る業務の適正な実施を確保するための措置等を講じる等の義務が課されています。これに対し、投資助言業については外部への委託について特に制限はありません。
留保事項
- 本書の内容は関係当局の確認を経たものではなく、本書作成日現在、法令上、合理的に考えられる議論を記載したものにすぎません。
- 本書は当事務所ウェブサイト掲示用に纏めたものに過ぎません。具体的案件の法律アドバイスが必要な場合には、各人の法律顧問にご相談下さい。
[1] 有価証券等管理業務を行う金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関、保険会社(外国保険会社等を含みます。)、信託会社及び株式会社商工組合中央金庫以外の者で、以下に該当する者をいいます(金商法施行令第15条の4の2、業府令第6条の2)。
・当該登録申請者の役員(役員が法人の場合の職務執行を行う社員を含みます。)又は使用人
・当該登録申請者の親法人等又は子法人等
・当該登録申請者の総株主等の議決権の50%を超える議決権を保有する個人